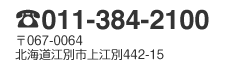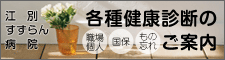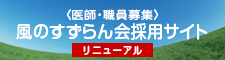- ホーム(法人トップ) >
- 江別すずらん病院 >
- コラム >
- コラム2014年12月「★連載小説★Medical Wars 第9話」
コラム
コラム2014年12月「★連載小説★Medical Wars 第9話」
Medical Wars (福場将太・著)
*この小説はフィクションです。
■第9話「最高のクリスマス・イブ」(救命救急)
1
さて、季節は冬…タイトル通り12月24日である。今年はイブが金曜日、恋人たちにとっては最高の週末だ。いくつものロマンスがあちこちでキャンドルライトに浮かぶことだろう。しかしこれはご存じ医学生の物語、そんなに甘くはございません。しかも我らが14班が今週回っているのは救命救急…実際に働くドクターにとってはもちろん、学生にとっても過酷なことで知られる科だ。
ここでのポリクリはレポートや口頭試問などない代わりにとにかく実戦。実践ではなく実戦だ。救命救急医療はまさに戦場、最終日の今日もとにかくその現場に立って実戦なのである。6人は2人ずつ3つのチームに分かれ、救急車・外来・当直のいずれかの実習に当たる。では12月24日のチーム分けはと言いますと…。
同村・美唄は救急車実習。朝から南新宿消防署に待機し、出動する救急隊とともに同乗する。長・向島は外来実習。朝からすずらん医大病院の救命救急センターに詰めて訪れる患者を待ち受ける。そして井沢・まりかは当直実習。センターに来るのは昼からでよいのだが、そのまま翌日25日の朝まで待機…御愁傷様です。
そんなこんなで始まる今年最後の物語、彼らがどんなイブを過ごしたのかを見ていこう。ぜひ達郎さんのCDでも流しながらお楽しみ頂きたい。
この日の朝、長はいつものように新宿へとバイクを走らせていた。通学には片道1時間ほどかかる。本来なら病院近くに一人暮らしをしてもよい距離なのだが…彼は32歳の大学生、これ以上両親に負担をかけるわけにもいかない。またスネをかじっている分せめて実家で一緒にいてやりたいという想いもあった。
それならバイトでもしろよ、と思われるかもしれないが彼は私大の医学生…そんなことをしてもし留年でもすればそれこそ両親に負担をかけてしまう。一刻も早く卒業すること、それが最優先事項なのだ。サラリーマンである父親が定年退職するのも数年先の話、それまでに自立しなくては…彼は毎朝老いていく両親の顔を見る度にそう思うのだった。
冷たい空気を切り裂きながらバイクは四ツ谷を抜け新宿に入る。靖国通りに差しかかると、歩道橋のアーチの向こうにはいつもの高層ビルたちが遠く霞む。ヘルメットの中にこぼれる溜め息…冬空の下でも人々はこの街で忙しなく行き交っている。彼もまたその一粒に過ぎなかった。
ふと見た腕時計は6時50分。向島との学生ロビー待ち合わせは7時半。こんなふうに集合の早い日は自宅で朝食はとらず途中の弁当屋でパンとコーヒーを買うのが彼のお決まり。バイクを道路脇に停め、その小さな店に足を踏み入れた。
「おはようございます!」
明るい声が疲れた男を迎える。
「どうも、おはようございます…長谷川さん」
長はヘルメットを小脇に抱えて挨拶を返す。24時間営業のこの店は、こんな早朝でも当たり前のように開いている。レジに立つ女性店員の歳の頃は30半ば、この時刻は1人で勤務のようだ。
「長さん今日も早いわね、ホホホ」
店名の入った青いエプロン姿で彼女は愛想よい笑顔を見せた。やや小太りなその体型が優しさと可愛らしさを引き立てている。
「今週は朝が早い科の実習なんですよ」
「あらそう、寒いのに大変ね」
2人の会話を聞いてもおわかりのように、彼はすっかり常連さんだ。
「長谷川さんこそいつ来てもこの店にいるじゃないですか。一体いつ休んでらっしゃるんですか?」
そんなことを言いながらパンを選ぶ。
「私は夜から朝までのシフトが多いからね。もうすぐあがって、子供を幼稚園に送ってから寝るの。そんで夕方起きて子供を迎えに行ってからまた出勤って感じ」
「お子さんも、お淋しいですね」
「まあうちは母子家庭だから、そのくらい働かないと生きていけないの」
それを聞いて長は肩身が狭くなる。手にしかけたカツサンドを一度棚に戻す。
「今夜はクリスマスだから本当は子供のそばにいてやりたいんだけどさ、こういう日ってちょっと給料いいから、ホホホ」
「お子さん、おいくつでしたっけ?」
「6歳…来年小学生。みやびっていうんだけど、まあ大きくなったら美人になるよ、私みたいに。なんて、ホッホホホ」
彼女…長谷川悦子はよく笑う。家事と仕事と子育てに追われおそらく自分の時間などほとんど持てずにいるのだろうに、そんなことはおくびにも出さない。長は合わせて笑いながらも彼女のすごさ、女の…母の強さを感じていた。
そこで悦子は少し後ろを振り向く。台の上に置かれた写真立て、その中で白いワンピースの少女が微笑んでいた。…みやびちゃんだろう。優しそうな女の子だ、と長は思う。それに、やはり悦子に似ている。その写真立ては深夜の一人勤務の時だけこっそりそこに置いていると彼女は言った。
「クリスマスにねえ、なんか流行のゲームソフトが欲しいって言っててね。何だっけ?そう、『フニー仮面の冒険』とかいうの。あの子、いつも留守番で淋しいから買ってあげようと思ってたんだけど…」
そこで残念そうな声になって続ける。
「今日発売で、しかも大人気だからずっと前から予約しておかないとダメなんだってね。私、そういうのよく知らないから…」
どう答えていいかわからず長は「そうですか」と返す。彼が少し暗くなってしまったのを見て、悦子はすぐに笑顔に戻った。
「まあ、私ドジだからね、ホホホ!」
「ハハハ…。え〜と、じゃあこれを」
無理に笑って商品を手渡す長。
「はい、タマゴサンドとコーヒーですね。毎度ありがとうございます!」
彼女はリズミカルにレジを打つ。
「240円です。そういえば長さんは結婚とかしないの?」
「いえいえ、僕はまだまだ未熟者ですから」
「こりゃ余計なことを言いました、ホホホ!はいこちら、商品になります」
代金と引き換えにビニール袋を受け取った彼に、悦子は「じゃあ、安全運転でいってらっしゃい!」と最後の元気をくれた。その明るさを背中に受けながら彼は暖かい店内から再び冷気の中に出る。
キーを回すと勢いよく唸りを上げるバイク、またがった彼は新宿の雑踏に紛れていく。排気ガスと人ごみに呑まれそうになる街、その片隅に見つけたこの弁当屋には小さな幸せが灯されていた。
*
午前10時、長と向島は救命救急センターにいた。ここは事故や急病のため生死の境をさまよう患者たちが運ばれてくる場所、迎えるスタッフも一分一秒を争っている。正直なところその最中で悠長に学生に指導している余裕などない。2人はできるだけ邪魔にならないよう壁際の定位置に立ち、緊迫の中で行なわれる処置を見守るしかなかった。
そして当然ながら、ここに運ばれてくる患者は助からないことも多い。心筋梗塞や脳血管障害、交通事故や転落事故…その病態は多岐に渡るが、死に一歩踏み込んだ患者を生に引き戻すことは並大抵ではない。すでに朝から5人の患者が運ばれ、4人が死亡していた。
「また…ダメだったね」
向島が小声で言う。長も「はい…ビルの窓拭きで6階から転落ですもんね」と真剣な表情で答えた。
実際にはここに到着した時点で手の施しようのない患者もいる。もしかしたら救急車が到着した時点ですでに心肺停止していたのかもしれない。それでも僅かな可能性に一縷の望みを託し、患者たちはやってくる。
今日2人目に運ばれてきた50代女性もそうだった。朝食中に胸を押さえて倒れたきり、彼女は帰らぬ人となった。この処置室で懸命な蘇生術が行なわれたがその瞳が再び開くことはなく、救急車に同乗した夫と娘は死亡診断後に室内に呼ばれた。横たわる最愛の家族に駆け寄り、何度も何度もその名前を呼び泣き叫ぶ…何もできない学生はその光景を直視することさえままならなかった。
…もしかしたら、今夜は家族でクリスマスを過ごす予定があったのかもしれない。来年には夫婦で旅行する計画もあったかもしれない。娘が彼氏をお披露目する日を楽しみにもしていただろう。
そんなことを考えながら長は3年前祖父の訃報を受けた時のことを思い出していた。死は嫌でも死を呼び起こさせる。自分の将来を最後まで心配してくれていた祖父、医学部に受かったことを誰よりも喜んでくれた祖父、医者になれた時一番に報告したかったのに…間に合わなかった。その棺の横で涙したあの日…それは彼が人前で泣いた初めての記憶だった。
そして彼は改めて感じる。多くの場合、死は突然訪れるのだと。心臓外科の実習で見たあの脈打つ心臓…それがいつ停止するかなど誰にもわからない。大晦日の最後の一秒まで、自分が無事来年を迎えられる保障などどこにもないのだと。
*
所変わって南新宿消防署。同村と美唄は用意された机でそれぞれ教科書を読んでいた。救急車実習では、救急隊が出動する時に同乗し隊員たちの実際の業務を体験する。よって、出動要請が来るまではひたすら待機となる。
現在午前11時。2人は9時からここにいるのだが、未だ要請はなし。周囲に隊員たちがいる部屋でペチャクチャおしゃべりをするわけにもいかず、無言で自習するしかなかった。
まあそもそもあの夜の告白以来、2人の間の空気はまだ淀んでいる。普段の実習ではそれほどでもないが、こうして黙って2人でいるとどうしても意識してしまう。あれだけ当たり前だった一緒に地下鉄で帰ることさえ、未だにどちらからも声をかけられずにいた。他の班員たちもそれを感じ取り、以前のように同村をからかうことはなくなった。それがさらに彼を惨めにするのだが…まあフラレた男とはそういうものです。精進しなさい、同村くん。
今回の実習ではそんな2人がペアになってしまったわけだが…これもジャンケンの結果だから仕方ない。
「来ないね…出動」
美唄が教科書に視線を落としたまま小声で言った。2人は小さな机に向かい合っているので聞こえないフリもできない。
「そ・そうだね…」
「先に回った班の人の話だと、ない時は全然ないらしいからまあ仕方ないね」
「う、うん」
「でも、出動がないのはいいことだよね。クリスマス・イブなんだし…みんな平和に過ごせた方がいいもんね」
美唄はゆっくり教科書をめくっている。同村はそんな姿を見て、また彼女の病気のことを考えてしまうが…それを表に出すわけにもいかない。苦肉の策で愚かなセリフを返すしかなかった。
「そうだね…今夜、ホワイトクリスマスになるかな?」
「何言うてんねん、にーちゃん」
後ろから太い声でそうツッコミを入れたのは古株救急隊員の佐野だ。彼は缶コーヒーを片手に苦みばしった顔で近付いてきた。
「雪が降ったら事故が増えるやんけ。今夜はクリスマスで人も多い、雪なんてとんでもあらへんわ」
大阪弁丸出しで話す彼の年齢は50歳くらい、とても体格がよくまさに体力勝負の救急隊員といった出で立ちだ。
「す・すいません」
同村は慌てて頭を下げる。すると途端に豪快な笑いが返された。
「ハハハ、別にええねん。にーちゃんらはまだ若いんや、クリスマスも楽しまなあかん。今日も6時には帰してやっから安心せえ」
そこでコーヒーを飲み、佐野は「んで、その後はそっちのねーちゃんとデートかいな?」と付け加えた。美唄が「やだ、違いますよぉ。そんなんじゃないんです」と笑う。
辛いな、同村。だが男は辛抱だ。佐野さんもう少し空気読んでよ!…って無理か。
「ハハハ、そりゃ失敬!」
佐野は笑いながら同村の肩を叩くが、そこで館内放送が流れた。
「入電中、入電中。南新宿4丁目のオフィス小池ビル34階で、40歳男性が会議中に倒れたとの通報。現在意識は回復しており麻痺などない様子。至急出動せよ」
「よっしゃ行くで、にーちゃん、ねーちゃん!」
コーヒーを放り投げ走り出す佐野。2人も慌てて席を立ちその後ろを追った。
乗り込んだ救急車はサイレンを打ち鳴らし飛び出していく。その車内は難破船のように激しく揺れる。進行方向横向きに座っていることもあり、乗り物に弱い者ならすぐに酔ってしまうだろう。
「にーちゃん大丈夫かいな?」
振動をものともせず佐野が言った。
「大丈夫です。行き先は、オフィスビルですよね?」
「その34階や。この辺りは高層ビルばっかりやから到着してもまた現場まで時間がかかってまう。まあ意識は戻っとるから大丈夫やとは思うけどな」
「それでも、こうやって出動するんですね」
「当たり前や」
佐野は言い切る。救急車のタクシー化が問題視される近年、同村にはこの言葉は少し意外だった。そして思い出す…いつかコンビニで買い物をしていた時に駆けつけてきた消防隊のことを。誤報や悪戯も多い、それでも通報の度に全速力で出動するのが仕事だとあの時の隊員も言っていた。同村はそこで唇を噛む。
救急車はさらにスピードを上げた。そして人と車が溢れる新宿の交差点を走っていく。
「救急車が通ります、御協力ください」
車外スピーカーで助手席の隊員が叫んだ。同村、そして美唄の緊張も否が応でも高まっていく。
到着、ドアが開いた瞬間水色の救急服姿の佐野が飛び出した。続いて2人の隊員もビルへ駆け込んでいく。それを追って同じ服を着た同村と美唄も走る…当然その左腕には『研修中』の黄色い腕章。
巨大なビルはエレベーターホールまでまず距離があり、34階に到着しても現場までまた長く複雑な廊下があった。
「遠藤さん、大丈夫?」
後ろを振り返りながら同村が言う。美唄は元気よく「大丈夫!」と返したが…先ほどから彼女は段差につまずいたり、傘立てを引っくり返したりしている。初めての場所、しかも薄暗く入り組んだこの場所では無理もないのだが、彼女が一度透明な自動ドアに正面衝突してからは同村も気が気でない。
「こんなの、日常茶飯事!」
美唄はぶつけたおでこを少し赤く腫らして笑う。そんな彼女を、同村はまた心の中で抱きしめてしまうのだった。
*
倒れた男性会社員は、本人は大丈夫と拒否したものの一応近くの病院に搬送された。検査では大きな異常なく、医師は疲労と栄養不足が原因だろうと診断した。
帰りの救急車の中、美唄はおでこをさすりながら言う。
「たいしたことなくてよかったね」
「そうだね。食事とか睡眠がかなり不規則だったみたい」
答える同村。続いてほっとした様子の佐野が言った。
「最近はカロリー食だけですませる奴が多いけど、やっぱ飯はちゃんと食べなあかん。ねーちゃんもダイエットには気をつけや」
「大丈夫で〜す。私、食べるの大好きですもん!」
と、笑顔100パーセントの美唄。そういえば最近顔がちょっと丸め…って、こりゃ失敬。
「そうかそうか。おりょ、どうしたんやそのおでこは?」
「さっきちょっとぶつけちゃいまして。私、ドジなんです」
「ハハハ、おもろいねーちゃんや。帰ったら冷やすもん貸してやるわ」
ふんぞり返って笑う佐野。こんな職務だからこそ、この豪快さが必要なのかもしれない。
*
所変わってすずらん医大の教育棟、いつもの学生ロビー。時刻は午後1時、そこは昼食を摂るポリクリ生で賑わっていた。
「おはよう、秋月さん」
ソファの彼女に井沢が声をかける。
「あ、井沢くん。おはようってもうお昼だよ」
「ごめんごめん。当直に備えてさっきまで寝てたからつい」
爽やか青年はそう返しながらまりかの正面に腰を下ろす。
「そっか、いいなあ。私も寝貯めしたかったけど朝目が覚めちゃって。だからここで自習してたの」
「さすが班長!まあ今日で救命救急は終わりだからあと一日頑張ろうよ。そういえばちょっと雨がちらついてきてたよ」
そこで彼女は窓の外を見る。
「本当だ。あんまり激しくならないといいね」
そんな会話をしながらやがて時刻は1時半に近付く。まりかが腕時計を見て言った。
「それじゃあ行きましょうか、明日の朝までの長い実習に」
「おっす、では長さんと向島さんの待つ救命センターにいざ参りましょう」
2人は立ち上がり、学生ロビーから駐車場に出る。少しずつではあったが、雨脚は強まりつつあった。
2
南新宿消防署。午後からも数回の出動があったがいずれも軽い貧血など命に別状のないものばかり。中には赤ちゃんの発熱に驚いて救急車を呼んでしまった母親もいたが、それも大事には至らなかった。その度に佐野は「何よりや」と笑う。彼にほだされたのか、同村と美唄も徒労の出動を「損した」ではなく「よかった」と思えるようになっていた。実はこういった感覚こそがポリクリの醍醐味であり、教科書ではけして学べないことなのである。
そんなこんなで午後5時半、署内の待機室で3人は机を囲んでいた。
「どや、救急車実習は?」
学生にも冷蔵庫の缶コーヒーを振舞って佐野が訊く。2人は「ごちそうさまです」とそれに口をつける。
「まあ今日はあんまり大変な出動がなかったから、物足りんかったかもしれんけど…」
「そんなことないです。とっても勉強になりました」
と、美唄。同村も深く頷く。
「それならよかった。このまま平和に一日終わってくれたらええにゃけど、でも雨も降っとるし夜になったらきっと出動は増えるやろな」
そうなんですか、と同村が相槌。
「せや…特に今夜はクリスマスの週末や。浮かれる奴や酔っ払いが増えればそれだけ事故も増えるからな」
そこで佐野がまた豪快に笑う。
「まあ安心せい。6時でにーちゃんとねーちゃんの実習は終わりや、ハハハ!せいぜい事故に遭わんようにデートしてくれよ」
「もう、だから違いますって!」
そんな談笑をしていると、再び館内放送が流れた。
「入電中、入電中。8丁目の路上で交通事故、乗用車が歩いていた少女と接触。少女は5から7歳、意識はなくショック状態。至急出動せよ」
聞き終える前に佐野は走り出していた。同村も立ち上がりながら「僕らも行ってよろしいですか?」と尋ねる。
「おう、最後の出動や、ついて来い!」
部屋を飛び出しながらそう叫ぶ佐野。2人もすぐに追って廊下に出たが、彼の背中はもう遥か彼方だった。この瞬発力…さすがです。
*
猛スピードで辿り付いた現場は、新宿の外れの小さな曲がり角。事故の原因としては、子供がいきなり飛び出したことと雨のせいでブレーキのかかりが甘かったことが推測された。正面衝突は避けられたものの少女は全身を強く打ち意識不明の重体だ。
「雨で体温が下がっとる、おい毛布や!早く!」
若い隊員に指示して持ってこさせると、佐野は太い腕で少女を毛布にくるませる。学生2人は邪魔にならぬよう少し離れて立つ。周囲には野次馬も集まっており、近くの交番の警官が意気消沈した運転手から事情を聴取していた。
「よし、ゆっくりや、首を動かすなよ!」
佐野は大粒の雨から少しでも庇うように少女を担架に乗せ、隊員たちは手際よく彼女を救急車に運び込んだ。
「親御さんはいらっしゃいませんか!」
間髪入れず佐野が叫ぶ。野次馬たちは顔を見合わせてどよめくばかり。同村も目を凝らして見回したが名乗りを上げる者はいない。美唄は小さく「どうして…?」と呟いた。
「仕方あらへん。では病院に向かいますから!」
そう警官に告げて佐野は救急車に乗り込む、2人もそれに続いた。警官の敬礼と誘導を受けながら車はその場を離れスピードを上げていく。そして車内では少女への処置が始まった。
病院へ向かう…といってもまずはその搬送先を探さなくてはならない。特に今回のように緊急手術が想定されるケースではそれに対応できる病院を見つける必要がある。
「佐野さん、讃武会病院も無理だそうです!別の事故でオペ室が埋まってるって…」
揺れる車内で若い隊員が声を荒げる。
「アホ、こっちは一分一秒を争っとんのや!え〜い、くそっ!」
佐野は般若のような形相で叫ぶ。また別の隊員が「血圧下がってます!」と報告した。学生はせめて邪魔にならないように救急車の隅で小さくなるしかない。美唄は両手を胸の前で組み、少女の命運をひたすら祈っていた。同村も少女の痛みを分け合うかのように強く歯を食いしばっている。
「脈拍と呼吸、ともに弱ってます!」
佐野は苦虫を噛み殺したような表情を浮かべたが、次の瞬間同村と目が合い何かを思い出した。
「そうや…すずらん医大、逆方向になるけどすずらん医大病院はどうや?裏道で行けばそんなに時間はかからん!」
「わかりました、連絡します!」
「絶対に取り付けろよ!」
もちろん救急車を受け入れない病院側も精一杯なのだろうが、受け入れさせる側も精一杯…これが救命救急医療の戦場である。
「もうちょっとの辛抱や、頑張れよお嬢ちゃん!絶対助かるで!」
酸素マスクを当てられた少女に佐野が言う。その瞬間何かが破裂したように美唄も「頑張って!」と叫んだ。同村も「頑張れ!」と続く。
「佐野さん、すずらん医大、大丈夫です!」
「よっしゃあ、Uターンして全力疾走や!」
救急車はサイレンを打ち鳴らし、車外スピーカーからは隊員の声が響く。
「救急車が通過します!ご協力お願いします!」
街で誰もが見かけたことがあるだろう、疾走していく救急車を。その内側には、外とはまるで違う極限状態の世界がある。夕刻となり新宿はますますクリスマスムードに染まる…流れる音楽、輝くネオン、サンタの衣装をまとった店員、寄り添う恋人たち。その前を通過する一台の救急車の中に、誰よりも奇跡を必要としている少女がいることをこの街は知らない。
*
少女はすずらん医大病院の救命救急センターに運び込まれた。画像撮影と並行して手術の準備も行なわれる。その慌しい渦中において、奇しくも14班の6人は集合することとなった。
「血圧下がってます!」
「昇圧剤もう1投!輸血全開!」
処置に当たっているのは、この一週間同村たちの指導をしてくれた藤原医師。学生は部屋の隅でそれを見守る。美唄は今も両手を胸の前で組んで祈り続けていた。
「先生、画像出せます!」
若い医師が叫ぶ。藤原が少しだけ処置の手を止めてそちらに駆け寄ると、パソコンには少女のレントゲンやCTの画像が表示された。
「脳は…大丈夫そうだな。肋骨もヒビは入ってるけど肺に刺さっては…いない。次、腹部出して」
後輩は手早くパソコンを操作する。藤原の目が見開かれ、その指は画面を差した。
「ここだ、肝損傷…そして脾臓破裂」
他の部位もチェックして彼は再び処置台に戻る。
「よしオペだ!おい、早く親に連絡しろ!」
「それが、身元がわからないんです。事故現場の近所の人に今警察が聞き込みをしてくれてるようですが…」
看護師が答えた。部屋の入り口には刑事らしき男の姿も見える。雨で濡れたボロボロのコートとハットを身にまとい、そこから処置の様子を見ているようだ。
「持ち物からわからねえのか?」
「何も持ってないんです…スカートのポケットに小石が入っているだけで」
「何だそりゃ!携帯電話とか何か持ってないのかよ!」
藤原は相当気が立っている…無理もない。その手にはこの幼い少女の命運が握られているのだから。彼は荒井口調のまま、当直以外の学生はもう帰るよう指示した。
「藤原先生、オペ室の準備できたそうです!」
駆け込んできた看護師が言う。
「よし、行くぞ!当直のポリクリはついて来い!」
井沢とまりかは雰囲気に圧倒されながらも、真剣な面持ちで「はい」と強く返す。間もなく少女を乗せたストレッチャーが運び出される。その時、長には初めて患者の顔が見えた。
…あれ?
小石を投げ込まれたように、彼の心が少し波立った。
*
少女が運び出された後の処置室は、嵐が過ぎ去ったように静まり返る。井沢とまりかもスタッフたちと出ていき、学生4人は未だ壁際に立ち尽くしていた。
「身元は…うちらもわからんのや」
入り口のところで佐野とあの刑事が話している。少し放心していた同村もそのやり取りを聞いて我に返った。
「今部下が近所の聞き込みをしていますので、わかり次第そちらにも連絡しますね」
と、刑事。佐野は「よろしく」と連絡先を伝えて室内に向き直った。
「お〜い、にーちゃんねーちゃん、署に戻るで」
同村と美唄は頷いて駆け寄る。そして長と向島に目で挨拶するとそのまま部屋を出ていった。もちろん少女の容態は佐野だって気になっている。しかし救急隊の仕事は送り届けるまで、それが終わったらまた署で次の出動に備えなければならない。
救急車がサイレンを鳴らさず走り去った頃、処置室にはいくらかのスタッフが戻り散らかった室内を片付け始めた…こちらもまた次の患者に備えなければならない。そう、あの少女が特別なわけではない。これが日常なのだ。
「僕たち実習終わりだったね。そろそろ行こうか」
そう言って向島がゆっくり歩き出す。長も合せて足を進めたが…数歩で立ち止まり、入り口の刑事に声をかけた。
「あの、女の子の身元は…やっぱりわからないんですか?」
本来なら刑事が学生の質問に答える義務はない。もしかしたらその外見から彼をプロのドクターだと思ったのかもしれない。刑事は「ええ」と頷き、身元に繋がる持ち物も親からの連絡もないことを告げた。
「せめて、名前でもわかれば探しようもあるのですが…」
「もしかしたら…洋服に名前とか入ってないですか?」
向島も足を止めて言った。
「手編みっぽいセーターでしたから、ひょっとして…」
「ナルホド…」
刑事はそう言うとツカツカと処置台に歩み寄り、看護師に了解を得て先ほど処置のために切り裂かれたセーターを手にした。長も引き返して隣でそれを見守る。
「う〜ん、名前名前…」
雨と泥、そして血が付着した布地を慎重に繋げていく。
「やっぱりないかな…あ、あった!胸の所にイニシャルが縫い付けてあるぞ」
学生は刑事の手元を覗き込む。
「ええと…MH」
そう読み上げられるのが早いか、彼は部屋から飛び出した。刑事も向島も驚いて振り返るがもうそこに長の姿はない。
そう、彼には嫌な予感がしていた。あの少女の顔を見た時から、どこか遠くから警鐘が聴こえていたのだ。もちろん一瞬見ただけ、しかも意識もなく酸素マスクを当てられた状態なので記憶に自信が持てなかったが…確かに見覚えがあった。
そう、今朝方あの弁当屋で見た写真立ての少女。MH…長谷川みやび。
ただの他人の空似かもしれない。事故現場と彼女の家が近いかどうかもわからない。でも、もしかして、もしかしたら…!
彼は教育棟に飛び込むとロッカールームに着ていた白衣を投げ捨て、バイクのキーを手に取る。そして駐車場に引き返した。
…頭に、娘のことを話す笑顔の悦子が浮かんだ。
理屈ではない。説明などできない。彼の心は…いや、彼の体は見えない力に操られるようにバイクにまたがる。威勢よく嘶いた愛車は荒馬のごとく豪雨の中に飛び込んでいった。
*
午後6時半。南新宿消防署で実習修了の印鑑をもらった2人は、佐野たちにお礼を言って建物を出た。日はとうに暮れている。バッグから折りたたみ傘を取り出した美唄に同村が「用意がいいね」とコメントする。
「一応持ち歩いてるの。さ、どうぞ」
彼女は開いた傘にそっと同村を招く。もちろんためらってしまう主人公。
「私だけ傘をさすわけにいかないでしょ。ほら、早く」
文字通り頭を下げて同村はそれに応じる。
「ありがとう、遠藤さん。でも大丈夫?君が濡れないかな」
「平気平気」
美唄は笑って歩き出す。おでこの腫れもひいてきたようだ。こんな時、男が傘を握るべきなのか…同村にはわからない。そんなことにも戸惑いながら並んで歩いていく。
「すごい雨になっちゃったね」
「そうだね」
そんな言葉を少しだけ交わす。話題がないわけではない。クリスマス、ポリクリ、そしてあの少女のこと…2人とも頭の中には浮かんでいたに違いない。しかし…お互い口にはできなかった。いつからか仲良くなって、どこからか気まずくなって…いつの時代も男と女はこんなことのくり返しである。
無言のまま大通りに出る…と、そこで2人の前を一瞬で通過するバイク。
「あれ、今の…長さんじゃないかな」
と、同村。
「私もそう思った」
「あんなに急いで…どうしたんだろう」
失踪するバイクはあっという間に新宿のネオンに消えていった。美唄がフフッと笑って言う。
「長さん、実習終わって帰ってるんじゃない?イブだし、デートとかかも」
「…そうだね」
「そういえば佐野さん、私たちのこと、からかって大変だったね」
そこでまた美唄は笑う。その笑顔の意味が同村にはわからない。
「…でも私、佐野さんはすごい人だと思ったよ。救急車の中で女の子に頑張れ頑張れって声かけてさ、なんか応援してるみたいだった」
同村もそこであの光景を思い出す。
「そうだね。救急隊は命の応援団なのかもしれない」
「さすが文芸部、じゃあ佐野さんは団長さんだ」
美唄が嬉しそうにそう言った。そんなやりとりに同村は一瞬懐かしさを覚える。そして意を決したように真剣な顔になって言葉を続けた。
「ねえ、遠藤さん…こんなことを言う資格はないのかもしれないけど」
おいおい、何を言う気だ?
「もしよかったら…食事でも行かないかな?」
おおっそう来たか!この男、突然大胆になる。
「いや、あの、別にデートとか変な意味じゃなくて…今日の実習のこととか色々話したいし。べ、別に嫌ならいいんだけどね。ハ、ハハハ…」
笑顔が硬いぞ同村!しかも勇気と弱気が混ざって挙動不審だ。
美唄は前を見ながら少し考えていたが、ふいに向き直って答えた。
「いいよっ!」
そこには笑顔全開100パーセント。…ほんと、女心ってミステリー。
「私もイブに一人で晩御飯って淋しいしね。ただし、お店は私が決めるからねっ」
「あ、ああ…」
彼女の明るさにまたまた戸惑う同村。おいおい、君が誘ったんでしょ?
「じゃあ、傘を貸したお礼にちょっとおごってね」
「え?ああ…も、もちろん」
「冗談よ、クスクスクス…」
何がそんなに…というくらい楽しそうな美唄。男はわけがわからないまま、彼女の望む店へと連れて行かれるのであった。
…まあ、何はともあれいい展開なんじゃない?ね、同村くん!
*
「長谷川さん!」
息を切らして長は弁当屋に飛び込んだ。
「あら長さん、どうしたの?そんなにズブ濡れで…まだお弁当はたくさんあるわよ、ホホホ」
いつもの明るい悦子だ。
「ハアッ、ハアッ、いやそうじゃなくて…あの…」
そのただ事ではない雰囲気に彼女も怪訝な顔になる。
「何、どうしたのよ?」
「あの、み、みやびちゃんは…」
「え?」
当然不思議そうに答える彼女。
「うちの娘が何か?」
「今、どこに?」
「え?…家にいると思うけど。4時に幼稚園に迎えに行ってそれから出かけてないはずだから」
「で、電話してみてください。お願いします!」
「え、でも…」
「お願いします!」
長の勢いに押され、悦子は携帯電話を取り出し耳に当てた。
「おかしいわね…出ないわ。夜、外に出るはずはないのに…」
彼女の顔は少しずつ不安の色に染まっていく。番号を確かめてまたコールするが結果は同じだった。
「出ない…で、出ないわ!」
そこで呼吸を整えた長が言った。
「いいですか、落ち着いて聞いてください。もしかしたらみやびちゃんは…」
*
同時刻、井沢とまりかは少女の手術に立ち会っていた。執刀は先ほどの藤原医師。
「よし、そこ、もう少し持ち上げて…そうだ、そのまま動かすなよ」
処置室の時より落ち着いた口調で彼はメスを走らせる。ここはBGMなどない緊急オペ室。室内にはモニター音だけが響き、緊迫の時間が流れている。壁際の2人も視線を逸らすことなく術野を見つめていた。
*
「そんな!」
悦子は顔を真っ青にして、写真立ての娘を振り返る。
「確かに、あの子のセーターにはイニシャルが…。私が縫ったの!」
「なら、おそらく…。長谷川さん、一緒に病院に行きましょう!」
悦子は一瞬よろめくが、気を取り直して奥のスタッフルームに呼びかけた。彼女と交代で帰ろうとしていた男性店員がドアから顔を出し、そのただならぬ様子に気付く。
「どうしました、長谷川さん?」
「娘が交通事故に遭ったかもしれないんです。今、すずらん医大病院に…すいませんが…」
そこまで聞いて彼は駆け寄ってくる。
「何?そりゃ大変だ!ほら、早く、店のことはいいから早く行きなさい!」
悦子は激しく頭を下げて礼を言う。男性店員は「今、タクシーを…」と店の電話を取ったが、すぐにボタンにかけた指が止まる。
「今夜はクリスマス・イブで新宿方面は大渋滞だ」
「長谷川さん!」
その時後ろから長が叫んだ。
「ちょっと怖いかもしれませんが、それでもよければ俺が送ります」
*
「…それで、やっぱりキーヤンカレーなわけね」
席についたところで同村が言う。すっかり見慣れたハワイアン風の店内は少しだけクリスマステイストの飾りつけがされ、流れる音楽もハワイアンアレンジのクリスマスソングとなっていた。相変わらず店長のこだわりを感じさせる。
「やっぱり、14班といえばここでしょ」
得意げに笑う美唄。
「君は本当にここのカレーが好きなんだね。まあ確かにおいしいけど」
「だって、今日で今年のポリクリ最後でしょ?食べおさめだよ。よ〜し、今日は『全部カレー』にしよう」
『全部カレー』とは、ビーフもポークもチキンもエビもキノコも…とにかく全ての具が盛り込まれたボリューム満点の一品。今朝佐野に行った言葉通り、彼女には栄養失調の心配はないようだ。
「さすが遠藤さん。よし…じゃあ俺もそうしよう」
「OK!同村くん、残しちゃダメだからね」
…無気力男と元気娘、結局相性は悪くないようです。たとえそれが友情と呼ばれるものだったとしても。
*
男性店員の予想は的確であった。もしタクシーを利用すれば新宿通りで足止めを食らっていただろう。その点、長のバイクならその車間を擦り抜けてまさに最短の時間で移動できる。まあその分冷たい雨と風にさらされてしまうことにはなったが。
午後7時半。オペ室前の廊下、置かれた長椅子に2人は腰を下ろしている。刑事に了解を得て先ほどのセーターを悦子が確認、事故に遭ったのは彼女の娘・みやびであることが確定した。
看護師の貸してくれたタオルで体を拭きながら、長は隣の悦子を見る。彼女はタオルを膝の上に置いたまま…弁当屋を出る時に思わず掴んできた写真立てに視線を落としていた。そこに笑っている少女は、今ドアを一枚隔てた向こうで生死の境をさまよっている。
「長谷川さん、タオル使ってくださいね…風邪引きますよ」
悦子は力ない瞳で長を見る。そして小さく「ええ…」と呟いた。少女の身元は確認されたものの、彼女がどうしてあの時刻にあの場所を歩いていたのかは依然不明のまま。現場は家から歩いて行けない距離ではないが…雨の中、彼女はどこに向かっていたのか。
長はその謎を考えるが…もちろんわかるはずもない。診療時間を過ぎた院内は薄暗く、静寂が広がっていた。
*
一方こちらでは高カロリーのカレーを完食した2人が大きなお腹で食後のコーヒーを楽しんでいた。食事中、美唄は楽しそうに4月からの14班の思い出を振り返った。それに相槌を打ちながら同村は思う…美唄は本当に細かいところをたくさん見ている、と。
そういえばそんな会話をした、そういえばそんな気持ちになった…彼女の言葉がまるで魔法の呪文のように、懐かしい場面をいくつも蘇らせる。彼女にかかれば小さな出来事も特別なことのように思えてくる。同村は気付いていた…美唄が笑う度に自分の笑顔が引き出されていることを。
そしてふと思う。もしかしたら彼女は今の一秒一秒を心に焼き付けようとしているのかもしれない、と。もし将来視力を失っても…見る事のできる卒業アルバムをそこに造るために。
カップに口をつけながら、今彼女は黙って窓に伝う雨を見ている。そして、そっと囁くように言った。
「でも…本当に、私たちって幸せだよね」
独り言かと想い同村は何も言わない。するとまた「本当に…幸せだよね」と穏やかにくり返された。
「こうして元気で、おいしいものを食べていられるんだもん」
「そう、だね…」
男はゆっくり答える。
「そりゃ悩みは色々あるけどさ…私達の悩みや不安なんて、全部幸せの範疇なんだよね」
そこで同村は今日の実習で出会った患者たちを思い出す。
「俺…今日すごく思ったんだ、色々な所に色々な人がいるんだなって。遠くに見えるビルの豆粒みたいな部屋にも誰かがいて、その人に歯その人の人生があって…みんな生きてるんだって」
「そうだよね。お医者さんから見たら病気はよくあることかもしれないけど、その人にとっては一大事だよね。その人生の主役はその人なんだもん、お医者さんは脇役」
美唄はコーヒーに口をつけて続ける。
「クリスマスだってそうだよね、みんなのものだもん」
「どういうこと?」
同村は尋ねる。彼に向けられた大きな二つの瞳は店のライトを映していた。
「ほら、クリスマスの主役は恋人たちみたいに言うじゃない?でもそうじゃないってこと。同村君が今言ったみたいに、街には見えない所にもたくさんたくさん人がいる。だからね、デート中の恋人たちだけじゃなくて、例えばその2人を乗せるタクシーの運転手さんにもメリークリスマス、食事するレストランの店員さんにもメリークリスマス、お皿を洗う厨房さんにもメリークリスマス」
そこで同村も「今夜当直のお医者さんにもメリークリスマス?」と合いの手。美唄は嬉しそうに頷いて続ける。
「そうそう!病院の警備員さんにも、入院してる患者さんにも、清掃のおばさんにも、それからえ〜と…とにかくみんなにみんなにメリークリスマスってことだよ」
「遠藤さん…」
同村は完全に彼女の言葉に引き込まれていた。
「やっぱりすごいや、遠藤さんって。そんなふうに考えられるなんて…」
彼はそう言って珍しくためらいない笑顔を見せる。素直に…感動していたのだ。
「そっか、みんなにメリークリスマスか…そうだ、そうだ」
同村はコーヒーを飲むことも忘れ、何かに納得したようにくり返している。そんな彼を見ながら美唄も微笑んでいる。
「もう同村くん、大げさ過ぎるよ。クスクスクス…」
…みんなにメリークリスマス、それはもちろん君たちにもだからね。
*
午後8時半、オペ室のドアが開いた。最初に姿を見せたのは藤原。彼は全てを出しきったようなやつれた顔で現れた。…お疲れ様です。
「先生…」
悦子が彼の前に立った。その瞳にはすがるような不安が浮かんでいる。その後ろで長が「お母さんです」と説明した。執刀医は状況を理解する。
「ああそうですか。お母さん、大丈夫ですよ…手術は無事に終わりました。幸い脳や心臓、肺は無事でしたし、傷ついた内臓も修復できました。ご安心ください」
藤原は少し笑顔を見せる。
「一時間もすれば麻酔も解けて…話もできると思いますよ」
「はあ…」
それを聞いて悦子はその場にペタンと座り込む。張り詰めていた糸が緩んだのだろう。
「ありがとうございます、ありがとうございます…」
彼女は涙を流してくり返した。そして長が手を貸し立ち上がったところで、ストレッチャーが運び出されてくる。そこには、酸素マスクをつけた最愛の娘。くり返しその名を呼びながら悦子がすがりついた。
「今からICUという病室に移りますので、お母さんも一緒に行きましょう」
「はい、ありがとうございます。みやび、みやび、わかる?お母さんだよ」
涙声のまま娘とともに彼女は廊下を去っていく…精一杯寄り添いながら。長も安堵を浮かべ、その背中を見送った。
「あれ長さん、どうしたんですか?」
後ろから声がかけられる。振り返ると、そこにはオペ室から最後に出てきた井沢とまりか。2人はとっくに帰ったはずの男がそこにいることが不思議そうだ。
「ああ…ちょっと色々あってね」
彼はそう言って微笑んだ。本当に色々お疲れ様でした、長さん。
*
その後、藤原の予測通り少女は目を醒ました。涙の母に付き添われ、自分がベッドにいることが最初は理解できない様子であったが…幸い記憶の欠損もなく、自分が事故に遭った経過を含め全てを思い出せた。
「ごめんね…ママ」
やがて彼女はそう言った。
「私ね、公園に行ったの。前に幼稚園の遠足で行った公園ね。あの時、綺麗な石がたくさん落ちてたのを思い出して…拾いに行ったの」
悦子は娘の小さな手を握りながら「どうしてそんな…」と尋ねる。
「…ママへのプレゼントにしようかと思ったの。ママはもう大人だからサンタさんプレゼントくれないでしょ?いつも頑張って働いてるのに…ご褒美ないのおかしいでしょ。だから私が…」
「みやび…」
悦子には別の涙が込み上げてくる。そこでそっと看護師が少女のスカートのポケットに入っていたあの小石を手渡した。受け取った彼女の涙がその宝石に落ちる。
「ママ…夜は外に出ちゃダメって言われてたのに…ごめんなさい」
「ううん、もういいの。ママこそごめんね」
母親はそこで娘を抱きしめる。藤原たちスタッフもそれを見て静かに退室、最後尾にいた長たち3人もそっと部屋を出てドアを閉めた。
3
キーヤンカレーからいつもの地下鉄駅までの道、同村と美唄はまた相合傘で歩いていた。少し雨脚も弱まったようだ。遠くには新宿中心街のネオンが輝き、かすかにクリスマスソングも聞こえてくる。
「同村くん、今日はありがとね」
「こっちこそ、本当に楽しかったよ。やっぱり遠藤さんと話してると幸せな気持ちになれる」
「そんな…」
美唄は白い息を吐きながら、少し頬を赤らめる。と、そこで彼女の携帯電話が鳴った。
「あ、ごめん。ちょっと傘持ってて」
そう言いながら傘を預け、携帯電話を取り出す。
「メールだ…まりかちゃんから。あ、『さっきの女の子、無事助かりました。お母さんも見つかりました』だって…」
「そりゃよかった!」
同村がそう喜んで美唄を見ると、彼女は瞳から大粒の涙をこぼしていた。
「遠藤さ…」
「よかった…よかった…」
美唄はそうくり返しながら携帯電話を胸に抱きしめている。
「遠藤さん…」
そこで同村の気持ちが爆発する。彼は美唄の正面に立ち、急き立てるように言った。
「遠藤さん、大丈夫だよ。これからも大丈夫だよ。確かに目は悪いけど、涙が出るんなら…君は大丈夫だよ」
その声は力強く、そして優しい。それは無口な男の精一杯の叫びだった。
「…ありがとう、同村くん」
美唄は涙をそのままに、とびっきりの笑顔を見せる。
「どうしていつも、そんな嬉しいことを言ってくれるの…?ほんとに、ほんとに、嬉しいよ」
同村はそこで彼女の手を握る。
「先のことはわかんないよ。いつまで目が見えてるのか、もしかしたらずっと大丈夫かもしれない。いつか見えなくなるのかもしれない」
彼女は黙ってその言葉を聞く。
「そんなわからないことに押し潰されちゃうよりも、わかっていることを大事にしようよ。君は歌うのが好き、みんなといるのが好き、医学が好きで誰かの役に立ちたい…それは間違いないだろ?」
傘に落ちる雨がまた少し穏やかになる。
「俺も…今はっきりわかってることがある」
同村は握る手に力を込めた。
「俺は君が…美唄さんが…好きだ!それは絶対間違いない」
よく言った、告白アゲイン!まあやってることは中学生のようですが…。
「同村くん…」
美唄は瞳を見つめ返しながら言った。
「本当に…私でいいの?私、たくさん迷惑かけちゃうよ?大事な物を踏んづけちゃうし、自動ドアにぶつかっちゃうし」
彼女の声は震えている。同村は彼女のおでこにそっと触れて言った。
「…大歓迎」
次の瞬間、美唄は背伸びをし、同村に唇を重ねた。傘が地面に落ちる。
かくして2人のファーストキッスは…キーヤンカレーの味でしたとさ。
*
夜の学生ロビー、休憩を言い渡された井沢とまりか、そして長の3人は遅すぎる夕食を囲んでいた。といっても自動販売機のパンとコーヒーだが。
「それにしても、長さん大活躍だったんですね」
班長が缶コーヒーを片手に言う。時刻は午後10時前、もちろん周囲に他の学生の姿はない。
「いや、たまたまだよ。たまたま知り合いの娘さんだったからね」
と、副班長は頭を掻く。井沢も「クリスマスにいいことしたじゃないっすか」と微笑んだ。
「そういえば井沢くんは本当によかったの?今日、当直で…」
心配そうに訊くまりか。
「え?ああ、大丈夫。彼女とは昨日クリスマスやったから。それよりみやびちゃんさ、早く元気になればいいよな。クリスマスも病院じゃつまんないだろうし」
「そうね…。あの子、とってもいい子だもんね。あの小石の話聞いて私もホロッときそうだった」
そんなやりとりを聞きながら、長が缶コーヒーをそっと置く。
「なあ、ひとつ思いついたことがあるんだけど…」
浪人生のボスは少し真面目な顔になる。そして彼らしからぬ…いやむしろ彼だからこそと言うべきなのかもしれないアイデアを語った。2人も聞きながら最初は驚きを見せていたが、次第にその口元が綻んでくる。
「長さん、それ素敵です!」
聞き終えたまりかがまずそう反応した。井沢も勇んで同意したが、そこで不安要素も指摘する。
「でも、今から準備できますかね?俺たちはまた実習に戻らなくちゃいけないですし」
「そうだよな…。よし、じゃあダメモトで電話してみるか」
長は取り出した携帯電話をコールする。
「あ、繋がった。もしもし同村?俺だよ、長。夜分にごめんな。ちょっと相談があるんだけどさ…え?美唄ちゃんも一緒?ならなおさら都合がいいよ」
それを聞きながら井沢が隣のまりかに小声で言う。
「あの2人、なんで一緒なんだ?もうとっくに実習は終わってるだろうに…。秋月さん、あいつら一体どうなってんの?」
「さあどうなってんのかな?フフフ…」
*
長からの電話を切り、同村は美唄にその内容を説明する。健全な2人は、ちょうどいつもの地下鉄駅に着いたところだったのだ。予想通り美唄は「わあ素敵!」と大はしゃぎ。
「でも、今から手に入れるのは…」
と、不安そうな顔をする主人公。オイオイ、さっきのかっこいい君はどこへ行ったんだ?
「同村くん、言ってたじゃない。万が一を成功させるためには…?」
「百の無駄骨でも足りない、か」
頷く同村。美唄も「そうだよ」と微笑む。そう、今日もそれを学んだんじゃないか、君たちは。
「よし行こう、遠藤さん!」
そう言って再び地上への階段を引き返す。彼女も嬉しそうについて行きながら言う。
「了解!って、同村くんさぁ、告白の時だけ下の名前で呼ぶわけ?あれって作戦?一回目の時もそうだったよね」
「い、いいから、さあ行こう!」
悪戯っぽく笑う美唄に同村はトナカイさんのように鼻を真っ赤にする。まあまあ、微笑ましいじゃないですか…正直書いてる作者が恥ずかしくてもう限界です。
*
ICUの病室、薄暗い室内で長谷川親子はずっとおしゃべりをしていた。みやびが生まれた朝のこと、入園式の日のこと、一緒にいったイモ堀り遠足のこと、そしてもういないお父さんのこと…。藤原の許可で酸素マスクも外され、少女はずっと母親の手を握りながら話を続けた。
「ねえ傷口が痛まない?」
心配そうに尋ねる悦子に娘は笑顔で首を振る。
「大丈夫だよ、ママ。それにまだ全然眠たくないの。だからもっとお話しよう」
母親が夜勤の時はいつも一人で眠るのが当たり前の娘。それでも淋しいとは言わない娘。悦子はまた泣きそうになるのをそっと隠し、壁の時計を見た。
「あらもうすぐ0時だわ。じゃあ今夜は特別にもうちょっと話そうか」
嬉しそうに頷くみやび。
「こんなに遅くまで起きてたの初めてだね。0時になったら次の日になるんだよね?じゃあもうすぐクリスマスだ」
そこで少女は目で室内を見回した。
「ねえママ…病院にいても、サンタさん来てくれるかなあ?」
悦子は言葉に詰まる。
「きっと…無理だよね。このお部屋には窓も煙突もないしね」
「そうね…」
その時だった。小さな音が聞こえた。シャンシャン、シャンシャンと音は遠くから少しずつ近付いてくる。悦子は耳を疑い周囲を見回す。
まさかそんなはずは…しかし確かに近付いてきている、鈴の音が。
「あ、サンタさんだ!サンタさんだよ、ママ」
「え、ええ…」
鈴の音はどんどん大きくなる。そして鈴だけではない、トナカイの闊歩する音、その息遣いまで聞こえるのだ。やがてそれらは入り口のドアの向こうで止まった。悦子にはとても信じられない…しかしドアの向こうには、まるでトナカイの群れがそこにいるような気配がある。
そしてドアは静かに開かれた。そこには…赤い服に白髭の男。
「サンタさん!」
みやびが嬉しそうに言った。
「メリークリスマス、みやびちゃん。遅くなってごめんね。ここには煙突がないから迷っちゃったよ」
サンタはそう言いながらゆっくりベッドに歩み寄る。その隣で悦子は自分が夢でも見ているのかとただ呆然としていた。
「はいみやびちゃん、プレゼント」
サンタは白い袋からそれを取り出し、彼女の枕元に置く。少女は「ありがとうサンタさん」と横になったままそっとその包みに触れた。
「早く元気になるんだよ…みやびちゃん」
悦子はそこではっとする。この声、もしかして…。
「あのねサンタさん。お医者さんたちがね、私の命を助けてくれたの。だから絶対元気になるんだ」
「そうかい。でもね、君を助けてくれたのはお母さんなんだよ」
そう言ってサンタはそっと彼女の頭を撫でる。
「お母さんがね、セーターに君の名前を刺繍してくれていたから…だから君のことがわかったんだよ」
サンタはそこでニッコリ微笑み、そっとドアの方に向かった。自分の前を通り過ぎた時、悦子にはその正体がはっきりとわかる。
「あの…」
「それでは失礼しました」
サンタは振り返らずにそれだけ言う。彼女は頭を下げた。
「本当に…本当に…ありがとうございました。一度もちゃんとお礼を言っていなくて、あの、本当に…」
「ママ、サンタさん困っちゃうじゃない。サンタさんは忙しいんだよ?また次のお家に行くんだから」
サンタは「そうです」と囁き、少しだけ振り返って「それじゃお幸せに」と付け加える。そして手を振る娘と頭を下げる母親を残し、そのまま部屋を出ていった。
ドアが閉まると再び鈴の音、トナカイの足音も聞こえ始める。それらはゆっくりと移動を始め、だんだんと遠ざかっていく。
音が空の彼方に消えてから、みやびは「ママ、プレゼント開けて!」とワクワクしながらねだった。悦子が枕元のそれを丁寧に開くと…ゲームソフト『フニー仮面の冒険』。
「これとっても欲しかったやつだ。やったあ、サンタさんすごい!早く退院してやらなきゃ」
プレゼントを抱きしめる娘を見ながら、彼女は全てを理解する。
「でもどうして私が欲しい物がわかったんだろ?ねえママ、サンタさんに連絡したの?」
悦子はベッド脇の椅子に腰を下ろして首を振った。
「ううん、してないわ。でもママのお友達で今のサンタさんと同じにおいの人がいるから…その人がサンタさんの知り合いかも」
「におい?そういえばサンタさん、煙のにおいがしたね。きっと煙突を通る時についちゃうんだよ。そっか、ママのお友達…」
「フフフ…」
悦子はそっと娘の頭を撫でる。
そう、あのにおい…早朝に弁当屋にやってくる彼がいつも漂わせている香り。それで彼女はサンタの正体を確信した。
間違えるはずはない。だってそれは…愛した夫が吸っていたのと同じタバコのにおいだったから。
*
「いや〜長サンタ、最高っす!」
と、井沢が拍手。学生ロビーで衣装を脱ぎながら長は照れ笑い。
「しかしこの歳でもうおじいさんの役をやることになるとは…」
「自分で言い出したんじゃないですか」
井沢の隣でまりかも笑う。こんなサプライズに藤原の許可が出たのはひとえにこの2人によるところが大きい。信頼ある特待生と顔の広い爽やか青年の口添えの賜物である。
「そうだけどさ…でもまさかこんな大ごとになるなんて。プレゼントを寝ている間にそっと枕元に置くだけだったはずなのに」
「そりゃあ協力要請した相手が悪かったですぜ」
そう言って井沢が2人を見る。それは頼まれたゲームソフトだけではなくサンタ服まで確信犯で用意してきた同村と美唄。もちろん主犯は彼女である。長はそちらを見て言う。
「2人とも本当にありがとうな。人気のソフトをよく見つけてくれたよ」
「いえいえ、まさに眠らない街・新宿のおかげですね」
と、同村も笑い、「最後は遠藤さんのゴリ押しで展示用のを売ってもらいました」と続けた。隣で美唄も得意気にVサイン。もちろん彼女のカメラにはサンタの姿もたくさん納められている。
「でも、長サンタ、本当に素敵でしたよ!まあ、トナカイのソリに乗ったサンタの正体は、バイクに乗るチョイ悪オヤジですけどね!」
「おいおい美唄ちゃん、まいったな」
そこで長は離れて作業している男の方を向く。
「向島さんも、わざわざありがとうございました!」
「ん?いいよ、別に…。あれくらい、たいしたことない」
と、ミュージシャンは使用したスピーカーを片付けながら答えた。タネを明かせば人数分の鈴を持ってきたのもこの男。彼のレクチャーのもと長以外の5人で近付いてくる鈴の音を演出、そしてスピーカーからはトナカイの息遣いや足音を臨場感たっぷりに流す…ドアの向こうの舞台裏はそんな感じだったわけである。
「でも本当にサンタが来たみたいにリアルでしたよ、MJさん!」
と、美唄。先輩は得意げに「誰だと思ってるんだよ」と返す。う〜ん、グッジョブ、MJK!
「まあみなさん、今日の企画は大成功ってことで」
と、班長がまた拍手する。それにみんなも合わせた。
めまぐるしく駆け抜けた一日…いろんな患者のいろんな人生に出会った。神様はそう都合よく奇跡を与えてくれるわけではない。神様がくれるのはほんの小さな偶然だけ。それを繋ぎ合わせて奇跡に変えられるかはきっと一人一人にかかっている。
3月のあの日、この6人が集まったのもまさしく偶然。もしかしたらこの偶然も奇跡に変わってきているのかもしれないね。
*
その夜、時間は穏やかに流れた。雨もいつしか優しい霧雨に変わっている。
向島は田倉明日香の病室を訪ね、眠れずにいた彼女にクリスマスソングを演奏した。
井沢は当直実習の合間に恋人に電話した。
まりかも実習の合間にある病室を訪ねた。そこにいる人物については、次回お話しするとしよう。
同村と美唄は最終の地下鉄に飛び乗り、その車中で彼女からまたまた驚きの計画が語られた。
そして長はバイクを飛ばして帰宅、起きて待っててくれていた両親に肩叩きをしながら普段言えない感謝の言葉を伝えたのだった。
4
12月25日。静かに雨も上がり、眩しい朝日に街が照らされ始める。午前8時、救命救急センターで井沢とまりかは実習修了の印鑑をもらった。
「お疲れだったな、2人ともいい頑張りだったぞ」
藤原にそう言われ、2人は頭を下げる。
「それにしても災難だったな、イブに当直とは」
そう笑う藤原。しかし学生の表情には大きな満足が浮かんでいる。
「いえ先生、今までの人生で最高のクリスマス・イブでした」
井沢がそう言い、まりかも力強く頷いた。
*
「メリークリスマ〜ス!」
2人が学生ロビーに戻ると、クラッカーが鳴った。そこには三角帽子をつけた美唄たち。
「え?みんな…」
戸惑う井沢。まりかも目を丸くしている。
「これで今年のポリクリ終わりだろ?やっぱみんなで締めくくろうって遠藤さんが言ってさ」
と、ちょっと帽子が恥ずかしそうな同村。見るといつものソファに人数分のケーキとグラスが用意されている。バイクでひとっ走り買ってきたと長が説明した。
「い、今からここでパーティですか?」
「そうです班長!あなたが実習しておられる間に、副班長の私が準備しておきました。さあ、グラスをどうぞ」
「え?長さん、ここでお酒は…」
「大丈夫、ブドウジュースです」
そう言って長はまりかのグラスにジュースを注ぐ。みんなもそれに従った。
「みなさ〜ん、飲み物はいきましたか〜?」
朝から大はしゃぎなのは美唄だ。全員グラスを掲げたところで長がまりかに挨拶を促した。もう何がなんだかという感じで彼女は一歩前に出る。
「ええみなさん…本当に驚きの連続ですが」
そこで全員が笑う。
「まあこれで救命救急の実習も終わりです。そして今年のポリクリもこれでおしまいです。本当にお疲れ様でした。じゃあ…カンパイ」
「カンパ〜イ!」
恥ずかしそうに言ったまりかに続いてみんな一斉に叫ぶ。それに合せて向島が再びセッティングしたスピーカーで音楽を流した。
「ちょっと向島さん、ボリュームでかすぎですって!学務課に見つかっちゃいますよ」
と、慌てる井沢。その後は美唄を筆頭に全員でケーキを味わう。そして改めて今年の思い出を語り合った。
「でも遠藤さん、ついに念願の班飲み会が実現したね。まあノンアルコールだけど」
と、同村。
「そうだね、今年中にやれてよかった!」
もちろん笑顔は100パーセント。もはやアルコールなど問題ではない。昨夜に思いついてすぐ決行…ちょっと強引だけど、これが彼女の幸せの作り方。
談笑が続く中、ふと長が思い出したようにフォークを止めた。
「あ、じゃあ美唄ちゃん、いつかのクイズの答えは?」
まりかもそれに食いつく。
「そうそう、私も気になってたの。14班のみんなが集まるとどうなるかっていう…」
そう、それはいつかみんなで食堂で昼食を囲んでいた時のこと。何故か流れはクイズの出し合いになり、美唄からの問題がそれであった。結局その場で正解者は出ず、彼女はそれを飲み会までの宿題としたのだ。
「あ、そうだそうだ!ではみなさん、正解発表しま〜す!」
美唄はそう言ってソファから立ち上がった。みんなは拍手を贈る…彼女は楽しい空間を生み出す天才だ。
「14班のみんなが集まるとどうなるのか…。じ・つ・は…私たちの名前って、苗字のアルファベットを合わせるとすごいことになるの」
美唄はもったいつけて言う。
「え?なになに、どういうこと?」
向島もノリノリだ。
「いいですか?MJさんのM、私の遠藤のE、同村くんのD、井沢くんのI、長さんのC、そしてまりかちゃんの秋月のA…」
一人一人の顔を順に見ながら彼女は続ける。
「そして最後にLを付けると、なんと『MEDICAL』なのです!ね、すごくない?」
「本当だ!」
まず同村が反応した。みんなも驚きを口にする。
「ほんと、嘘みたい!」
まりかが嬉しそうに言う。そこで向島が「でも、最後のLはどこから来たの?」と質問。まあ確かにそこは疑問だ。
「やだな〜もう1人、大事なメンバーがいるじゃないですか」
そこで美唄はコートのポケットから小さなぬいぐるみを取り出す。それはラッパを持った天使…。
「ラブちゃん!」
同村が感激して叫んだ。みんなも歓声を上げる。
「そう、14班の守り神、ラブちゃんのLで〜す!だからクイズの正解はみんなが集まるとメディカルになる、でした!」
美唄はハイテンション、その爆走は止まらない。
「ついでに発表、私、同村くんとデキてま〜す!」
再びみんなから歓声。
「ちょ、ちょっと遠藤さん、それは…」
「やったな、同村!」
混乱する同村に井沢が肩を組む。向島も嬉しそうな美唄の顔を見て、そっと微笑んだ。
その後祝福と冷やかしの質問攻めにあう2人、その後で美唄は自分の病気についても打ち明けた。知らなかった3人は最初は驚いたものの、彼女が「これからもよろしくね」と言ったのに対し心からの笑顔で答えた。
「何か困ったことがあったらいつでも言ってね」
と、まりか。長も頷く。
「美唄ちゃん、歩き難い所があったらいつでも俺が手を繋ぐよ。あ、同村に殴られるな」
井沢がボケてまた同村が「うるさい!」と赤くなる。そしてその場に笑いが起る。そう、彼らはみんな病気と向き合っていく医学生なのだ。
こうして、14班年内最後の実習はようやく実現した初飲み会をもって終了する。まあきっと帰ったらみんなバタンキューでしょう。本当にお疲れ様でした。
ポリクリも残すところあと2ヶ月。ゲームセンターでラブちゃんを取ったあの日から始まった長い旅も、少しずつ終わりが近付いています。メディカル諸君、新しい年もやってくるけど今はぜひこうして一緒にいられる時間を大事に抱きしめてほしい。神様がくれた素敵な偶然を大切にしてほしい。
誰だって、いつ何が起こるかわからないのだから。
1月、神経内科編に続く!