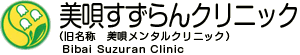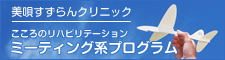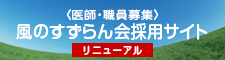- ホーム(法人トップ) >
- 美唄すずらんクリニック >
- コラム >
- 2016年7月
コラム
2016年7月★スペシャルコラム「刑事カイカン 夕焼けの丘 (上)」
*このコラムはフィクションです。
■プロローグ 〜前島浩之〜
「その曲、教えてください!」
昼前。用もなくぶらついていたショッピングモールの出口で突然声をかけられた。振り返ると一人の女がそこに立って肩で息をしている。
「はい?」
そう返した俺に女は息も絶え絶えに言葉を続けた。
「あ、あの、すいません。ハア、ハア、その曲の…」
苦しそうに胸に手を当て背中を丸めながらも、その二つの瞳はまっすぐにこちらを見ている。一体何なんだこいつ?
「どういうこと?」
「あの…、ハア、ハア」
「とにかく、まず呼吸を落ち着けなよ」
「ごめんなさい」
女の歳の頃は二十歳前後。肩までの長い黒髪に水色のサマーセーター、膝下までの紺のスカートにダサい靴下とスニーカーを履いている。そして小柄の痩せ体型。
「ハア、ハア…」
しばらく息が整いそうにないので俺はバツ悪く周囲を見回した。平日のショッピングモールはそれほど混雑はしていない。出入りする客もまばらで、ビラ配りのピエロも暇そうに店先でバーゲンを伝えていた。しかし…そんな雰囲気を差し引いても、この女の存在は浮いている。容姿だけではない、まとわりつく空気がどこか世間離れしている。
…まさか家出してきた大富豪のお嬢様とかじゃあるまいな。まあそれにしちゃ服が地味か。
「驚かせてすいません」
ようやく安定した彼女が言った。肌が恐ろしく白い…しかしそれは美しさよりも儚さを感じる白さだ。
「あの、今、あなたが口ずさんでた曲のタイトルを教えて頂けませんか。できたら歌っている歌手の名前も」
…何言ってんだこいつ?新手のキャッチセールスか?いぶかしいことこの上ない。
俺の表情を読み取り、女は「怪しい者じゃありません、ただ…」と慌てて事情を説明する。それによれば先ほど俺が下りエスカレーターに乗っていた時、上りエスカレーターに乗っていた彼女はすれ違いざまに俺が口ずさんでいた歌が耳に入ったのだという。
「お願いします。その曲、どうしても知りたいんです」
激しく頭を下げられる。曲のことを知るためだけに急いで下りエスカレーターに乗り換え俺を追いかけて来たっていうのか、この女。
「歌ってたかな、俺」
「はい、確かに『夕焼けに向かうトンボを見つめて〜』って。それ、ずっと私が探してた曲なんです」
恥ずかしげもなくその一節を歌い、すがるような目で俺を見る。事情はさっぱりわからないが必死なのは伝わってきた。
ああ、その曲か。まあ確かに口ずさんでいたかもしれない…つい無意識に歌うのは俺の癖だからな。
「突然失礼なことを言ってすいません。でも私…どうしても知りたくて」
どうやら詐欺の類ではないらしい。どうせ退屈してたところだし、ちょっとくらい相手してやるか。
「わかったよ。でもまずお互い自己紹介からしようぜ。俺は前島浩之、23歳のフリーターね」
「あ、はい。私は凪野しらべ…21歳です」
彼女は身分を明かさなかった。まあ対して興味もないが。
「しらべちゃんね、了解。それでさっきの曲だけど、タイトルは『夕焼けの丘』ってんだ。歌ってんのはベイシティボーイズってバンド。でもよく知ってたね、こんなマニアックな曲」
「夕焼けの丘…ベイシティボーイズ…」
彼女は嬉しそうにそうくり返す。お、笑うとちょっと可愛いかも。
「ありがとうございます。さっそく店で探してみます」
お礼を言ってショッピングモールの中に戻ろうとする彼女…そのまま見送ってもよかったのだが、俺は呼び止めてしまった。
「ちょっと待ちなよ。cd屋に行っても売ってないって。もう十年以上前の曲だし、ベイシティボーイズはインディーズだしすぐに解散しちゃったから。中古ショップでもあるかどうか」
途端に彼女の表情が曇る。
「そんな顔すんなって。なんなら今から俺の家に来る?この曲のcdあるよ」
「本当ですか、行きます!」
打って変わっての笑顔で即答。こいつ…感情と表情がそのまま連結しているのか?まあいいや、暇つぶしがてらそれくらいしてやるか。
どうせ俺は…役になんか立たない人間だしな。
■第一章① 〜ムーン〜
1
私の名前はムーン、警視庁捜査一課の女刑事である。もちろんこんなふざけた名前の日本人がいるはずもなく、ムーンというのは職場上のニックネームのようなものだ。これは一般の方はあまりご存じないのだが、警視庁捜査一課はミットと呼ばれるいくつかのチームに分かれており、私の所属するミットではお互いをニックネームで呼び合うのが古くからの慣例らしい。ちなみに私の上司はカイカンなる私以上に奇異なニックネームで呼ばれている。
正午。自分のランチのついでにその変人上司に頼まれたテイクアウトのハンバーガーを片手に警視庁に戻る。…と、正面玄関の辺りが何やら騒がしい。
「お願いです、力を貸してください」
中年女性がそう声を上げ、複数の署員が「お気持ちはわかりますが」「お母さん落ち着いて」などの言葉でそれをなだめている。漏れ聞こえる情報から推測すると、どうやら入院中の娘が行方不明でそれを警察に捜してほしいと母親が嘆願しているらしい。ただ娘が姿を消したのはほんの数時間前の話で、しかも自らの意思で外出したというのだ。
「娘は心臓の病気なんです。もし発作を起こしたら大変なんですよ!」
「ご心配はわかりますけどね、でもお嬢さんは病状もご存じなのでしょう?大人の女性がそれでも自分で外出されたわけですから…警察が捜索というわけにはいきませんよ。それも今朝のことですし、お帰りまでもう少し待ってみてはどうでしょう」
「それで娘に何かあったらどうするんですか!」
そんなやりとりが続く。署員の対応は正論だ。現時点で家出でも誘拐でもなく、しかも未成年でもなくただ自分で外出した成人に対して捜索願を受理するのは難しい。捜査員を動かすとなれば尚更だ。
でも…母親の訴えもわかる。私はつい立ち止まってその光景を見守った。
さらに十分ほどのやりとりの後、結局は母親があきらめる形でその場は散会となった。背中をすぼめてトボトボと玄関に向かう後ろ姿には落胆と悲哀が浮かんでいる。
…仕方のないことか。
そう思って私もエレベーターへと歩き出す。しかし、どうにもやりきれない。そういえば午後の仕事は書類整理だけだったな。
「あの、ちょっとお待ちください」
気持ちが高まるのが早いか、私の足は踵を返し、私の口は警視庁を出ていく彼女にそう呼びかけていた。
2
「それで相談に乗ってきたわけだね」
私からハンバーガーの袋を受け取りながらいつもの席で警部が言う。そう、この人がカイカン。室内でもボロボロのコートとハットを着用し、その右眼は長い前髪に隠されているというどこからどう見ても不審人物。
「はい。詳しく伺ったんですが、その行方不明の女性は凪野しらべさんという21歳。すずらん医科大学病院に心臓の病気で入院中です」
「行方不明って…自分で外出してるんじゃないのかい?」
「確かにそれはそうなんですが…」
私は母親から聞いた彼女の病状、そしてその深刻さを説明する。小学校低学年の頃から入退院をくり返し、この十年ほどはずっと病院暮らしで外泊はおろか外出もなし。院内の庭を散歩するのが唯一外気に触れる時間だった。長期入院により病気の進行を遅らせることはできているが、根治が望めるわけでもなく、大きな発作を起こす度に少しずつ衰弱している。そんな彼女が今朝、ベッドに『一日だけ自由にさせてください』と母親へのメモを残して姿を消した。
「また発作を起こせば命の危険もあるそうなんです」
そう力説した私に、「ああそう」と低い声が返される。普段から長い前髪のせいで表情が読み取りにくい警部だが、それを差し引いても反応が薄い。私は急かすように「いかがしましょうか」と尋ねた。
「いかがって…君はどうしたいんだい?」
「できれば捜索に向かいたいと思います」
「そう…」
ハンバーガーの袋を机に置く警部。そして数秒の沈黙を挟み、彼女が薬やお金を持参したのかを私に確認した。
「はい。凪野さんは一日分の内服薬と普段院内で使っている財布を持って出たようです」
警部はもう一度「ああそう」と呟くと少し座り直してから言った。
「ムーン、君の気持ちもわかるけど現時点では捜索の対象にはならないよ。確かに病気によるリスクもあるけど、ご本人はそれも承知で出かけてるんだから。それに一日自由にさせてってメモに書いてるんだ。遅くても明日には戻るんじゃないかな」
「それを待っていて手遅れになったら大変です!」
私は苛立ってしまう。どうも警部の対応が気に食わない。もっと興味を示してくれると思ったのに…。
「自分の意思で行動している人を、警察だからって勝手に保護するわけにはいかないよ」
「ですが、命の危険があるんですよ?市民の安全を守るのが警察官の務めじゃないですか」
警部は小さく溜め息を吐く。
「自殺しようとしてるっていうのなら話は別だけど、このケースはそうじゃない。確かにリスクはあるけど、そのリスクを冒すのもその人の権利だよ」
「そんな」
「この社会には危なっかしい生き方をしている人はたくさんいる。君はその人たち全員を保護するって言うのかい?」
そんなこと言ってない…と口に出そうになるのをぐっと堪える。違うよ警部、そんなんじゃない。確かに私たちは全員を守ることなんてできないよ。この世の中には今この瞬間だって危険にさらされている人がどこかにいる。私の言ってることは中途半端な正義かもしれない。でもせめて…知ったのなら、気付いたのなら、精一杯その人を守ろうとするべきじゃないの?
心の中で警部への失望がインクの染みのように広がっていく。変な格好も、ヘアースタイルも、時々口にくわえるおしゃぶり昆布も…そんな一見ふざけていても、警察官としての信念だけはしっかりした人だと思ってたのに。結局中身もいい加減だったってこと?ちょっと頭が切れるだけの変人だったってこと?
気が向いた事件にだけ取り組むのなら、それはただの趣味…正義なんかじゃない。
「警部…」
両方の拳を握り締めてから言う。
「もう一度確認します。私たちは警察官として凪野しらべさんを保護するべきとは思われませんか?」
私はまっすぐにその左眼を見つめる。警部は右手の人差し指を立てたが、すぐにそれを下ろしてから言った。
「…思わないよ」
「そうですか、わかりました」
身を翻して私はドアに向かう。「どこに行くんだい」と後ろから聞こえたが無視してそのまま部屋を出る。そして1階に下りると、待たせていた母親に今から私が捜索に出ることを伝えた。そして母親には病院に戻ってもらう。もしかしたら彼女が自分で帰ってくるかもしれないから。
頭を下げる母親を見送ると、私は駐車場に向かい愛車に乗り込んだ。
イライラする。警部の下についてもう何年にもなるが、今までずっと従ってきたつもりだ。突飛な行動に驚かされたり、時には捜査のルールを破ることもあったが、それでも全ては事件解決のため被害者のためと信じて協力してきた。
…「そりゃ大変だムーン、すぐ捜しに行くぞ!」。きっとそんな返事がもらえると思ってたのに。私がここまで警部と意見を違えたのも、警部に幻滅したのもおそらく初めてのことだ。
「もう、どうしてよ!」
そう叫んでアクセルを踏み込む。私の怒りに応えるように愛車は勢いよく嘶いた。
■第一章② 〜前島浩之〜
1
新宿区だって中心街から三十分も歩けば四ツ谷に入る。特に俺の住んでいる方面は閑散とした住宅街。平日の昼、ほとんどの奴が学校なり仕事なりに出ている時間だ。うろついているのは俺みたいな風来坊と、疑いもせずついてくるこの女くらいだ。
「そうなんですか。ベイシティボーイズって横浜出身なんですね」
「ああ。確か高校の同級生でバンドを結成したんだ。あ、別に敬語で話さなくてもいいぜ、しらべちゃん。たいして歳も変わんないし」
「あ、ごめんなさい…じゃなくてごめんか。フフフ」
最初こそ驚いたが、話してみると彼女は普通の女の子だった。まあ世間知らずなのは否めないが、笑ったり驚いたりとても感情が豊かなのは好感が持てる。東京じゃ嬉しいのか悲しいのかもわかんない顔した連中ばかりだからな。
「前島くんは東京出身なの?」
最初はぎこちなかったが敬語も少しずつ外れてくる。
「そうだよ。まあ実家は八王子の方だけどね」
「それが四ツ谷で一人暮らしか。どうして?」
いつもなら誤魔化す質問だった。しかし、不思議と腹も立たず俺は答える。
「予備校に通うためさ。実はさっきフリーターって言ったけど、別にバイトしてるわけでもないんだ、俺。本当は浪人生。結構難しい大学目指してて…。でももうやめたんだ、受験するの」
「どうして?」
「なんかテンション下がっちゃってね…全然受かんないし」
いつものタバコ屋の前に来る。店のじいさんは相変わらず眠そうだ。彼女はさらにどうしてと尋ねようとしたが、俺は「ここで曲がるんだ」とそれを遮った。
「この裏路地に入れば後は道なりさ。本当はもっと新宿の中心に住みたかったんだけど、家賃も高いしさすがに親が許さなくてさ。あ、スタジオアルタ行ったことある?」
彼女は優しく「ううん」と返す。その後もたわいもない会話をしながら歩く。そしてもはや目的を失った俺の下宿が見えてきた。
「ほらあそこのアパートだよ。あそこの305号室なんだ」
*
「さあ入って。お客さんが来るなんて思わなかったから散らかってるけどね」
俺に促され彼女は「お邪魔します」と息を弾ませて玄関に入った。まったく…世間知らずにもほどがあるぜ。こんな男をそう簡単に信頼していいのか?
ラジカセのある部屋に通して手近な椅子を勧める。「ちょっと待ってて、今探すから」とcd棚をあさる俺の背中には、彼女のワクワクの視線が痛いほど感じられた。純粋というか無垢というか…そんなに楽しみなもんかね。羨ましいくらいだよ…あ、あった。
「これだこれだ。ベイシティボーイズの『夕焼けの丘』」
振り返って示した俺に彼女はさらなる笑顔。どうやったらそんなに嬉しそうな表情ができるのか。俺はディスクを取り出すとケースを手渡す。
「待ってな、今かけてやるから。何年ぶりかな、これ聴くの」
ラジカセにセットして再生ボタンを押す。キュルキュルとディスクが回り、やがてその軽快なエレキギターのイントロが流れる。続いてベース・ドラム・キーボードと参入して伸びやかなボーカルが始まった。
まあ…久しぶりに聴いたがやっぱ良い曲だな。演奏技術はまだまだつたないけど、バンドメンバーの情熱と若さが伝わってくる。
「どうかな、これでしょ?君の探してた曲…」
そう言って振り返った俺はぎょっとする。彼女の瞳からは大粒の涙がこぼれていた。どうしたと尋ねる俺に彼女は首を振る。
「違うの…本当に嬉しくて。ありがとう、前島くん」
両目を拭い、そのせいで前髪が涙でへばりついたグチャグチャの顔で彼女は微笑む。俺には一体何がどうなっているのかさっぱりわけがわからなかった。
2
コンビニで二人分のペットボトルを買って戻ると、しらべはまだラジカセにかぶりついていた。何度も何度も再生し、歌詞カードを読み返している。
「ほいウーロン茶。すごいね、そんなに聴きたかったんだ」
「ありがとう。本当に前島くんにはなんて感謝したらいいかわからないよ。本当に…生きててよかった」
「そんな大げさな」
俺は自分のお茶に口をつけながら床に腰を下ろす。彼女の感動も少し落ち着いてきたようなので改めて事情を伺うことにした。
「それで…しらべちゃんはどうしてこの曲をずっと探してたの?」
彼女は数秒考えてから、ラジカセのボリュームを絞った。
「こんなにお世話になったんだから、ちゃんと説明しなきゃね」
「いや、別に言いたくないことなら無理しなくても…」
「ううん、大丈夫。実は私ね、ずっと入院しててね…」
彼女は語り始めた…本当に少しずつ少しずつペットボトルに口をつけながら。心臓の病気で幼い頃から入退院のくり返しだったこと、ここ十年は病院の外に出ていないこと、発作を起こす度に命が磨り減っていくのを感じること…。
「私にとって生きることは誤魔化すことだったの」
友達と遊びたい、学校に通いたい、街を歩いて買い物がしたい、オシャレをして旅行に出掛けたい…そんな届かない日々への憧れ。少しずつ落ちていく体力、少しずつ不自由になる毎日、少しずつ近付いてくる死神…そんな奪われる日々への恐怖。全ての気持ちは誤魔化す以外に心を持ち堪える方法がなかったとしらべは言った。
「そう…それは…なんて言えばいいか」
言葉が見つからない。もちろん驚いたが、出会った時のどこか浮世離れした雰囲気の理由にはこれで納得がいった。俺が口ごもっているのを気遣ってか、彼女は「でもね」と優しく微笑む。
「今日は朝からとっても体調が良かったの。まるで神様が一日だけ健康をプレゼントしてくれたみたいに。だから行くなら今日しかないなって」
「行くって…」
「どうしてももう一度聴きたかったの、この曲」
しらべはラジカセに視線を送る。
病室暮らしの彼女にとって唯一の娯楽はラジオだった。正確には憶えていないが、しばらく退院できないと宣告されたある日にたまたま流していたラジオから飛び込んできたのがこの曲だったという。ぼんやり聴いていたので曲名も歌手名もわからない、でもそのエネルギー溢れる歌と演奏に彼女の心は揺さぶられた。最初は何気なく横になって聴いていたのだが、そのワンフレーズワンフレーズは確実に心の鐘を打ち鳴らし、気付けば彼女はベッドから降りてラジオの前に立っていたのだ。
「今でもはっきり憶えてるの…その時の気持ち。命が燃え上がったって言うのかな、感動が止まらなかった。まだ死ねない、頑張らなきゃって思ったの」
『夕焼けの丘』は絶望の中にいる主人公が夕陽に染まる丘に立ち、オレンジ色の空にまっすぐ飛んでいくトンボを見て生きる勇気を取り戻す内容だ。切ない歌詞と明るい局長、そして爽やかだがどこか寂しげなボーカルが絶妙のバランスで寄り添っている。間違いなくベイシティボーイズの最高傑作だと俺も思う。
「まるで魔法みたいにね、その時ラジオからオレンジ色の風が溢れ出して部屋中をいっぱいにしたような気がしたの」
「…わかるよ」
素直に同意した。この曲を具現化したとしたらきっとそんなイメージだと俺も思うから。
「それでね、曲名とか歌手が知りたくて、もう一度流れないかなって思ってそれからずっとラジオをつけて過ごしたんだけど…二度と巡り会えなくて」
無理もない。ベイシティボーイズはわずか一年ほどで無名のまま解散した。俺も偶然彼らがゲスト出演したラジオを聴いてその存在を知った。『夕焼けの丘』は素直に名曲だと思ったのでcdを購入し、その後もラジオにリクエストしたりもしてみたが、結局世間に認知されることもなくその存在はレコード店から姿を消した。あれはもう俺が中学生の頃…いや小学生の終わりだったかな。幼い頃の記憶なんて曖昧なものだ。彼女が正確な日時を憶えていなくても無理はない。
「私、サビの部分の歌だけは頭に残ってたからそれを手掛かりにお母さんにもcdを探してもらったりしたんだけど、やっぱり見つからなくて。それでもあきらめきれなくて…どうしても自分で探し出したくて」
「それで病院を飛び出したの?」
彼女は頷く。
「もう今日しかないなって思ったの。こんなに体調が良い日はもうないかもしれない。不安もあったけど、自分を信じて飛び出そうって」
自分を信じて…か。俺の大嫌いな言葉だ。それこそ歌やドラマの常套句だが、根拠も実績もない奴がただ感情だけで「自分を信じて」と口にするのはむしずが走る。人には限界がある。そのことを受け入れもせずに自分を信じるなんてのはただの馬鹿だ。
でも…今目の前にいる彼女はどうだろう。いつ発作を起こすかもわからない心臓を抱えて、頼りない命を抱えて…保証のない一日に足を踏み出している。
少し沈黙が生まれたので、俺は「体調は大丈夫なの?」と問う。
「おかげさまで、今のところすこぶる快調。あ、でもそろそろお昼の薬は飲まなくちゃ」
彼女はポーチから取り出した錠剤を慣れた手つきで口に運び、ペットボトルを飲む。見ると時計は午後1時半。
「こんないい気持ちでお薬飲むの初めてかも。今日は本当に勇気を出してよかった」
そう言うとしらべは俺をじっと見る。
「え、何?」
「本当にありがとう、前島くん。…いい人だね」
「そんなことないって」
恥ずかしい。少なくとも君を部屋に誘った時、俺には邪な思いもあったよ。感謝される資格なんてない…ごめんな。その綺麗な瞳に俺なんか映しちゃダメだ。こんな薄汚い男を見つめちゃダメだよ。
俺は謝ろうとしたが、やっぱりやめてペットボトルを飲む。そこで彼女は思いついたように「今度は前島くんのこと教えてよ」と言った。
「え?」
「私ばっかり話してるじゃない。確か予備校に通うために一人暮らし始めたんだよね」
あまり話したくないことだった。でも彼女への申し訳ない気持ちがあったので俺は口を開いた。
「…俺ね、オチコボレのボンボンなんだ」
俺の話を彼女は黙って聞いてくれた。話しているうちに気付く…きっと俺は聞いてもらいたかったんだと。
俺の親父も親父の親父も医者だった。そして二人の兄貴も医者になった。だからってわけじゃないが、俺も医学部を目指した。まず現役の受験は見事に失敗。それで親父に相談して、医学部専門予備校に通うために八王子から四ツ谷に出てきた。そして始まる俺の浪人生活…一年目、二年目と失敗して今年の春に賞味四回目の不合格。さすがにやる気も失せてしまい、そもそも本当に医者になりたかったのかもわからなくなっていた。
「それでさ、今年はもう予備校にも行かずにブラブラしてんだ。親父には勉強してるって嘘ついて仕送りだけはもらってさ…最低だろ?まあ親父も半分気付いてるみたいで、仕送りはだんだん減らされてるけどね。
…だからしらべちゃんに感謝されるような奴じゃないよ、俺は」
「そう…」
悲しそうに呟いた彼女。
「はい、俺の話はこれにておしまい!それよりベイシティボーイズだろ、せっかくだからしっかり聴こうぜ」
俺は沈んだ空気を払うように明るく言うと、再びラジカセのボリュームを上げた。
3
それから二人で色々な話をした。歳が近いので漫画やアニメなども共通の話題が多い。まあ彼女は入退院をくり返していたので知らないこともあったが、その点に気遣いながら俺はできるだけ楽しい雰囲気になるよう努めた。彼女もたくさん笑ってくれた。
「ああ楽しい、こんなに人と話したの何年ぶりだろう。友達もみんな忙しくてなかなかお見舞いに来てくれないから」
「こちとら暇な浪人生、なんぼでもつき合いますぜ」
「またそんなこと言って…実家のお父さんに怒られるよ?」
そこで彼女は少し淋しそうな顔。
「もうあきらめられてるって。あ、実家っていえばさ、ベイシティボーイズの出身は横浜だろ?実は横浜には『夕焼けの丘』のモデルになった公園があるんだぜ」
「本当?」
彼女は途端に明るくなる。やっぱり笑った顔が可愛い。
「前にベイシティボーイズがラジオにゲストで出た時に言ってたんだ。港が見える公園で、そこの丘でこの曲の歌詞を思いついたって。ちょうど季節も今頃でさ」
「そうなんだ…」
ワクワクしているしらべに俺は「行ってみるかい?」と尋ねる。俺が言い終わらないうちに彼女は「うん!」と大きく頷く。
「了解。じゃあ俺の車で連れてってやるよ。あ、でも体調は大丈夫かな」
「大丈夫だよ。前島くん、車まで持ってるんだね」
「ボンボンだって言ったろ?」
そこで二人で笑い合う。笑うなんて…いつ以来かな。
…ピンポーン。
ふいに玄関のチャイムが鳴った。滅多に客なんて来ないのに。宅配便か?それともまた受信料の取立てか?彼女に「ちょっと待ってて」と伝え俺はインターホンの受話器を取る。
「はいもしもし?」
「突然すいません、こちら警視庁のムーンという者ですが」
女の声だった。ムーンというのはよくわからないが警視庁ってことは…警察?
「あの、何のご用でしょう」
「実はある若い女性を捜しておりまして。少しお話を伺えませんか?」
「はあ…」
曖昧に返事をして受話器を置く。振り返るとしらべが不安そうな顔で俺を見ていた。手短に事情を説明すると彼女は「きっとお母さんだ」と呟いた。
「お母さんが警察に通報したんだ。私を捜してほしいって…それできっと」
「そうか。じゃあ…どうする?」
彼女はブンブンと顔を横に振った。
「お願い、まだ連れ戻されたくないの。一緒に…一緒に夕焼けの丘を見に行きたい。それが終わったらちゃんと病院に帰るから」
「でも…」
「お願い。きっとこんな日はもうないから。お願い…前島くん!」
彼女はそうせがみながら涙ぐむ。そして玄関から再びチャイムが鳴る。
…ピンポーン。
TO BE CONTINUED.
(文:福場将太)