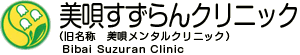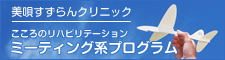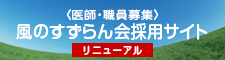- ホーム(法人トップ) >
- 美唄すずらんクリニック >
- コラム >
- 2010年2月
コラム
2010年2月スペシャルコラム『薬剤師探偵と雪の出会い(ふれあい編)』
※このコラムは愛する職場をモチーフにしたユーモアミステリーであり、フィクションです。
「じゃあ、まずは世間話でもしましょうか、馬渕さん」
彼女はそう言って紅茶の缶を窓のところに置く。青年もコーヒーの缶をそのとなりに置き、ゆっくりと口を開いた。
「はい……、じゃあ……む、邑上さんはこの電車でどこに向かわれているんですか? 確か、先ほど北海道の人間じゃないとおっしゃってましたけど……」
「ええ、今は九州で働いています。北海道には前に1年ほど暮らしていたことがあるんです。心の病院の薬剤師として……。その時職場で仲良くなった女の子がついに結婚することになって……その披露宴に昨晩出席してたんです。まあもう少しゆっくりしたかったんですけど、仕事もあるんで今日すぐに帰ることにしたんですけど……まさかこんな大雪になっちゃうなんて」
「そうだったんですか。普段九州なら、雪も久しぶりなんじゃないですか?」
「そうですね。なんかふるさとに帰ってきた気がします。あの頃が懐かしい……」
「ふるさとに帰る……」
そこで青年は声を荒げる。
「そうです! 僕は帰ろうとしていたんです、ふるさとに! そう、そのために空港に向かっていた……そう、確かそうでした!」
「記憶が戻ったんですか?」
「え、ええ、少し……。確かに僕は、ふるさとに行こうと思い立って空港に向かった……でも、僕はいったいどこへ行こうとしていたんだろう……」
一瞬嬉しそうな顔をした青年の表情は再び固くなる。
「ふるさとってことは、ご実家じゃないですか?」
「いえ、僕は道産子で、両親も両祖父母もみんな北海道にいますので……特に道外に実家などはありません。親戚も特には……」
「……そうですか」
「それに……ふるさとに行こうとしていたはずなのに、なんだか……自分でもよくわからないのですが、今まで行ったことがない場所に初めて行こうとしていたような……そんな気もするんです」
「今まで行ったことがないのに……ふるさと?」
「お、おかしいですよね。道産子なのに道外にふるさとがあって、ふるさとなのに今まで行ったことがないなんて。や、やっぱり僕の記憶はどうかなっちゃったんでしょうか、あぁ……」
青年はそこで頭を抱え込む。
「だ、大丈夫ですよ。きっとちょっと混乱してるだけですよ」
彼女は慌てて青年をいたわる。
「馬渕さん、ほら、顔を上げて下さい。せっかく記憶が戻ってきたんじゃないですか、もう一度ゆっくり考えてみましょうよ。そうだ、チケット……! 飛行機に乗ろうとしていたんなら、航空券を持ってるんじゃないですか? それを見れば何かヒントになるかも……」
青年は彼女の言葉に再び冷静さを取り戻す。彼は顔を上げ無理に笑顔を作った。
「そ、そうですね。……すいません邑上さん、僕、すぐに取り乱しちゃって……。せっかく邑上さんが付き合って下さってるのに……」
「いえ、そんな……」
「落ち着いて少しずつ考えます。そうですね、チケットがあれば……記憶を辿る手掛かりになりますもんね。ちょっと待ってください」
青年は服のポケットを探り、中身を取り出した。
「ええと、財布に、手帳と……家の鍵……だけですね。航空券はないみたいです。きっと僕は……空港に着いてから買うつもりだったんでしょう」
「でも、この電車に乗った時の乗車券はあるんじゃないですか?」
「それも……見当たりませんね。きっと……この財布に入っている乗車カードを使って乗ったんでしょう。仕事でしょっちゅう電車を使うので、いつも電車カードを持ってるんです」
「あの、失礼ですが、お仕事は何を?」
「え? え、あ〜。僕、実は製薬会社で働いているんです。プロパーって言って、色々な病院にお薬の紹介をして回る仕事を……って、すいません、邑上さんは薬剤師さんだからご存知ですよね」
「プロパーさんだったんですか。じゃあ私たち、近い仕事をしていたんですね」
「そんな……薬剤師の先生にはいつもお世話になってます。ああ、薬剤師さんに迷惑かけるなんてプロパー失格ですね」
「そんな、気になさらないで下さい。こちらこそ製薬会社さんにはいつもお世話になってます」
彼女はそう言うと嬉しそうに紅茶に口をつけた。
「でも馬渕さん、プロパーさんって大変ですよね。色々気を遣われることも多いでしょう」
「ええまあ。自信を持って発売したお薬を使ってほしくて色々なお医者さんにご紹介するのですが、なかなかうまくいかなくて……。すっごく仲良くなって、この先生は熱いぞって思ってもお薬は使ってくれなかったり、ご紹介してもあんまり興味なさそうだった先生が大穴で薬を採用してくださったり……。あ、すいません、こんなつまんない話……」
「いえいえ。前の職場の薬局長なんかよくプロパーさんと遊びに行ったりしてましたし、私も時々混ぜてもらってたんで……そういう話題、好きですよ」
「邑上さんって……いつもそんなに優しいんですか?」
「そんなことないですよ。むしろ職場じゃ無口で地味なやまとなでしこやってます。あ、それよりその手帳にふるさとの手掛かりとか書いてないですか?」
「あ、そうですね。見てみましょう」
青年は手帳をめくり始めた。
「……今日の日付何も書いてないですね。年末年始にも特に気になる記載は……」
確かにほとんどメモなど書き込まれていないようだ。彼女もそれを覗き込む。
「時々土曜日と日曜日に丸がつけられてますね。あ、でも7月から9月だけか……。休日に遊びに行く予定でしょうか?」
「わ、わかりません……遊びなら冬にだって行きますし……。それに、毎月末日に片仮名で『キムラ』と書かれてるみたいですけど……木村なんて名前に思い当たる人いないんですけど」
「面会する先生の名前とかじゃないですか?」
「いえ、そんな先生は……。でもここに書いてるってことは、僕は毎月木村って人に会ってたんでしょうか? でも、去年の10月以降はキムラのメモもなくなってるし……何かあって会うこともなくなったんでしょうか。全然思い出せない……もしかしたら、失くしている記憶は今日だけじゃないのかもしれません」
「馬渕さん、焦っちゃダメです」
と、彼女の強い口調。
「わ、わかってます。飲み物も冷めちゃいますから、ちょっと関係ない話でもしましょうか」
*
窓の外……空からの贈り物は続いている。動き出すことのないその車中で、2人の会話はいつしか青年の身の上話になっていた。
「じゃあ、馬渕さんはおじいちゃん子だったんですね」
「ええ、子供の頃はいつもおじいちゃんと一緒でした。昔話が好きなおじいちゃんで、おじいちゃんは自分のおじいちゃんから聞いた話を僕に得意げにするんです。祖々々父の話ですから、それこそ明治時代とかの話です」
「それはいいおじいちゃんですね」
「大好きでした。よく横に布団を敷いて一緒に寝たりもしました。まあ、しつけは厳しい人でしたから、僕はよく怒られてはぶててましたけど」
懐かしそうに話していた青年はそこではっとなる。
「あ、すいません。僕また自分の話ばかり……。記憶をなくしてのんびりしてる場合じゃないのに」
「いえ、とってもあったかいお話でした。それに、まだ電車は動き出しそうにありませんし」
そこで2人は窓の外を見る。
「それにしても……よく降りますね……。馬渕さんは道産子ですからもう慣れっこですかね」
「まあ……、でも今だからこそ暖房やストーブがありますけど、それこそ祖々々父の時代なんか大変だったでしょうね。こんな電車だってなかったんですから」
「そうですね……。でも、そろそろこの電車には動いてほしいところですけど」
「このまま停まってたら後ろから来る鈍行列車にさされちゃいますね」
青年がちょっとおどけてそう言った瞬間、彼女の紅茶を飲む手が止まった。彼女は沈黙している。
「え? む、邑上さん?」
彼女は固まっている。青年は驚いて言葉を続けた。
「え、僕何かまずいこといいましたか? あ、今のは冗談ですよ。この雪じゃ後発の電車だって停まってるでしょうし……。あの、不愉快な気持ちにさせたのなら……謝ります」
動揺する青年の言葉を一掃するかのように、彼女はやがてゆっくりと口を開いた。
「……調剤完了じゃ」
その声は今までとは別人のように深く透き通っている。

「む、邑上さん……?」
「馬渕さんの身に何が起こったのか、そして馬渕さんのまだ行ったことのないふるさととはいったいどこか……」
「わ、わかったんですか?」
驚く青年に、彼女ははっきりと告げた。
「謎と手掛かりを調合し、真実を処方する」
(次回、「別れ編」にて完結)