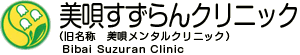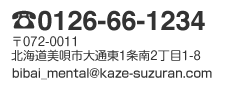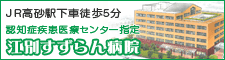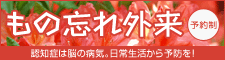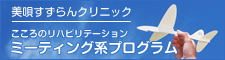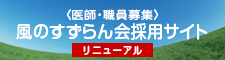- ホーム(法人トップ) >
- 美唄すずらんクリニック >
- コラム >
- コラム2025年1月「病名の由来」
コラム
コラム2025年1月「病名の由来」
新年明けましておめでとうございます…という言い回しは実は間違っている、という話を聞いたことがある。古い年が明けて新年が来るのだから、けっして新年が明けたわけではないという理屈らしい。
まあこんな言葉の間違い・勘違いは日常茶飯事であって、目くじらを立てて訂正するほどのことでもないのだが、医療における病名も時としてそんな間違い・勘違いを生む。
例えばクローン病という名称。このクローンは学者の名前であって、遺伝子工学のクローン技術とは一切関係ない。ダウン症も、ダウンという言葉から倒れるイメージがあるかもしれないが、これも人名。川崎病も、四日市喘息のように川崎市で発生した公害病のようだが、これもまた人名である。かくいう僕も医学部に入るまで、自閉症は部屋に閉じこもる引きこもりの病気なのだと思いこんでいた。
そんな勘違いを避けるため、あるいは誤解による偏見をあおらないために、正式に改められた病名もいくつかある。
例えば、かつて精神分裂病と呼ばれていた病気は統合失調症に改められた。精神機能の統合、すなわち心の働きのまとまりがうまくとれないという病態を的確に表している。実は研究者の名前にちなんでブロイラー病にする案もあったそうだが、日本でブロイラーというとどうしても鶏をイメージしてしまうので不採用だったらしい。
他にも、痴呆症という呼び名が認知症に改められたのも有名だ。確かに「痴」も「呆」もマイナスイメージのある漢字なので改名はよかったのだが、ただ認知症という呼び名ではやや説明不足。認知機能、すなわち記憶したり認識したりする脳の働きに支障が出る病気なのだから、認知不全症などとした方が丁寧だ。まあそうすると、何もわからない人のように誤解されかねないので難しい所ではあるのだが。
僕の持病の眼科疾患・網膜色素変性症はどうだろう。網膜の中にある視細胞が徐々に壊れていく病気で、おそらく病名はこのことを表している。逆に進行性の夜盲症と視野狭窄という具体的な症状については病名からはわからない。むしろ「色素」という単語から色覚異常が主体の病気と誤解されるかもしれない。
そんなわけで病気のネーミングというのはなかなかにして難しいものなのだが、最後にこれだけは声を大にして伝えておきたい。
適応障害に発達障害、気分障害に人格障害と、精神科にはやたらに『障害』というワードが入る病名が多い。しかしながら、その診断を受けた人がイコール障害者ということではけっしてない。手帳や年金を受給する際に程度を認定される『障害』と、病名の中にある『障害』は別物。英語では別の単語であるのを同じ『障害』という日本語を宛ててしまったことによる混乱である。ちなみに患者さんが社会生活する上で支障になる環境側の原因のことも、日本語では『障害』と呼ぶので、ますますややこしいことになっている。
病名には成り立ちがある。ネーミングが誤解や偏見を招くこともあるが、研究に尽力した医療者の思い、理解を求めて闘った患者の願いが込められた名称もある。現在何らかの診断を受けて治療をしておられる方、改めてその病名の由来を調べてみるのもよいだろう。
(文:福場将太)