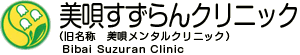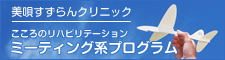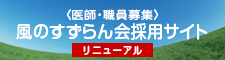- ホーム(法人トップ) >
- 美唄すずらんクリニック >
- コラム >
- 2014年06月
コラム
2014年06月「HAPPY NURSE DAY」
この季節、あの儀式がそういえば毎年行なわれていた。それはもう随分と懐かしい、東京で過ごした大学時代のこと。
儀式の名は『戴帽式』。残念ながらこれは医学部の行事ではない。うちの大学には看護専門学校も併設されていたため、部活によっては医学生と看護学生の両方が所属しているものもあった。僕が所属していた柔道部・音楽部もそうで、特に柔道部においてはマネージャーだけでなくプレイヤーとしても看護学生が所属しているのが古くからの慣例であった。僕が1年生で入部した時も、医学部男子と並んで看護学部女子2人が入部した。2人とも同い年であったこともあり、時間を共有する中で看護学生の実態を良くも悪くも知ることとなった。いや、別に今回のコラムは喫煙とか合コンとかを批判する内容じゃないのでご安心を。
医学生の場合、病棟で実習するのは5年生だ。最短でも23歳、浪人や留年でもっと年上の場合も珍しくない。対して看護学生の病棟実習は2年生から始まる。つまり20歳。正直すごいと思う。その若さで医療の現場に触れるのだから。そこで目にするものはけして夢や希望だけではない、否が応でも過酷な現実をいくつも知ることになる。もし自分がわずか2年生にして病棟実習で患者さんを受け持てと言われたら、多分気持ちで負けてしまうと思う。やっぱり女は度胸、ということだろうか。
それはさておき、看護学生が病棟実習を始めるに当たりその証としてナースキャップを授与される儀式がある。それこそが『戴帽式』である。僕の柔道部同期だった女子2人も、2年生の6月にその儀式に参列した。
戴帽式は平日午前に体育館で行なわれる。これは看護学校の行事なので当然医学部の方はその時刻講義中。それでも柔道部のように看護学生も所属している部活では、体育館前に医学生部員もかけつける。そして出てきた彼女たちをお祝いしてあげるのが通例だ。つまりこの日は講義を抜け出す医学生が続出することになる。僕も1年生の時から6年間このお祝いに参加したが、やはり自分の同期が戴帽した時は感慨深かった。式典そのものは外から見ることはできないので詳細は知らない。噂ではキャンドルサービスのようなことをするらしい。その間医学生は体育館の外で花束とプレゼントを抱えて待ちぼうけ。そして識を終え体育館から出てきた彼女たちはナースキャップと白衣に身を包んでいる。その姿は紛れもなく白衣の天使…というほどおぼこくはなかったが、それでも看護師の玉子のオーラは十分だった。同じタイミングで入学したのに、なんか一歩も二歩も先を行かれた感じがした。ちなみにうちの看護学校は3年制だったので、こっちが病棟実習する頃にはもう向こうはプロの看護師2年目になっている計算だ。その時はどうかいじめないで、なんて冗談を交わしながら花束贈呈と記念撮影。最後に柔道部恒例の胴上げをしてめでたしめでたしってな感じでそのイベントは終わる。
とまあここだけ読めば明るく楽しいことばかりのようだが、もちろんそれはその時だけ。看護学生たちは過酷な病棟実習を経て卒業し、やがて看護師となり、病院における最大組織である看護部の一員となるのだ。その闘いは生易しいものではないだろう。詳しくその大変さを尋ねたことはないが、見ていればそれは十分に伝わってくる。
 看護師、それはきっと生半可な気持ちではできない仕事だ。誇りがなければできない仕事だ。もしかしたら医師よりもずっとずっと誇り高いかもしれない。クリニックで一緒に働いている看護師さんたちを見ていても思う。自分への厳しさ、患者への優しさ、おどけていてもそこにはどんな試練にも屈しない強さが感じられる。その誇りと信念はきっと看護学生時代から培われてきたのだろう。僕が医学部5年で病棟実習に出た時、同じように実習している看護学生たちを見た。彼女たちは病棟に入る時と帰る時、必ず頭を下げて病棟ナースに挨拶する。「今日もよろしくお願いします」「今日はありがとうございました、失礼します」…どうやったらバレずに帰れるかばかり考えていた自分たちが恥ずかしくなるほど立派な姿だった。もちろん一歩外に出れば合コンもして喫煙もするのかもしれない。それでもあの厳しい教育としつけは強靭な精神を育てる上で必要なのだろう。残念ながら医学部にはそれがなかった。あるのは進級や国家試験合格のためのプレッシャーばかり。看護師にとってのナイチンゲール誓詞のように、医師としての新年や精神を磨く教えはあまり受けた記憶がない。だからこそ余計に彼女たちが誇り高く感じられるのかもしれない。
看護師、それはきっと生半可な気持ちではできない仕事だ。誇りがなければできない仕事だ。もしかしたら医師よりもずっとずっと誇り高いかもしれない。クリニックで一緒に働いている看護師さんたちを見ていても思う。自分への厳しさ、患者への優しさ、おどけていてもそこにはどんな試練にも屈しない強さが感じられる。その誇りと信念はきっと看護学生時代から培われてきたのだろう。僕が医学部5年で病棟実習に出た時、同じように実習している看護学生たちを見た。彼女たちは病棟に入る時と帰る時、必ず頭を下げて病棟ナースに挨拶する。「今日もよろしくお願いします」「今日はありがとうございました、失礼します」…どうやったらバレずに帰れるかばかり考えていた自分たちが恥ずかしくなるほど立派な姿だった。もちろん一歩外に出れば合コンもして喫煙もするのかもしれない。それでもあの厳しい教育としつけは強靭な精神を育てる上で必要なのだろう。残念ながら医学部にはそれがなかった。あるのは進級や国家試験合格のためのプレッシャーばかり。看護師にとってのナイチンゲール誓詞のように、医師としての新年や精神を磨く教えはあまり受けた記憶がない。だからこそ余計に彼女たちが誇り高く感じられるのかもしれない。
心の医療においても、看護師の存在はとても大きい。外来でも入院でも、一番患者さんと接しているのは紛れもなく彼女たちなのだ。
戴帽式でナースキャップを受け取ったあの日、その心にはどんなキャンドルが灯されたのだろう。彼女たちは誇りを持って医師の指示を受けてくれる。僕はいつも助けてもらってばかりだけど、たまには心のキャンドルが燃え上がるような、しびれる指示を出したいものだ。
(文:福場将太 写真出典:カヤコレ)