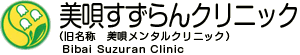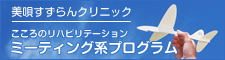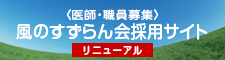- ホーム(法人トップ) >
- 美唄すずらんクリニック >
- コラム >
- 2017年11月
コラム
2017年11月★スペシャルコラム「刑事カイカン 赤い実、15歳の日々(前編)」
*このコラムはフィクションです。
■プロローグ ~赤井このみ~
そう、あたしはドーナツ。
「ねえ、あんたは一体誰?」
思わず足を止め、目の前のあまりにもちっぽけな存在に問いかけた。
「つまんなそうな顔しちゃってさ。ねえ、あんたは誰なの?」
なんの工夫もないショートボブの黒髪、ワンポイントのオシャレもない制服、センスの欠片もない鞄、ソックス、靴…ぜ~んぶ全部何から何まで校則どおりのコーディネイト。ごらんあれ先生方、これぞお望みどおりの模範的な女子中学生でございます。
「ねえ、あんたは何がしたいの?」
また言ってみる。もちろん相手は何も返さない…それどころか全くおんなじ口の動きでおんなじ言葉を投げかけてくる。そしてお互い呆れ笑い。
そりゃそうだ、それはガラスに映ったあたしなんだから。そう、ちっぽけなのはあたし、何者かわかんないのはあたし。ほんと何やってんだろ、帰り道に突っ立って、ビルの窓に映った自分に話しかけて…バカみたい。スマートフォンの画面を見るともう午後6時過ぎ、とっくに日が暮れた通学路には他に制服姿の子はいない。
さっきの進路面談の時の先生とママの顔…なんで二人ともそんなに楽しそうに笑ってんのって感じだった。「娘さんのご成績なら私立の高校でもどこでも入れますよ」なんて担任たる風間先生が言って、「そんなそんな、先生方のご指導のおかげですわ」なんて保護者たるママが言って、当事者たるあたし一人が置いてけぼりでどんどんどんどん話が弾んで…結局それでおしまい。あたしの進路面談なのに一体誰の話をしてんの?言われても嬉しくないとこばっか褒めるし、まあ何か要望がありますかって訊かれてもたいしてないんだけどさ。
…ハア、あたしって何なんだろ。
小さな溜め息。それをかき消すようにビル風が吹き抜ける…排気ガスの嫌な臭いがする。
「あんたも大変だね」
また目の前の自分に言ってみる。今度はお互い苦笑い。いい加減そろそろ帰ろっかな、ママはご機嫌のまま会社の忘年会に行っちゃったから家には誰もいないけど。ご褒美にって買ってくれたドーナツの袋だけがあたしの手にぶら下がってる。
あ~なんだろこの感じ、気持ちがモヤモヤしてとにかくつまんないつまんないつまんない。そう、まるでドーナツ。あたしは一番肝心なとこがぽっかり空いちゃってるんだ。
「そんなにつまんないなら、何かしてみればいいじゃない」
え?今のあたしが言ったの?他に誰もいないしあたしの声だからそうだよね。なんかガラスに映った方のあたしが言ってくれた気がした。
何か…してみる?頭の中でそうくり返した瞬間だった。
…パチン!
びっくり、胸の奥で何かがはじける音がした。周りに聞こえちゃいそうなくらい、クラッカーみたいに大きくて軽快な音。
何かする?そっか、そうだよね。何かすればいいんだ。遠慮せずにやったらいいんだ、どうして今まで思い付かなかったんだろ。そうだ、そうだよ、何かしよう。何でもいいから何かしよう!
「ありがと!」
そう言うと、あたしは導火線に火が着いたねずみ花火のように勢いよく駆け出した。
■第一章① ~赤井このみ~
1
「帰ろうよ、このみ」
ホームルームの後、すみれがそう声をかけてきた。
「ごめん、チャビンに呼び出されてんの」
「え、また?これで三日連続じゃん、敵も手ごわいねえ」
言葉とは裏腹にすみれの目は明らかにニヤついてる。
「こら、面白がってるでしょ」
「キャハハ、ま、しょうがないか…でもまさかこのみがそんな大胆なことするなんて思わなかったな。これまでどっちかっつうと地味系だったから、いきなり反乱軍のリーダーになっちゃうなんて」
「別にリーダーじゃないし、っつーかメンバー誰よ」
「そっかそっか。でもうちは似合ってると思うよ、それ」
すみれは視線をあたしの頭に向けて微笑む。
「…ありがと、じゃあ闘ってくるね」
そう言いながら立ち上がり、ゆっくり深呼吸。
「お、臨戦態勢だね。ファイトだ!」
そんなあったかい声援を背中に受けながらあたしは教室を出た。
*
「おい、聞いてるのか赤井、いつまでそんな髪してるつもりだ?年が明けたら受験なんだぞ、そんな頭で受けられると思ってるのか?」
狭い生活指導室にチャビンのだみ声が響く。窓にはせっかく12月の冬空が綺麗に広がってるのにこれじゃ台無し。
「いいか、お前は成績も良いしこれまで三年間なんのトラブルもなかった。このままいけば内申書だって問題なしだ。なのになんで今になってそんな不良みたいなことをする?」
「別に不良になったわけじゃありません。勉強だってしてます。それに受験要項に髪の毛の指定はなかったと思いますけど」
「屁理屈言うんじゃない!なあ赤井、一体どうしちゃったんだ?これまでのお前はどこに行っちゃったんだ?風間先生も心配してたぞ。なあ赤井、何か悩んでるんなら相談に乗るぞ」
チャビンは今度は声を落として「誰かに何か言われてるのか?」「危ないことに巻き込まれてるんじゃないのか?」とこっちの目を見て言ってくる。的外れにうんざりしながらあたしは「そんなことありません。自分がしたくてしているだけです」と返した。
「それならさっさとその変な髪を元に戻しなさい!」
チャビンがキレた。あたしは「失礼しまーす」と足早に部屋を出る。ドアを閉める時にまだ後ろでゴチャゴチャ言ってたけどそんなの気にしない。フンだ、何が変な髪よ、あんたのバーコード頭の方がよっぽど変だって。あたしはあたし、別に先生の期待に応えるために生きてるわけじゃないんだから。
教室で鞄を取るとそのまま早足で階段を下りる。踊り場の鏡に映る女子中学生は今までとは違う、制服と顔はおんなじだけど髪の色は真っ赤。赤毛のアンもびっくりの鮮やかな真っ赤っか。そう、まさに名を体で表したあたしは赤井このみ。
なんだろ、この気持ちの良さ…モヤモヤの霧が晴れて雲一つない青空が広がったみたいに心が晴れ晴れしている。テストで学年一位になった時より、修学旅行でランドマークタワーに上った時より、ママに新商品のコロンを買ってもらった時よりずっとずっと良い気分。よ~し、二段飛ばしだ!
ジャンプで1階に着地、1年生の何人かがこっちを見てるけど…どう?この髪、ちょっと素敵でしょ?
校舎の出口に向かって廊下を進む。 …あれ、あの人誰だろ?
職員室の前で教頭先生と名刺交換してる女の人が目に入る。…うわあ、すっごい美人。淡く茶色に染めた髪をセンターで分けて肩まで伸ばして…薄紫のコートはちょっと地味だけど、似合ってるっていうか着こなしてる。それになんてったってあの切れ長の目、すっごい綺麗。
誰なんだろあの人、女優さん?学校でドラマの撮影でもするのかな?
そんなことを思いながら校舎を出る。さて、これからどうしよう。すみれはもう帰っちゃっただろうし、宿題も授業中にやっちゃったから帰ってもやることないし…あ、そうだ。
ひらめいたあたしはあの場所に向かう。
普段あまり使われない旧体育館、その裏側にある壊れた机や椅子の廃棄場…そこがあたしのお気に入りの場所。1年生の時に散歩してて偶然見つけてから時々足を運ぶこの学校でのあたしの秘密基地。どうしてだかわかんないけど壊れて積み上げられた机や椅子を見てたら心が落ち着くんだ。
グラウンドの脇を抜けて、旧体育館の裏に回って少し草が生えた所を通る。体育館の中からはスパーンスパーンって音がする。何かの部活だろうけど、冬休みも近いのにご苦労様だね。草むらを抜けると机と椅子の山が見えてきた。そういえば髪を赤くしてからここに来たのは初めてだな。来たよ、あたしの坊やたち。
「どう?髪を赤く染めてみたんだ」
そう言って机と椅子の山に駆け寄る。柔らかい風が吹いて少しだけ木の香りがした。この感じもあたしは大好き。続けて「結構似合ってると思わない?」と問いかける。
「フフフ…いいんじゃないですか?」
突然低い声がした。え、嘘、ほんとに机が喋った?
「最近の中学生にはそういう髪がはやってるんですか?」
空耳じゃない、確かに声がする。でもまさか机が喋るわけないよね。…ってことは。あたしは急いで山の裏に回ってみる。するとそこには驚くべき人が立っていた。
2
「うわああ」
思わず声を上げてたじろぐ。だってこの人…変な格好してるんだもん。ところどころ破れたボロボロのコートに冒険家みたいなツバの大きなハット。そして長い前髪は右目を隠してる。一体何なの、この人…。ひょっとして変質者?反射的にポケットのスマートフォンに手が伸びる。
「こんにちは、ここの生徒さんですね。驚かせてごめんなさい、けして怪しい者ではありませんからご安心を」
いやいやいやいや怪しいでしょ、怪しさ満天でしょ。でも確かに…声は低くて落ち着く感じだし言葉遣いも丁寧。前髪に隠れてない左目も黒く澄んでる。
「お、おじさんは誰ですか?」
「おじさんですか、フフフ…。私はカイカン、警視庁捜査一課所属の刑事ですよ」
刑事ってことは警察だよね。この人警察官なの?じゃあもしかして変装してるとか?
「刑事さんなんですか。け、刑事さんがどうしてこんな所に?」
「いやあ、私の部下が用事でこの学校に来てましてね、待っている間暇なので校内を散歩してたらここを発見したんです。あ、用事といっても別に学校で事件があったわけじゃないので安心してください」
「そうですか…」
一応納得してあたしはそっとスマートフォンから手を放す。でもカイカンって一体どういう名前なんだろ…そんな名字あるのかな?
「それにしても…ここはなんだか落ち着く場所ですね。長年生徒さんたちを支えた机や椅子が役目を終えて休んでるというか…お疲れ様って感じかな」
こっちの戸惑いなんかお構いなし二カイカンさんは話す…よくわかんないけどちょっと嬉しそうに。この場所が落ち着くってのは同感…フフ、変な人だな、なんだかおかしいや。
「ここは君の秘密基地かな?だったら大切な時間を邪魔しちゃ悪いので私は失礼しますね」
…わあびっくり、どうしてわかるんだろ?刑事さんだから?
「あの、どうしてそう思うんですか?ここがあたしの…その、秘密基地だって」
「フフフ、私にも経験がありますからね。休み時間とか放課後とか、無性に一人になりたくなって、誰にも見つからないお気に入りの場所で過ごしたりしたもんです。ちなみに私の秘密基地は屋上に上がる誰も来ない階段でしたが。
別に珍しいことじゃありません、というよりほとんどの人はそういう場所を隠し持っているものですよ」
そうなんだ。じゃあすみれとか他の同級生もみんな秘密基地にこっそり行ってるってこと?校内にそんなにたくさん秘密の場所があるのかな。
「そうですか…。はい、ここがあたしの秘密基地なんです。刑事さん、全然邪魔じゃないですからどうぞゆっくりしていってください。初めてのお客さんです」
「それじゃあお言葉に甘えて」
そこであたしとカイカンさんは積まれた椅子の山の中からまだ座れそうなのをそれぞれ見つけて腰を下ろす。不思議な感じだった、変な人だとは思うけど悪い人じゃないみたいだし…それにあたしの周りにいる大人たちとは何かが違う。
「君、お名前は?」
「赤井です、赤井このみ」
「そうですか。その髪の色にぴったりのお名前ですね。確か最近染めたって先ほどおっしゃってましたね」
独り言を聞かれた恥ずかしさもあってあたしは無言でコクンと頷く。一瞬の沈黙…また木の香りがした。風に前髪が揺れておでこがくすぐったい。カイカンさんの長い前髪もそよいている。
「あの…」
風が通り過ぎると、自然とあたしの口が開いてあの日のことを語り始めた。
「あのですね、刑事さん、あたし別に不良ってわけじゃないんですよ。今まで悪いこともしたことないし…むしろもっと色々すればよかったなって思ってるくらいで」
カイカンさんはじっとこっちを見ている。
「とりあえず勉強はしてたんですけど、それで成績もまあまあ良くて、先生からも親からも褒められて…最初は喜んだりもしたんですけど、最近になってなんかつまんないっていうか、このままでいいのかなって気持ちがどんどん大きくなってきたんです。でもどうしていいかわかんなくて…ずっとモヤモヤしてて」
「ナルホド」
独特のイントネーションで低い声の相槌。
「先週の金曜日も進路面談があったんですけど、なんか先生と母親だけで盛り上がっちゃって…あたしは蚊帳の外でした。日が暮れた誰もいない帰り道でビルの窓ガラスに映った自分を一人で見てたらとってもつまんなくなって…寂しい気がしてきました。それでガラスに映った自分に話しかけたりして…バカみたいですよね。
そしたら突然胸の奥でパチンって音がしました。そして思ったんです、このままじゃいけない、何でもいいから何かしてみようって。まるでパチンが合図だったみたいに」
カイカンさんの口元がちょっとほころぶ。
「それであたし、そのまま勢いでコンビニに行って、髪染め液買ったんです。髪の毛を赤くしたらなんだかスカッとしました。
…あの、あたしって変ですか?」
「フフフ…」
カイカンさんは小さく笑ってゆっくり首を振る。そして右手の人差し指を立てて言った。
「ちっとも変じゃありませんよ。君くらいの年頃ではそういうモヤモヤやパチンはあって当然です」
「ほんとですか?でも同級生にはそんな子いませんよ。受験生だからみんな勉強の話ばっかりで…。友達はこの髪のこともいいねって言ってはくれますけど、でもやっぱ驚いてたかな」
「人それぞれモヤモヤの形は違いますからね。それにパチンの時期もそれぞれ違う。一生モヤモヤしたままでいられる人もいますけど、大人になってからパチンが来る人もいます。だから君くらいの年頃でちゃんとそうやってパチンがあるのは悪いことじゃありません」
なんだかわかるようなわかんないような話だけど、それでも先生やママみたいに怒ったり嘆いたりされないだけ有難い。
「刑事さんもモヤモヤやパチンはありました?」
「もちろん。最初のパチンで私はこのハットをかぶりました。二度目のパチンがこのコートかな…ちょうど君くらいの年齢の頃です。初めて着た時は先生も親も大反対でしたよ。母親なんて恥ずかしいからやめてくれって泣き出しちゃって…まあそれでも懲りずに続けてたら呆れて何も言わなくなりましたけど」
あたしくらいの年齢って…何年同じコートを着てるんだろ。でもこのボロボロさを見たらそれも納得。
「あたしも母親からしばらく口をきいてもらえませんでした。生活指導のチャビンからは毎日呼び出されて怒られるし、最悪です」
「チャビン?」
やば、うっかり言っちゃった。
「ごめんなさい、友達とこっそりそう呼んでるんです。生活指導の南波先生、バーコード頭のハゲチャビンだから」
「フフフ、それは手痛い、先生も大変だ」
「やっぱあたし…迷惑かけてますかね」
カイカンさんはまた首を振った。
「いいんじゃないですか、そういったことができるのもモラトリアムの特権です」
モラトリアムって…何だっけ?どうしてだかわかんないけどあたしの頭にはまたドーナツが浮かぶ。モラトリアムの意味を尋ねようとした時、向こうから声がした。
「警部!」
見るとさっき職員室の前で見た美人の女の人がこちらにやってくる。警部って呼んでるってことは…。そんなあたしの疑問に気付いたのかカイカンさんは「あの人はムーン巡査、私の部下です」と言い、立てていた指を下ろすと椅子から腰を上げた。ムーンって…それも名字なの?そんなまさかね。
「やあムーン、よくここがわかったね」
「警部の行きそうな所はおおよそ想像がつきますから」
ムーンさんはそう言いながらあたしたちの前まで来る。近くで見るとやっぱり美人、いいなあ…。この人が刑事…、ドラマの中から抜け出してきたみたい。まあカイカンさんはカイカンさんでアニメか何かに出て競うだけど。ムーンさんがこっちを見たのであたしも立ち上がって会釈する。
「3年生の赤井このみです、刑事さんとお話してました。ごめんなさい、お仕事中に…」
「いえいえ、うちの警部の面倒を見て頂いてこちらこそありがとうございました」
微笑むムーンさんは笑った顔も綺麗。隣でカイカンさんも「おいおいムーン、私は子供か」と笑ってる。
「大人だったらちゃんと仕事しましょう。もう用事は済みましたから行きますよ」
「そうかい?じゃあ行こう。では赤井さん、失礼しますね」
軽く手を振ると、カイカンさんはそのままムーンさんと共に去っていった。二人の後姿を見ながらあたしは考えていた。
…生きてる世界が変わったみたい。カイカンさんにムーンさん。これまでの世界にはあんな人たちいなかった。もしかしたら髪を赤くしたことであたしは平行世界に転移したのかもしれない。
な~んてね、ライトノベルじゃあるまいしそんなことあるわけないか。ひょっとしてこれが世に言う中2病ってやつ?もう中3だけどさ。
■第一章② ~ムーン~
1
私の名前はムーン、警視庁捜査一課の女刑事である。もちろんこんなふざけた名前の日本人がいるはずもなく、ムーンというのは職場上のニックネームのようなものだ。これは一般の方はあまりご存じないのだが、警視庁捜査一課はミットと呼ばれるいくつかのチームに分かれており、私の所属するミットではお互いをニックネームで呼び合うのが古くからの慣例らしい。ちなみに私の上司はカイカンなる私以上に奇異なニックネームで呼ばれている。
そう、今私が運転する車の助手席でおしゃぶり昆布をくわえているのがそのカイカン警部だ。服装も髪型も嗜好も…ニックネームに引けを取らないほどにわけがわからない自他共に認めるド変人。
「いやあ、中学時代が懐かしくなっちゃったよ」
低い声がそんなことを言っている。
まあそもそもあの中学にこの人を連れて行ったのは私なのだが。というのも、交通課に勤務する友人から受けた依頼…今朝、パトロールをしていた彼女は登校中の女子生徒を撮影している不審な男を逮捕、他にも迷惑行為を働いているかもしれないから一度学校に確認しておいてほしいとのことだった。彼女には色々と借りもあるので私は引き受け、それにこの上司もくっついてきてしまったというわけだ。
「先生方に伺いましたが、今のところ特に生徒さんたちに直接的な被害は出てないみたいです」
「それはよかった、最近は物騒だからどこに不審者がいるかわからないからね」
あなたも知らない人から見たら立派な不審者ですって。さっきも赤毛の女の子と並んで話してたけど、あの光景だって見方によってはかなり危ない。
「先ほどの…赤井さんでしたっけ、彼女はあそこで何を?」
「ああ、どうやらあの場所は彼女の秘密基地らしい。それで放課後に一人でふらっと立ち寄ったんだって」
「そうですか。体育館の裏にあんな髪の少女だから私てっきり…」
「私も最初はそう思ったよ」
そう言って警部はくわえていた昆布を指に挟む。
「でもあの辺りに吸い殻は落ちていなかったし、彼女はそんな子じゃなかった。いや、きっとほとんどの子供は私たちが思っているよりずっといい子なんだろうな。赤井さんと話してそう感じたよ。髪を赤くした理由もなんとなく共感できたしね」
「理由って何です?」
「フフフ…君にもあったでしょ?パチンだよ、パチン」
またわけのわからないことを…まあ確かに彼女は悪い子じゃなさそうだった。人を見かけで判断してはならない…警部が言うと説得力があるな。あれ、いや逆か。この人は中身も変人なんだから。
「警部、私のために寄り道して頂いてありがとうございました」
「いやいや、交通課とは持ちつ持たれつだからね。それにこっちの捜査が行き詰まってたからちょうどいい気分転換になった。でもそろそろこっちを解決しないとね」
そう、そのとおりだ。私たちのミットが現在担当しているのは先日発生した殺人事件。捜査を開始してすでに三日目だが未だに容疑者はおろか犯人像も絞り込めていない。捜査会議を終えて警部と私は再び現場検証を行なうため警視庁を出てきた、その途中であの中学校に立ち寄ったのだ。
「では警部、このまま事件現場に直行しますね、近くですから」
そう言って私はアクセルを踏み込んだ。
*
ハンドルを切りながら頭の中で整理する。…事件のあらましはこうだ。
現場はシステム開発を主業務とする『セブンファイブフォー』という会社。会社といっても社員は社長を含めて三名という小さな会社で、もともと社長の個人事業だったのが最近ようやく人を雇える規模になったというもの。被害者はまさにその社長である名越達彦(なごし・たつひこ)、社長といってもまだ若い26歳の男性だ。死因は背中のほぼ中心を一突きされたことによる失血死、凶器は現場にあった果物ナイフでそのまま背中に刺さっていた。第一発見者は社員の藤川聡(ふじかわ・さとし)。一昨日の朝、つまりは月曜日の朝に出勤しオフィスで血を流して倒れている社長を発見、驚いて腰を抜かしているところにもう一人の社員である熊野大介(くまの・だいすけ)も出勤してきて二人で119番と110番をしたという流れだ。
司法解剖の結果、死亡推定時刻は金曜日の午後5時から翌土曜日の午前5時までの約12時間とされた。しかしその後の捜査で犯行推定時刻はさらに狭めることができた。
金曜日は午後4時半には終業とし、社長と二人の社員は三人で忘年会に向かった。居酒屋で一杯目のビールを飲んでいたところで名越のスマートフォンが鳴り、クライアントから緊急の問い合わせが入り彼だけがオフィスに戻った。立ち去る際に「作業が長引くかもしれないから二人で適当に飲んで解散して」と言い残したため、藤川と熊野は社長が戻ってこなくてもさほど気にせずそのまま飲み続け日付が変わった頃にようやく帰路に就いた。名越が店を出たのが5時半過ぎ、そのままオフィスに直行したとすれば6時には現場に戻っていたことになる。彼に作業を依頼したクライアントはなかなか返事が来ないため夜10時以降何度か電話をしているが名越がそれに出ることはなかった。社員の証言ではそのクライアントは会社にとって大切なお得意様であり社長が電話を無視することは有り得ないという。
以上を踏まえて考察すると、被害者は金曜日の午後6時から10時の間に殺害された可能性が高いということになる。
さらに遺体が発見された際、衣服は乱れオフィスはかなり散らかっていた。つまり犯人と被害者は現場で格闘した可能性が高い。加えてオフィスにあった金庫も開いており現金がなくなっていたことから、犯人の動機は金銭であったと考えられる。虚しい話であるが、物盗りによる犯行と見るのが最も妥当な現場であった。
しかしである。警部と捜査を進めるうちにそう単純な話でもなくなってきたのだ。
2
『セブンファイブフォー』のオフィスはビジネスビルの1階に入っていた。駐車場に車を停め、警部と私は未だに現場保存されているその部屋に足を踏み入れる。
「やっぱり、鍵をこじ開けた痕跡はないよね」
出入り口のドアの鍵穴を見ながら警部が言った。そう、物盗りの犯行と考えた際にまず生じるのがこの疑問だった。
「ええ、鑑識さんが調べましたが不審な傷などは一切ありません。もちろん針金とかで開くような物じゃありませんから、開け閉めするには正規の鍵を使うしかありませんね」
第一発見者の藤川が出勤した時、このドアは施錠されていなかった。つまり犯人は開けっ放しで立ち去ったことになる。しかし逃げる時はそれでいいとしても入る時はそうはいかない。犯人が物盗りなら侵入には必ず鍵が必要なのだ。
捜査の結果、鍵を所持していたのは社長と二人の社員のみ。これまで紛失もしていない。社員用の鍵は普段はデスクの上に置いていたらしいので、つまり外部犯とするならば犯人はこっそりそれを持ち出して合鍵を造っていたことになる。…部外者にそんなことが可能だろうか?
「犯人は合鍵なんか使わずに入った、例えば被害者の名越さん自身に招き入れてもらったとしたらどうだろう?」
「鍵を開けてもらって中に入る泥棒がいますかね?それに金庫の暗証番号を犯人はどうして知っていたのかが問題です、社員の二人も聞かされていなかったそうですから」
「名越さんを脅して金庫を開けさせたのかもしれない。そう、つまりは泥棒ではなく押し込み強盗だったんだ」
「強盗だとすると凶器が現場に会った果物ナイフというのは不自然ではありませんか?それに被害者がオフィスにいたのは偶然です、クライアントに言われて職場に戻ったわけですから。たまたまいた被害者を脅して金庫を開けさせる、というのは強盗の計画として無理があると思いますが」
すでに何度も検討した話だった。警部は「だよね」と呟くとドアから離れ室内に向き直る。三つのデスクとパソコン、コピー機、小さな応接テーブルとソファが所狭しとひしめき合うオフィス。全体的にこじんまりとしているが、テレビだけが大画面でやや不釣合いだった。床には書類と文房具が散乱し、遺体があった位置には白線で人型が描かれている。
「つまりムーン、外部犯だとすると犯人は泥棒。留守のオフィスで金庫をあさっていたところに被害者が戻ってきて鉢合わせした…と考えるのが一番妥当かな」
警部は右手の人差し指を立て、私の返事を待たずに言葉を続ける。
「被害者と犯人はそのままもみ合いになった。そして逃げようとして背中を向けた被害者を焦った犯人がその場に会った果物ナイフで刺した…」
それは遺体がドアに頭を向けて前のめりに倒れていたことから導かれた結論だった。凶器の果物ナイフは昼休みに熊野が実家から届いたフルーツをみんなに振る舞う際に使用した物で、そのままテーブルの上に置かれていたという。
こうして考えると、合鍵と金庫の暗証番号の謎は残るものの現場の状況は物盗りの犯行を物語っている…ある一点を除いては。
「さて、やっぱり最大の問題は…これか」
人型の白線の近くにしゃがむ警部。そう、この事件の謎はこれ、遺体は右腕を前に伸ばすような体勢で倒れており、そして右手の先には血文字が残されていたのだ。遺体が運び出された今も、その血文字は白線が再現した右手の位置にしっかり残されている。被害者は失血死していたものの厚手のセーターを着ていたこともあって出血は衣類の背中部分にとどまり、血文字以外に床を汚している血痕はない。
「ダイイング・メッセージ」
警部の低い声が床に響く。そう、不謹慎な言い方になってしまうが、まるで絵に描いたようなダイイング・メッセージを被害者は残していたのだ…それこそテレビのミステリードラマのような代物を。
私が警部の下についてもう何年にもなるが、これまでダイイング・メッセージなんてものにはほとんどお目にかかったことがない。現実にはそう都合よくダイイング・メッセージなんて残せないのだ。そしてそれが暗号になっているなんてことはまずない。
そもそもどうしてダイイング・メッセージを暗号にするのか?ミステリードラマではよく「そのまま書いたら犯人に隠滅されてしまうから」と説明される。しかしもし私が犯人だったら、被害者が書き残した物は暗号だろうが何だろうがとにかく全部消してしまうと思うが。それに大前提として品詞の人間が瞬時に暗号をひらめくというのも無理がある。
あるいは犯人が自分への疑いを逸らすために偽りのダイイング・メッセージを残すというパターンもある。しかしその場合は暗号にする必然性はない。誰も解いてくれなかったら意味がなくなるのだから。
…とまあそんなわけで、現実の事件現場では暗号のダイイング・メッセージが残されているなんてことはまず有り得ない。しかし、そのまず有り得ないことがこの事件では起きてしまっている。
「…アイウエオ、確かに片仮名でアイウエオと書かれているね」
警部が読み上げた。そう、被害者の名越社長はアイウエオと書き残しているのだ。一昨日、通報を受けて初めてこの現場に入った時、正直何かの冗談かと思ってしまった。被害者が刺され自分の血でアイウエオと書き残している構図は、安っぽいミステリードラマにしか見えなかった。しかしこれは現実の事件である。名越社長は最後の力を振り絞ってこれを残した…そのメッセージはこちらも全力で読み取らなければならない。
アイウエオ、アイウエオ、アイウエオ…。
アイウエオ、アイウエオ、アイウエオ…?
「アイウエオ…アイウエオ…」
警部もそうくり返し、口に昆布をくわえる。冗談みたいな格好をした刑事が冗談みたいな暗号を解いている。
アホか、ふざけるな!…と叫びたくもなるがこれは冗談ではないのだ。そしてこの
暗号こそがこの事件を単純な物盗りの千から脱輪させているに他ならない。
*
結局日が暮れるまで現場で考えたが、アイウエオが他の何かに形を変えることはなかった。警部もあきらめたように立ち上がり、背伸びをして昆布をコートのポケットに戻した。
「ダメだね。またゆっくり考えてみるよ。ここはどうも落ち着かない…」
警部はそう言って窓の方を見る。このオフィスの壁の一部は歩道に面した大きなはめ殺しのガラス窓となっている。そんなに人通りが多い道ではないが、それでも行き買う人々の全身が窓を隔ててよく見えた。
「警部、あれはマジックミラーですからこちらは見えてませんよ。そうじゃなかったらとっくに現場保存のブルーシートをかけてます」
「わかってるけどさ…まるで展示会場で現場検証のデモンストレーションをしてる気分だよ」
ダイイング・メッセージがアイウエオではそれも仕方ないかもしれない。
「警部、これからどうされます?」
「ひとまず警視庁に戻ろう。確か8時から藤川さんと熊野さんに改めて話を聞くんだったね。実はムーン、もう一人追加してほしい人がいるんだけど…」
「事件の夜に名越さんに電話をかけたクライアントですね。ご足労頂くよう連絡してあります」
私がそう答えると、警部は「さっすがムーン、お見事!」と言い嬉しそうにオフィスを出ていった。
■第二章① ~赤井このみ~
午後7時、晩ごはんの前にまたママと言い争いになっちゃった。だってあんまりにもこの髪のことをひどく言うからさ、こっちも言いたくないことまで言っちゃうよ。どうしてそんなに髪を戻せ戻せって言うの?あたしは気に入ってるんだよ?別に悪い子になったわけじゃないんだよ?
もう勝手にしなさいってママは自分の部屋にこもった。だからあたしは一人で晩ごはん。フンだ、どうせママにはわかんないよ。ママもチャビンもあたしのことなんか信じてないんだ、面倒かけるだけの存在だって思ってるんだ。
せっかく新しい世界が始まったのに…。そういえば今日の刑事さん、面白かったなあ。
そこで思い付いてあたしはスプーンを置くとすみれにメールする。
『ねえ、すみれには秘密基地ある?』
一分くらいで返事が来た。
『何それ?』
■第二章② ~ムーン~
1
事情聴取まで少し時間があったので私は警部と一度別れて交通課に顔を出す。案の定彼女はまだデスクに残っていた。
「美佳子、お疲れ」
私に気付くと彼女も「おうおう、お疲れ」と席を立つ。制服に身を包みスラリと背が高く長い髪を後ろでまとめたその姿はまさしく婦人警官。彼女が警視庁での同僚であり私の数少ない友人でもある氏家美佳子。
「今日は悪かったね、変なこと頼んじゃって。やっぱり征服警官が中学校に行くのは生徒を動揺させちゃうかなと思ってさ」
「ううん、ちょうど現場の近くだったから気にしないで」
「でも後からよく考えたら美人刑事を送り込む方がまずかったかなと思って。ほら、特に思春期男子諸君には刺激が強過ぎて」
「美佳子ったら何言ってんのよ」
そんなお決まりのやりとり。刑事という殺伐とした仕事の中で彼女の存在はいつも渇きそうになる心に潤いをくれる。
「電話でも言ったけど、今のところ生徒さんたちが危ない目に遭ってるとかはないみたい。一応先生たちも気を付けてくれるってさ。でも怖いよね、盗撮なんて」
「まったく、世の中どうなってんだか」
美佳子は苦々しくそう言うと、今朝の詳細を教えてくれた。ミニパトで駐車違反を取り締まっていた時、歩道橋の上から登校中の生徒を撮影する男を発見。怪しんだ美佳子が声をかけようと近付くと男は逃げ出したため追いかけ、追いついたところで相手が殴りかかってきたので美佳子の一本背負いが決まってお縄となったらしい。
「一体どんな人なの?通勤中のサラリーマンとか?」
「いやいや、30歳でさ、さっき聞いたらコンビニとか電気屋とかで働いてたらしいんだけど長続きしなくて、最近は仕事も見つからなかったって」
「それでストレス溜まってイライラしてたのかな、その人」
美佳子の柔道は中学生の頃からの筋金入りだ。それを喰らわされた男の姿が少しだけ哀れに思えた。まあ自業自得なので同情はしないけど。
「イライラしててもやっちゃいかんでしょ。一応は公務執行妨害で逮捕したけど…まあおそらく送検せずに釈放って感じかな。撮影に使ってたスマートフォンも調べたけど、道を歩く女子中学生がたくさん写ってただけでいやらしい物じゃなかったから」
唇を噛む美佳子。仮にその男に猥褻な意図があったとしてもそれを証明するのは難しい…この仕事をしている人間なら何度も歯痒さを覚える法の限界というやつだ。あとは無断撮影を肖像権の侵害で訴えるしかないが、それはもっと難しい。
「そんなわけで一晩お灸を据えて明日釈放。前科もないし今回はそれでしょうがないね。まあしばらくは中学校周辺のパトロールをするよ」
交通課の業務を逸脱することに全く面倒を感じない…サバサバしてるのに正義感と優しさが溢れている彼女。私は親愛を込めて「さっすが美佳子」と告げた。
その後も少し雑談をしてから私はそろそろ戻ると伝える。美佳子も腕まくりをして「よっしゃ、説教の続きじゃ」と取調室に向かった。そんな気持ちの良い後ろ姿を見送りながら、私は交通課を後にする。
2
午後8時、警部と合流し藤川と熊野の事情聴取を開始する。本人たちの希望で二人一緒にということになった。取調室の机を挟み二対二で席に着くと、「わざわざお越し頂いてすいません」と警部が切り出した。
「社長のためだから協力はしますけどね、でも刑事さん、もう知ってることは全部お話しましたよ」
藤川が答える。二人とも名越とは同世代の男性、藤川は女性的な顔立ちをしたやせ型、隣の熊野は焦げ茶色のくせっ毛と黒縁メガネが印象的。彼らを聴取するのはこれで賞味三回目なのでうんざりするのも無理はない。捜査がそれだけ昏迷していることは彼らにも伝わっているだろう。
「すいません、こちらとしても雲を掴むような状態でして」
警部があっけらかんと言う。そして事件当夜、つまり先週の金曜日のことを改めて確認していく。名越にいつもと変わった様子はなかったこと、忘年会のためにいつもより早く挙がって三人で居酒屋に行ったこと、オフィスを出る時に間違いなく出入り口のドアは施錠したこと、飲んでいたら5時半頃にクライアントからの電話が鳴り名越だけがオフィスに戻ったこと、二人は深夜1時頃までそのままそこで飲んでいたことなどが口を揃えて語られた。
「随分長い時間お店にいらっしゃったんですね」
「ええ、二人とも飲むのは好きなんで。それに一応忘年会ですしね。社長が抜けたことで余計に盛り上がっちゃって…ほら、上司の悪口とか言いだすと止まらなくなるじゃないですか」
そう言って藤川はちらりとこちらを見る。同意したいが警部の隣で大いに頷くわけにもいかない。
「名越さんに対してはご不満もあったわけですか」
「そりゃありますよ。給料安いしケチだし、あの時もせめて少しお金を置いていってくれればいいのにきっちり自分の飲んだ分だけ払って行っちゃうんですから…なあ、熊野」
「そうだなあ、確かにケチだね。窓がマジックミラーだからってカーテンも付けないし、地デジ対応のテレビだって買ったの最近だし。アナログ放送が終わって何年経ってるんだって話だよ。まあ…もともと一人で始めた会社だから節約が身に付いてるんだろうけどさ」
「それまでオフィスにはテレビがなかったんですか?」
「いえ、一応昔ながらのブラウン管のやつがありましたよ。俺たちが雇われたのが今年の春だから、その頃からようやく経営に余裕が出たんでしょうね。それで夏にやっとテレビを買い換えたんです」
熊野がそう言って鼻で笑う。オフィスに不釣合いなあの大画面テレビは名越にとって成功の証だったわけか…。続いて藤川が身を乗り出した。
「だからって刑事さん、俺たちが社長をどうこうしたなんて思わないでくださいよ。ケチでしたけど悪い人じゃないし、フリーターだった俺たちを正社員で雇ってくれて感謝はしてるんです。俺たちは金庫の暗証番号だって知らないですし…社長は金庫を開ける時は周囲の視線をすごく気にしてましたから盗み見もできません」
警部は感情なく「そうですか」と返す。確かに外部犯でないとしたら最有力容疑者はこの二人だ。鍵を持っているからオフィスへの出入りは自由だし、暗証番号も実は知っていたのかもしれない。
しかしそうなると矛盾が生じる。彼らが金庫のお金を盗もうとしたのならいつでもできたはずだ。わざわざ名越が残業しているところに押し入る必要はない。それに犯行推定時刻にはずっと居酒屋にいたというアリバイもある。店にも確認したがトイレなどで席を立つことはあってもせいぜい10分程度、仮にバイクや車を用いたとしてもオフィスまで往復する時間はなかった。誰かを雇ってやらせたという可能性もあるが、やはり名越がオフィスに戻ることになった時点で計画を中止したはずだ。
「ご安心ください、お二人には鉄壁のアリバイがあります」
警部がそう言うと熊野が「鉄壁のアリバイなんて…まるで推理小説みたいな言い方ですね」とまた鼻で笑う。
「不謹慎ですいません。推理小説といえば…アイウエオのダイイング・メッセージについては何か思い当たりませんか?」
「社長が書いた血文字ですよね。考えてますけど全然わかりません」
と、藤川。この二人は遺体を発見した時に被害者の残した文字を見ているのである。第一発見者の藤川が実はあの血文字を書いた、あるいは加筆したという可能性も以前に検討したが、血液の渇き具合からすぐに却下された。アイウエオの文字はかすれることもなく十分な血液で被害者自身の指によって書き残された…それは鑑識の見解からも疑いようのない事実なのである。
「お仕事でもプライベートでも、名越さんのお知り合いでアイウエオに関連した人はいませんか?」
警部がさらに尋ねる。
「ピンときませんね、プライベートはほとんど知りませんし。なんならブログに公開して訊いてみましょうか?全国のミステリーマニアが考えてくれますよ」
「それはやめてください」
私が語気を強めて言うと、藤川は「冗談ですって」と肩をすくめた。この三日間、名越の手帳やパソコン、自宅の私物なども含めて調べたがアイウエオに関連した情報は出ていない。独身であり、親戚付き合いもあまりしていないようだった。実家の両親の話では会社を立ち上げた五年前から一人我武者羅に頑張っていたという。
アイウエオ、アイウエオ、アイウエオ…考えれば考えるほどわからない。
「ねえ刑事さん、金庫から金が盗まれたってことは犯人は泥棒ですよね。だとすれば外部犯だ。そもそも社長が犯人の名前を知っているはずないです。となるとアイウエオは何か犯人の特徴を表しているんじゃないですか?」
熊野が指摘する。おそらくとっくに考えていたことであるが警部は「ナルホド」と頷いた。
「待て熊野、ダイイング・メッセージが犯人のこととは限らないぞ。もっと別の大切なこと…例えば俺たちへの遺言とかかもしれない。会社を頼んだぞ、みたいな」
「アイウエオをどう解釈したらそうなるんだよ?」
「だから例えばだって」
「そもそも暗号のダイイング・メッセージなんてナンセンスだ。あれは暗号じゃない、社長は普通にメッセージを書いたのにこっちの知識が足りなくて意味がわからないだけなんだよ。そうだ、アイウエオに見えるけどあれは古代象形文字かもしれない」
漫才のような二人のやりとりを警部が「まあまあ」と仲裁する。そしてその後もダイイング・メッセージ談義が催されたが実のある話にはならないまま彼らの聴取は終了となった。
*
午後9時、続いて事件当夜名越を残業に追いやったクライアントへの聴取が始まった。名前は高松光良(たかまつ・みつよし)、入室時からイライラが伝わってくる神経質そうな中年の男性。腰を下ろすやいなや警部の挨拶よりも先に彼は話し始めた。
「早いとこ終わりにしてくださいよ、刑事さん。こっちは忙しくて死にそうなんだから」
電話では何度か聴いていたがかなり早口で甲高い声だった。彼は警部の風貌にさらに苛立ちを強めているように見える。
「確かに先週の金曜日、名越くんに電話したのは僕ですよ。彼に開発してもらった会計システムがおかしくなっちゃったからどうにかしてくれって頼んだんです。すぐに調べて折り返すっていうのにいつまでたっても連絡がないから、こっちも頭にきてまた電話しました。でも何回かけても彼が出なくて…会社まで押しかけたい気分でしたよ!」
「でもあなたはそうしなかった」
「そりゃそうでしょう、静岡にいたんだから。仕方ないから自分らでなんとか修理して決済に間に合わせましたよ。わかりますか?三日間ほぼ徹夜です」
そう、高松は金曜日から月曜日まで静岡県の支社に出張していたのだ。同僚の証言も得られており、途中で抜け出して東京に往復する余裕はなかった。つまり、彼にもまた鉄壁のアリバイがあることになる。
「名越さんとは長いんですか?」
「彼が会社を始めた頃から少しずつ仕事をお願いするようになったんです。しっかりやってくれるからだんだん大きな仕事も頼むようになりましたね。金曜日の夜みたいに無責任に連絡が途絶えるなんてことはこれまでなかったから…少し心配はしてたんです。でもまさか殺されていたなんて」
高松は一瞬淋しそうな顔を見せたがすぐに真顔に戻った。通話記録では彼が名越に電話してシステムチェックを依頼したのが午後5時32分。その後しびれを切らして電話したのが午後10時ジャスト、以降深夜0時まで五回ほどかけているがいずれにも名越は応答していない。やはり当夜10時までには殺害されていたと考えるべきだろう。
「これまでに名越さんのオフィスを訪れたことはありますか?」
警部が切り口を変えた質問をする。高松は少し考えてから答えた。
「確か…一年くらい前に一回だけありましたかね。一つ大きな仕事を任せたくて…当時はまだ社員は名越くんだけでした。そういえば古めかしいブラウン管テレビが置いてあったなあ、まだ買い換える余裕がないとか言ってましたよ。それが今じゃ社員を二人も雇ってるんだからたいしたもんです」
気付けば彼の口調は穏やかになってきていた。目をかけていた青年の死にこの人もこの人なりに思いをはせているのだろうか。
「ナルホド。私の知り合いにも名越さんのような仕事をしている人がいますが、個人事業のシステムエンジニアは自分からクライアントの会社を回るのが普通だと言ってました。クライアントの方からオフィスを訪ねるのは珍しいことなんですね」
警部の言葉を聞きながら頭の中で考える。オフィスには普段からクライアントも出入りしていなかった…となるとますますわからない、一体何者が金庫を狙って忍び込んだのか?
その後も警部はいくつかの質問をしたが特に新たな情報は出てこず、高松は忙しそうに取調室から帰っていった。
■第二章③ ~?~
警察は…まさか感付いちゃいないだろうな。今のところそんな様子はないが…。
でもあいつが警察に余計なことを言いやがったらまずい。
早く、早くなんとかしなければ…。
■第三章① ~赤井このみ~
「おっはろー、このみ!」
木曜日の朝、いつもの通学路を歩いていると後ろからすみれが元気な声を投げてきた。
「やっぱ目立つよ、その頭。黒い人の波の中に赤い実がプカプカ浮いてるみたい」
「もう、何よそれ」
「褒めてるんだよ、とっても可愛いから。こりゃ男子もほっとかないな。赤井このみだから赤い髪、うん、思い切ってうちも髪の毛すみれ色にしてみようかな」
すみれはあたしの隣に並んでいつもの笑顔を見せる。なんだかほっとする。朝ごはんの時もママとはほとんど会話できなかったから。
「別に男子なんてどうでもいいよ、あたしがしたくてしてるんだから」
「そうなの?そういえば昨日のメールはどういう意味?秘密基地がどうこうって」
「ごめんごめん、気にしないで」
「変なの。あ、それよりそれより、山岡重司の新曲聴いた?かなりいい感じでさあ…」
そんなこと言いながら歩いてたら交差点の所に誰かが立ってるのが見えた。ゲゲ、チャビンじゃん。やば、目が合った。
「このみこのみ、ほら見て、チャビンがあんたを睨んでる」
「もう最悪、なんで朝からあんなとこに突っ立ってんの?」
あたしが無理矢理目を逸らしながら言うと、すみれは思い出したように返した。
「そういえば知ってる?後輩から聞いたんだけどさ、この近くで事件があったんだって」
「あれでしょ、会社の社長さんが殺されたっていう…ニュースで見たよ。っていうかこの前も話さなかったっけ?」
「違う違う、それじゃなくて昨日の話だよ。昨日の朝さ、なんか不審者がこの近くで逮捕されたんだって。通学中の生徒を撮影してたとかで婦人警官の人が捕まえたって…何人か現場を見た子がいたんだって」
「うわあ気持ち悪い、何それ?」
痴漢とか盗撮とか不倫とか、ニュースでも毎週のようにそんな記事を目にするけどその度に思う…男って、ていうか大人ってバカ?真面目に生きろとかいじめはするなとか偉そうに言ってるくせに、自分たちの方が汚いこといっぱいいやってさ。
「このみ、顔が恐いよ」
「いや、なんて言うか…愚かだなって思って」
「キャハハ、そうだね、愚か愚か。まあとにかくチャビンもそれでうちらの通学を見張ってんだよ」
チャビンは腰に両手を当て道行く生徒たちを目で追っている。ゲゲゲ、また目が合った。もうなんでそんなにあたしを目の敵にすんのよ!ねえ、あたしがなんかあんたに迷惑かけた?
顔を背けてチャビンの前を通る。見張ってくれるのはありがたいけどこれじゃあ逆効果だよ。あ、もしかしたら昨日のカイカンさんとムーンさんもそのことで学校に来てたのかなあ。
「はいはいこのみ、もう通り過ぎたよ」
すみれがポンポン肩を叩く。無意識にあたしは息を止めていた。
「ハア、今日はチャビンに呼び出されても絶対行かないから」
「残念でした、今日は午後からチャビンの数学だもん。どっちにしてもそこでお目にかかりま~す、キャハハ」
すみれが笑う。そうか…今日は数学の授業があったんだった。校門をくぐりながらあたしは溜め息を吐く。髪の色を変えて新しい世界が始まったはずなのに。
…そうだ、どうせならあれをやってみようか。前から一度やってみたかったあれ。
「今度は目を輝かせてどうしたの、このみ?」
「すみれ、見ててね。今日はほんとに反乱軍のリーダーになっちゃうから」
■第三章② ~ムーン~
昼食を終えて警視庁に戻ると、正面玄関の所で美佳子が誰かを見送っていた。相手は深々と頭を下げている。トレーナーにジーンズの大柄な男、もしかして…。
「それじゃあ淀山さん、これからは気を付けてくださいね」
「すいませんでした」
彼は泣きそうな声でそう言うと足早にその場を立ち去り、すれ違いざまに私をちらりと見た。美佳子もこちらに気付く。
「やっほー美人刑事、お疲れ」
「お疲れ美佳子、今のが昨日言ってた人?」
「そうなのよ。結局送検なしで釈放、調書だけ取っておしまい。まあ相当説教はしたから少しは反省してくれてればいいけど」
美佳子はそおう言って伸びをすると、「それよりそっちの捜査はどう?」と話題を転換した。
「システム開発の社長の殺人事件を担当してるんでしょ?解決できそう?」
「今のところは足踏み状態かな。単純な物盗りなようでそうでもない感じ喪あるし…」
「そっか、まあ根詰め過ぎないようにね。あたしは今から昼飯行くわ」
小さなハイタッチをして美佳子と別れる。被害者が殺害されたのが先週金曜日、遺体が発見されて捜査が開始されたのが月曜日、そして今日が木曜日だからもうじき事件発生から一週間が経過する。そろそろ目鼻がついてほしいところだ。
*
いつもの部屋に戻ると、警部がおしゃぶり昆布をくわえたままホワイトボードを見つめて唸っていた。そこにはアイウエオと大きく記されている。奥の机では私たちのミットの長であるビン警視がいつもどおり書類に目を通していた。
「お疲れ様です、ただ今戻りました」
そう言って自分のデスクに座る。警部は無言のまま思考を続け、ビンさんは小さく「お帰り」と呟いた。会話が始まる様子もないので私も手帳を開いて事件のことを整理する。
はたして犯人は何者だろうか。
金庫のお金を目当てに忍び込んだ泥棒が偶然戻ってきた被害者を殺害してしまったのか?それとも被害者が残業していることを知っていた誰かが最初から被害者を襲うつもりで押し入ったのか?前者だとすると入り口の合鍵と金庫の暗証番号をどうやって犯人が手に入れたのかが問題だ。後者だとすると凶器が現場に合った果物ナイフというのはおかしい。それに被害者が残業していたのは偶然なのでそこを狙って押し入るのも無理がある。
そしていずれの場合にせよダイイング・メッセージの意味がさっぱりわからない。死の間際、被害者はアイウエオで一体何を伝えようとしたのか?
ちらとホワイトボードの方を見ると、警部は立てた右手の人差し指に前髪をクルクル巻き付けていた。考え事をする時の癖だ。
…ピルル、ピルル、ピルル。
声をかけようとしたところでデスク中央の電話が鳴った。ビンさんは「はいもしもし」と優しい語り口でそれに出る。そして短い言葉を交わした後で受話器を口から離してこちらに言った。
「カイカン、それにムーン、赤井このみってお嬢さんを知ってるか?その子が君たちに相談があると警視庁に電話してきてるそうだ」
警部の指の動きが止まった。
■第四章① ~赤井このみ~
もうほんとに最悪、最悪、最悪!なんでこんなことになっちゃうのよ?あたしが万引きなんかするわけないのに、店長さんはあたしを犯人だと決め付けてる。せっかく人生初のサボタージュを決行してのんびりショッピングと思ったのに。
「正直に白状すれば今回は許してあげてもいいんだよ」
店長さんがまた同じことを言った。
「ですから、あたしは盗んでないんです。ちゃんと調べてもらえばわかります」
「じゃあ持ち物をチェックしようか?その征服のポケットの中も」
「嫌です、そんなの痴漢です」
そう返すと店長さんは呆れたように顔をそむけて頭をかく。あたしの隣で男の子は不安そうに視線を泳がせてる。壁の時計は午後2時…こんなんだったらチャビンの授業を受けてた方がましだったかな。この場にまた気まずい沈黙が流れる。
一体どうなっちゃうんだろ?まさかほんとにこのまま犯人にされちゃうなんてことはないよね?学校とか家にも連絡されちゃうのかな、そうしたらチャビンとかママにまたガミガミ言われるなあ。何なのよ、髪を赤くしてからろくなことがないじゃない。
思わずまた溜め息…その瞬間、入り口からあの低い声が入ってきた。
「どうもお待たせしました」
■第四章② ~ムーン~
1
警部に続いて私もその文房具店に入る。警部の風貌に店長は明らかな困惑と疑惑を浮かべていたので、いつものように私が警察手帳を示して身分を説明する。レジの所には電話してきた赤井このみ、そして彼女より少し幼い少年がいた。彼女が征服姿なのに対し彼は私服だった。
「警視庁の刑事さんですか…僕としてはあまり大袈裟にしたくはなかったんですがね。この子が知り合いの警察に相談するなんて言うものですから」
店長がそう言うと、このみは真剣な眼差しで一歩前に出た。
「急に電話しちゃってごめんなさいカイカンさん、それに…ムーンさん。でも他に方法が浮かばなくて…どうしていいかわからなくて…ほんとにごめんなさい。でもあたし、ほんとに万引きなんかしてないんです」
そう、彼女が私たちにSOSしたのはその濡れ衣についてだ。「警視庁のカイカンさんかムーンさんをお願いします」なんて110番があった時にはちょっと驚いたが、まあそんな無鉄砲さはいかにも中学生らしい。私たちのような名前の警察官が他にいるはずないのであっさりミットに連絡がつき、ここに来るに至ったわけである。本来は捜査一課の仕事ではないのだが…。
「いえいえ構いませんよ赤井さん、これも何かの縁ですから。ではではみなさん、詳しく事情をお伺いしてよろしいですか?」
まあ上司がこう言っているのでよしとしよう。
*
警部は相手を労りながら話を引き出すいつもの手並みで手際よく情報を集めていった。それをまとめるとおおよそこんな感じだ。
この店は主に登下校中の小中学生をターゲットにした個人商店の文房具店。50代の店長が一人で切り盛りしており、十畳ほどの店内は棚などでいくつか死角はあるものの防犯カメラは設置されていない。店長は入り口横のレジにいて、時々店内を回っては商品の整理や掃除をしている。朝と放課後は生徒たちで賑わうが、昼間は近所のお年寄りがたまに来店する程度。まあコンビニが台頭する昨今ではこのような店を維持するのは大変なことだろう。
それが本日午後1時過ぎ、珍しく若いお客が二名もいる状況で万引きが発覚した。客の一人が赤井このみ、そしてもう一人が彼女の隣でずっとおどおどしている青島という少年。このみとは別の中学校に通う1年生で、彼の中学は本日は開校記念日で休みだったらしい。
「正午に店内を見回った時は確かにその消しゴムはあったんです。その後でこの子たちが来店して、1時過ぎにもう一度見回ったらなくなってました。そのタイミングで女の子が店を出ようとしていたんで呼び止めました。その時間他にお客さんはいませんでしたから、彼女を疑うのも当然でしょう」
店長はこのみを厳しい目で見ながらそう主張した。彼女は「そのタイミングって…たまたま別のお店に行こうと思って出ただけですよ」と反論する。
「そうかねえ、だいたい昼間から中学生が街をうろついてる時点でおかしいじゃないか。授業さぼって…そんな頭して…それじゃ疑われても仕方ない」
「この髪の何がいけないんですか?」
「まあまあ赤井さん、落ち着いて。店長さんも決めつけはよくないですよ」
警部が両者をなだめる。そしてずっと黙っている少年に視線を向けた。
「青島くん、その時君はどうしてたの?」
少年はしばらく黙って考えてから、怯えた目で「まだ店にいました。ノートとか見てました」と答えた。私服なせいもあるが、小柄なため小学生にも見えそうな少年だ。警部は「そうですか」とだけ返し、また店長に向き直る。
「しかし店長さん、小さなお店とはいえそれなりに商品は並んでいますよね。正午に確認したとおっしゃいましたが…そんな正確に個数まで記憶できるものでしょうか?」
「なくなったかどうかくらいわかりますよ」
小さなお店という表現が癇に障ったのか、店長はむっとした様子で説明した。盗まれたとされる消しゴムは人気商品であり、最近も何度か万引き被害に遭ったため特に注意していたという。彼はレジからは死角になるその棚に警部と私を案内した。
「ほら見てくださいよ、1個なくなってるのは一目瞭然でしょう」
消しゴムは板チョコのように縦3列で横長に並べられていた。示された箇所を見ると、確かに右上の角の部分だけ消しゴムがない、それこそちょうど板チョコをそこだけ食べたような感じだ。
「刑事さんの言うように、確かに個数まで憶えていたわけじゃありません。でもきっちり縦3個で並べてるんです。正午に見た時には間違いなく1個も欠けていませんでした。でも今は見てください、一番右の列だけ2個しかないじゃないですか」
「ナルホド」
警部はそう言って棚を見つめる。私も警部の肩越しに消しゴムを数えた…縦3列に横7列、右上の1個が欠けて計20個。店内も明るいので見間違うとは考え難い。
「どこかに落ちているとかはないのでしょうか?」
黙っている警部に代わり私が尋ねた。店長は「もちろん棚周辺も探しましたよ」と返す。消しゴムは棚の上にしっかり置いてあるので客の身体が当たって偶然落ちる可能性も低いか。私はレジの方を見る。少年少女はお互いに言葉を交わすこともなく、成績表の返却を待つ時のように不安を浮かべてこちらを見ていた。レジは入り口のすぐ横だ、あそこに店長がいたのなら客の出入りを見逃すはずはない。消しゴムが消えた時、店内にいたのはあの二人と考えるしかなさそうだ。視線を戻すと、変人上司は棚を見つめたまま右手の人差し指に前髪をクルクル巻き付けている。店長はしばらく黙ってそれを見ていたが、沈黙に耐えかねたのか不機嫌そうに口を開いた。
「どうです?わざわざ来てもらって恐縮ですが、結論はもう出てるんですよ。男の子の方はボディチェックさせてくれましたけど、消しゴムなんて持っていませんでした。となるともうあの女の子しかいないでしょう?僕だって子供を疑いたくはないですが、けして根拠もなく言ってるわけじゃないんですよ」
警部は何も返さない。店長はこちらを見た。
「そうだ、じゃあ女刑事さんにあの子のボディチェックをしてもらいましょうか。それではっきりしますよ」
「そう…ですかね」
どう答えたものかわからず曖昧に返事をした。その瞬間、パチンという軽快な音が店内に響く。警部が立てていた指を鳴らしたのだ。
「その必要はありませんよ、店長さん」
よく通る声が告げる。
「消しゴムの消息はわかりましたから」
2
警部は少年少女も棚の所に呼び、相変わらずの得意げ口調で語りを始めた。
「よろしいですかみなさん、現在赤井さんに疑惑が向けられている消しゴム万引き事件について説明します」
全てを見通し田天才はまた右手の人差し指を立てる。
「正午に店長さんが見回った時には、消しゴムは縦3列でぴっちり並んでいた。しかしそれが1時過ぎに確認すると右上の1個が欠けていた。その間に店内にいた客は赤井さんと青島くんだけ。青島くんはすでに店長さんのボディチェックを受けて何も持っていないことは証明されています。
…確かに赤井さんが万引きしたように見える状況ではありますね」
「あたしはしてません」
彼女が胸の前で拳を握ってそう言うと、警部は優しく「大丈夫」と返した。
「しかし赤井さんは万引き犯ではありません。いえ、そもそも万引き事件なんてなかったんですよ」
「一体どういうことですか?」
と、店長。警部は棚の上に並んだ消しゴムを指差す。
「あなたはおっしゃいました、消しゴムの並んだ形を見て1個欠けていることがわかったんだと。個数まで憶えていたわけではないと」
「同じことじゃありませんか」
「いいえ店長さん、これは必ずしも1個なくなっている形とは限らないんです。そう、2個増えている形なんですよ」
「えっ」
私も含めその場にいた全員が小さく声を漏らした。消しゴムがなくなった謎に頭を抱えていたところに、全く逆の答えが示されたのだ。もともと縦3列横6列で並んでいたところに消しゴム2個が追加され、まるで縦3列横7列から1個なくなったように見えたのだと警部は解説した。
「フフフ、店長さんが勘違いするのも無理はありません。横6列と7列の違いなんて普通気付きませんし、それよりも四角形にぴっちり並んでいたのが1個欠けた形に変わっていることの方に意識は向いてしまうでしょう。それに、商品を盗む人間はいても増やす人間なんて普通はいませんから。
つまりこの事件、消しゴムは持ち去られたのではなく持ち込まれたということです。最近この消しゴムが何度か万引き被害に遭ったということでしたね。となればおそらく、過去に盗まれた消しゴムがこっそり戻されたのではないでしょうか」
唖然とする店長を尻目に、警部は少年の前にゆっくり進み出る。
「消しゴムを戻したのは君ではありませんか、青島くん」
少年の瞳が大きく揺れた。確かに警部の推理どおりだとすると、このみがそれをやったとは考え難い。学校をさぼって制服姿で店に来れば目立つし、彼女は自分で警察まで呼んでいるのだ。
「…ごめんなさい」
少年は泣きそうな顔でそう言うと歯を食いしばって頭を下げた。店長が詰め寄る。
「それじゃあこれまで万引きしたのも君だったのか」
「いいえ、それは違います」
警部が厳しい声で制した。
「同じ商品を二つも万引きしないでしょう。それに盗んだ品をこっそり戻すのなら、お客さんが多い時間帯を狙いますよ。それなのに青島くんは開校記念日で同級生がおらず、しかも他のお客さんも少ない時間帯にそれを決行しました。他の誰かに疑いがかからないようにするためです。すぐに帰らなかったのも、赤井さんに疑いがかからないか確認したかったからではないでしょうか」
少年は身体を震わせて両手で顔を覆う。
「本当に悪い子なら、例え盗んだ消しゴムが邪魔になったとしてもどこかに捨ててしまいますよ。君はおそらく誰かに頼まれた…いや命令されたんじゃないのかな?」
少年は顔を隠したままその場にしゃがみ込んだ。指の間から鳥のさえずりのような儚い泣き声が漏れてくる。店長も自らの過ちを察したように唇を噛んた。そしてこのみは…濡れ衣のことなど忘れたかのように、少年の肩にそっと手を置いた。そして自らも中腰になって彼に顔を寄せる。
「ね、もういいから全部話して」
私たち大人はメンバーズカードをなくしてしまった子供の世界…そこだけに存在する言葉を告げるように彼女は囁く。すると彼もまた、それが魔法の呪文であったかのように頷いて顔を覆った手をどける。二人は小さく言葉を交わすと一緒に立ち、異世界の住人である私たちに向き直った。
「本当に…すいませんでした」
深々と頭を下げる少年。その隣で彼女も一礼した。
「青島くん、悪いグループに脅されてやったそうです。お願いします、逮捕とかそういうのは許してあげてください。あたしは何も気にしていませんから」
警部が「了解しました」と返す。続いて店長も「疑って申しわけなかった。許してください」と頭を下げた。子供たちはほっとしたように頷き合う。
「ということでいいよね、ムーン?」
振り返って尋ねる上司に私は「これは仕事じゃなくボランティアですから」と返した。難解な殺人事件をいくつも解決してきたこの人にとって、こんな謎解きは天才外科医にとっての虫垂炎手術よりも簡単で取るに足らないものだったに違いない。でもきっとこの子たちにとっては、明日が変わるくらい重要な出来事だっただろう。
「ありがとうございました、カイカンさん、ムーンさん」
少しだけ可愛く首を傾けると、このみはそう言って淡く微笑んだ。
*
その後、店長からの連絡で少年の母親が姿を見せる。詳しく事情を聞いた母親は少年を潰れるほど強く抱きしめ、一緒に寄り添って帰って言った。そんな姿をこのみはどこか羨ましそうに見つめていた。少年に事後処理を強要した本当の万引き犯グループについては、母親から学校に相談して対処してくれるという。
■第四章③ ~赤井このみ~
マジすごかった、超能力みたいだった。ほんとに謎が解けるんだ、刑事さんって。
あたしは興奮でドキドキしながら店内を歩く。別にいいって言ったのに、店長さんがどうしてもお詫びのしるしに何か一つプレゼントするって言うからそれを選ぶために。カイカンさんも「せっかくだからもらっておきましょう」って言ってくれたし。う~ん、どれにしよっかな。やっぱあんまり高いのはよくないよね。そんなことより青島くん…ちゃんといじめグループに立ち向かわなきゃダメだよ。負けないでほしいな。
「戦利品は決まりましたか?」
すぐ後ろから声がした。見るとカイカンさん、その隣にはムーンさん。ムーンさんは室内で見てもやっぱり綺麗。
「まだですけど、ボールペンにしようかと思って。ほら、このキラキラしてるのとか良くないですか?」
「フフフ、そうですね。私の頃にも色々なペンがありましたよ。注射器の形したやつとか、コーヒーメイカーのミニチュアがついてて触るとブクブク泡立つやつとか…ねえ、ムーン?」
「警部と私は世代が違いますので」
「ありゃ、そうだっけ」
ほんとに不思議な人たちだな。ふと見ると店長さんがしょぼんとした感じでこっちを見てる。最初は疑われて頭にきたけど、なんだか今はこっちが申しわけない感じ。
「あの、カイカンさん、やっぱりこの赤い髪がいけないんですかね。そのせいで疑われて、みんなに嫌な思いをさせたんですかね」
「どうでしょう、まあ確かに一般的なイメージとしてそういう髪の色をしている人は不良だったりチャラチャラしてたりするのかもしれませんね」
「…ですよね」
「しかし赤井さん、君はそうではありません。それは君と話をすればわかることです。私もこれまで色々な人に出会ってきましたが、外見と内面の違う人なんて山ほどいましたよ。それにその髪、とても良い色だと思いますよ」
そこでムーンさんも言う。
「そうですね、可愛いと思います。それに外見の問題なら警部がダントツでナンバーワンですよ。警察官なのにしょっちゅう職務質問受けてますから。私も一番最初に会った時、警視庁に新入した不審者かと思って取り押さえちゃいました」
「そうなんですか、ハハ」
あたしが笑うとカイカンさんは「おいおいムーン、それを言っちゃあ」と慌てる。美人刑事さんは「失礼しました」とおすまし。ほんとに不思議な人たちだ。
そんな会話をしながらあたしは一本の赤いペンを見つける。黒いボールペンの中に一本だけあった赤いボディのペン。でもインクは黒。なんだかあたしみたい。
「よし、これにしようかな」
験し書き用に置いてあるメモ用紙に文字をしたためる。うん、書き心地もいい感じ。これに決めた!
「このペンをもらうことにします」
あたしがそう言って隣を見ると、カイカンさんがあたしの書いた文字を見て固まっている。え、何?石になっちゃったみたいに、右手の人差し指を立てたまま微動だにしない。一体どうしちゃったんだろ。
「あの、カイカンさ…」
「赤井さん、大丈夫だから」
呼びかけようとしたあたしを止めるムーンさん。そっと唇に人差し指を当てて沈黙を命じた。よくわかんないけど、これもカイカンさんには珍しくないことみたいだ。
…何だろ、ただ試し書きでアイウエオって書いただけなのに。
*
結局カイカンさんは固まったままだったので、あたしはムーンさんにお礼を言って店を出る。店長さんはボールペンをラッピングしてくれようとしたけど、悪い気がしたので断わった。シールだけ貼ってもらって商品を受け取る時、店長さんが最後にもう一度「ごめんね」と言ってきた。
「こちらこそご迷惑おかけしました。学校さぼってたのはほんとですし、今度はちゃんと放課後に来ますね」
自然にそんな言葉が出た。時刻はもう3時半。まだ家に帰るには早いし、これからどうしようかな。せっかくだからデパートとか行っちゃおうか。
ボールペンを胸ポケットに挿すと、あたしは夕暮れに向かう街に踏み出した。
■第五章① ~ムーン~
1
パチン、と店内に先ほどより大きく警部の指の音が響いた。
「アイウエオ…もしかしたら」
催眠術から醒めたように警部が動き出す。店内は下校中の生徒たちで賑わってきていた。
「警部、何かわかったんですか?赤井さんはもう帰っちゃいましたよ」
「ああそう、それよりムーン、もしかしたらダイイング・メッセージの謎が解けるかもしれない。現場に戻ろう」
二人で店を出ようとしたところで、息を切らせた男性が駆け込んでくる。応対した店長に対して彼は赤井このみが通っている中学校の教員だと名乗った。店長が青島の母親に連絡した時、このみの学校にも電話をかけ謝罪を入れていたらしい。
「私は生活指導の南波です。あの、赤井は…」
「もうお帰りになりました。あの、本当にすいません、生徒さんを疑ってしまって…」
店長が頭を下げる。教師も恐縮してかぶりを振った。
「こちらこそご迷惑をおかけしました」
そこで南波は警部と私を見る。店長が警察の人たちだと伝えると彼はとても驚いたようだった。
「あ、でもご安心ください。私たちはたまたまボランティアで協力しただけですから」
警部は簡単にそう説明すると、「では急ぎますので」と店を出た。私も一礼してそれに従う。南波は必死にこのみの行き先を尋ねていたが、店長がそれを知るはずもなかった。
2
『セブンファイブフォー』のオフィス。大きな窓から注ぐ日差しはもう弱く、夜がそこまで来ていた。警部は昆布をくわえたまま室内を歩き回り、また血文字の前で立ち止まるといった動きをくり返している。
床には被害者の体を表した人型の白線、その人型が伸ばした右腕、その先にある血文字、辺りに散乱したペン・マジック・書類…。文房具店で何かひらめいた様子だったが、アイウエオの意味が警部にはわかったのだろうか?
しばらく床を見つめていた警部は今度は大画面テレビに視線を注ぐ。そしてゆっくり右手の人差し指を立てるとこちらを見ずに言った。
「ムーン…このオフィスで見つけてほしい書類がある」
*
私はオフィス内の書類をチェックする。警部が探すよう指示したのはおおよそ事件とは関係なさそうな代物であったが…こんな時はとにかく従うしかない。それが事件改名への最短ルートだと私もこれまでの経験で十分承知している。
私が引き出しを引っ掻き回す中、警部も床に散らばった書類や壁に貼られた書類をチェックしている。どうしても気になったので私は手を動かしながら尋ねた。
「警部、もしかしてダイイング・メッセージがわかったんですか?」
「一つの解釈はできたと思う。でももし血文字の意味がそうだとしても、犯人はどうしてそれを消していかなかったのかが疑問だ。解読できなかったとしても、被害者が書き残した文字をそのままにしていくなんて…」
警部は口先で昆布を揺らしながら話す。
「それに藤川さんが遺体を発見した時、入り口のドアは施錠されていなかった。犯人が泥棒なら合鍵を持っていたはず。どうして鍵をかけずに出て行ったのか…」
確かに人間心理から考えれば遺体発見を遅らせるために鍵はかけるのが自然だ。
「それだけ気が動転していたということでしょうか」
「そうかもしれない。でも金庫のお金はしっかり持ち去ってるんだ。その頭があるんなら、血文字を消したり鍵をかけたりだってできたはずだよ。ねえムーン、私には犯人が何らかの事情で急いで立ち去ったように感じるんだよ。
犯人はとても急いでいた…慌てていた?だとしたら何故?急ぎの用事があった?約束があった?それとも誰かに現場を目撃された…?」
そこではっとしたように警部が窓を振り返る。足早に歩み寄ると珍しく「まさか」と口にした。私もそちらを見ると、通行人が何人か歩いているのが見えた。
「…ムーン、この窓はマジックミラーだったね」
警部が神妙な声で尋ねる。
「はい、そうです。ですから通行人からこちらは見えません」
「でももし犯人がそれを知らなかったとしたら?人を殺害した直後の犯人が、通りからこちらを見つめる人間に気付いたとしたら?
…自分の犯行が目撃されたと勘違いしたかもしれない。だとしたら犯人は目撃者の口を封じるために急いでオフィスを飛び出したっておかしくない。だから血文字は放置され、鍵もかかっていなかったんだ」
警部の推理力・想像力が並外れているのは知っている。しかしいくらなんでもそこまで具体的に絞り込めるはずがない。
「何か心当たりがあるんですね?」
「ムーン、昨日行った中学校はこの近くだよね。となるとこの窓の前の通りも生徒たちの通学路なんじゃないか?」
どんどん早口になる警部。私は窓の外を見ながら答える。
「そうだと思いますけど…」
「赤井さんが言ってたんだ、彼女が髪を赤くしようと思ったのはビルの窓に映った自分があまりにちっぽけだったからだって。窓に映った自分に話しかけてるうちに、そう思い立ったんだって。もし彼女が話しかけたのがこの窓だとしたら、中にいた犯人からは自分を目撃して何かを言ってるように見えたかもしれない」
恐ろしい推理が現実味を帯びてくる。書類を持つ指先が震え、背中を冷たい汗が一筋流れた。もしそうだとしたら…。
「警部、赤井さんが髪を染めようと思ったその日はいつなんですか?」
「…先週の金曜日さ。その日は進路面談で帰る時はもう日が暮れていたって言ってた」
金曜日の夜…それは被害者が居酒屋からここに戻った自国、まさに反抗推定時刻だ。そう思った瞬間、視線を引き出しに戻した私の目は目当ての書類を発見する。
「ムーン!」「警部!」
同時に叫び合う。一瞬早く私が口火を切る。
「ありました、探しておられた書類です。これで役に立ちますか?」
飛び掛る勢いで手渡すと、警部は「OKだ、ムーン」と意気込んだ。
「じゃあ君は急いで赤井さんを保護してくれ。もしかしたら犯人が今も彼女を狙っているかもしれない」
「わかりました、警部はどうされます?」
「私はこの書類を手掛かりに捜査して犯人を特定する。君が彼女を保護するか、私が犯人を確保するか、どちらかが成功すれば大丈夫だ」
警部が昆布を飲みこむ。了解を伝え私は全速力でビルを踊り出るとそのまま愛車に飛び込んだ。午後6時を回り、辺りは夜に包まれている。こんなことなら彼女の携帯電話の番号を聞いておけばよかった。いや待て、落ち着け、学校に訊けば彼女の住所や保護者の連絡先がわかる。親なら彼女の番号を知っているはずだ。もし帰宅していなければ親から連絡を取ってもらえばいい。
中学校の電話番号は…昨日職員室を訪ねた時にもらった名刺が役に立つ。私はイグニッションキーを回すより前にまずそこに記された番号にコールした。
プ、プ、プ、プ…。
気がはやる。焦るな、焦るな、大丈夫だ!
トルル、トルル、トルル…。
警部は言った、どちらかが成功すれば大丈夫だと。それはつまり…どちらも失敗すればアウトということだ。
…成功させなければ!
■第五章② ~赤井このみ~
またママからの電話が鳴ってるよ。しつこいなあ、どうせ早く帰ってこいとか言うんでしょ。そんでもって髪の色を戻せってお説教をするんでしょ。そんなのもううんざり。
あたしは着信を無視しながら街をぶらついた…コンビニとか、本屋さんとか、小物ショップとか。でももう日も暮れたしどうしようかな。帰りたくはないけど、帰るしかないか。
公園のベンチであたしはすみれから届いたメールを読み返す。一時間くらい前に届いたメール。
『反乱軍のリーダーこのみ様、人生初のサボタージュはどうでした?数学の授業でこのみがいなかったからチャビンがどうしたんだって何度もみんなに尋ねてたよ。うちも何回も訊かれたけど誤魔化しちゃった。
そしたらさっき、街でもチャビンに会ってさ。このみのこと捜し回ってる感じだったよ。愛されてるねえ(笑)。そんな感じかな。まあ反乱もほどほどにね。じゃあまた明日~!』
…チャビンが捜し回ってるって、こりゃ相当怒ってるな。いいじゃん一回くらい授業さぼったってさ。もしかしてチャビンからママに連絡行ってるのかも。だからこんなに何回も電話かけてくるのかも。だとしたら帰ったら大目玉だな。
あたしは腰を上げるとスマートフォンの電源を切る。もうちょっとだけぶらぶらしてから帰ろう。
■第五章③ ~?~
見つけた、見つけたぞ!
あの赤い髪…間違いない、あいつだ。講演からとぼとぼ出てきやがった。
あの時、あのオフィスで社長を殺した時にあいつは窓の外から俺を見ていた。見ながらぶつぶつ何か言ってた。今のところそのことを警察には通報してないようだが、いつそうするかわかったもんじゃない。その前にどうにかしなければ。
幸い警察はまだ俺には目を付けてないようだ。あの美人の女刑事、オフィスのビルから出てきたのを見たから多分事件を捜査してるんだろうけど、俺を見ても何も知らない様子だった。今なら逃げ切れる、逮捕されずにすむ。そのためには目撃者を確実に黙らせなければ。
落ち着け、ゆっくり後をつけるんだ。
ここはまだ人通りがある。あいつが路地に入ったところでかたをつけてやる。
よし、そのまま歩け。街にはのん気なクリスマスソングが流れてやがるがまあいい。そう、赤鼻のトナカイさ。
暗い夜道でもそのふざけた髪が俺の目印になってくれるからな。
あいつが裏通りに入る。
…よし、今だ!
TO BE CONCLUDED.
(文:福場将太)