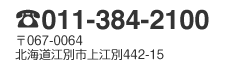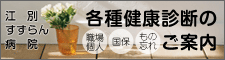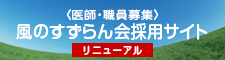- ホーム(法人トップ) >
- 江別すずらん病院 >
- コラム >
- コラム2014年10月「★連載小説★Medical Wars 第7話」
コラム
コラム2014年10月「★連載小説★Medical Wars 第7話」
Medical Wars (福場将太・著)
*この小説はフィクションです。
■第7話「2つの告白」 (眼科)
1
まずは夜が冷気を帯び、少し遅れて日中にも肌寒さが存在を強める…そんな10月最終週。今週14班が回るのは眼科である。結論から言うと、今回は美唄の物語。
月曜日は朝から雨であった。深夜に東京の空を覆った霧雨のベールは明け方には無数の雫に姿を変え、道行く人々の傘に滴っている。
いつものようにみんなで集合する朝の学生ロビー、そこからして彼女は不自然であった。笑顔も元気も一見は普段通りなのだが、どうもテンポというかタイミングというか調子がおかしい。それは同村でなくとも、他の4人の目にも明らかであった。
「さあ今日も元気に頑張ろう、エイエイオー!」
まずは第一声、そうやって振り上げた拳を彼女は壁にぶつけた。痛そうに患部をさすりながら、心配してくれる同村に「ごめんごめん、テンション上げすぎちゃった」と苦笑い。最初はただのドジかとも思われたがその後の実習でもやはりおかしい。必要以上に話していたかと思えば、今度は逆に指導医から質問されて何も聞いていなかったりする。院内ではほとんど私語をしないまりかでさえ、気になって「ねえ大丈夫、美唄ちゃん?」と声をかける始末。その度に美唄は「え、何が?大丈夫だよ」とガッツポーズを返すのだが…。そう、けして明るさがないわけではない。ただその明るさに…無理があるのだ。未だ飲み会開催には至っていないとはいえ、もう半年以上も苦楽を共にしてきた仲間たちがそれを感じ取らないはずがなかった。長や井沢が「今日の美唄ちゃんどうしちゃったんだ?」と囁き合う中、ただ一人向島だけが時折冷静な視線を彼女に送っていた。
そして迎えた眼科2日目の火曜日、雨はまだ降っている。朝の集合に少々早く到着した同村は学生ロビーの隅で山田と話していた。
「ドーソン、なんか14班ますます仲良い感じじゃん!」
山田が白衣の腕まくりをしてそう言った。季節が秋に向かい、学生たちの衣装もケーシーからまた長袖の白衣に戻りつつある。
「…そうかな」
「そうだよ、俺の班なんてバラバラだべ。男ばっかだし。そっちは女が2人もいるもんな」
同村は「まあ…」と曖昧に頷く。
「秋月と遠藤か…改めて考えてもすごい組み合わせだよなあ、特待生とキャピキャピ娘」
「変な言い方するなよ」
少しムッとする同村に、山田は声を落として続けた。
「いやすまん、お前が遠藤に惚れてんのは俺も賛成だけど…」
「山さん、こんなとこで何言ってんだ」
同村も小声で牽制する。
「いや悪い、ただ…変な噂聞いてさ」
「…噂?」
「いや、聞いた話だけど…遠藤って学校じゃあんなに明るいけどさ、新宿の街で会っても同級生とか無視して通り過ぎるんだってさ」
「…そんな」
とても信じられない話だった。同村の知っている彼女は、むしろみんなでいる時も誰かが蚊帳の外にならないよういつも気を配っているような人間だからだ。人のちょっとした心の変化や痛みも敏感に感じ取る…そんなところこそ彼が美唄に惹かれた最大の理由でもあった。彼の悲しそうな瞳に気付き、山田は慌てて取り繕う。
「まあ、ただの噂だべ。どうせモテない女たちが嫉妬して流したんだろう、気にすんなドーソン」
そこで悩める親友の肩を叩き、「俺はお前を応援するべ、変なこと言ってすまん」と付け加えた。
「ああ…ありがとう」
「じゃあ俺、時間だから行くべ。またそのうち飲もうな」
正直過ぎるのがたまに傷な男はそう言うと颯爽と学生ロビーを出ていった。一人で病院に向かうところを見ると、確かに彼の班はバラバラらしい。
その後、同村はいつものソファに移り班員たちの到着を待った。一人、また一人と姿を見せたが…彼が一番待っていた存在は結局集合時刻を過ぎても現れなかった。
「しょうがない…行きましょう」
何度か携帯電話でコールした後、腕時計を見てまりかが歩き出す。同村たちも仕方なくそれに続く。また長と井沢が「美唄ちゃん、何かあったのかな」と囁き合う。
その後、眼科外来で行なわれたのは教授による診察主義の実習。もしかしたらと同村はずっと入り口のドアを意識していたが、結局最後まで彼女が姿を見せることはなかった。
*
「本当にどうしたのかな、美唄ちゃん」
昼休み、キーヤンカレーで井沢が言った。いつしかこの店は彼らの居場所のひとつになっている。
「確かに…今まで全出席だったのにな。サボるのは向島さんの専売特許ですよね」
と、長。
「おいおい、最近はちゃんと来てるだろ」
向島が笑い、そこでみんなも笑った。その後カレーを味わいながら雑談を楽しみ、食後のコーヒーが運ばれた頃にまた長が話題を戻す。
「でも美唄ちゃん、昨日もなんか変だったし…。向島さん何か聞いてないんですか?」
音楽部先輩は「いや何も…」と静かに答えるのみ。その視線は手元のコーヒーに落とされている。
「私も何回も電話してるんだけど、繋がらなくて…」
今度はまりかが口を開く。
「ねえ、同村くんは何か聞いていないの?」
「いや、何も…」
先ほどまでの雑談でもどこか上の空だった同村はカップを置いてそう応える。そして数秒の後、はっとしたように切り返した。
「だ、だいたいどうして俺に聴くんだよ」
「だって、仲良いから」
まりかが少し悪戯っぽくそう言い、井沢と長もニヤリとした。彼のロマンスはもはや公然の秘密になりつつある。主人公は「べ、別にそんな…」と赤くなった。文芸部にあやかって言うなら、『走れメロス』のラストシーンのメロスのようだ。
「だって、いつも一緒に帰ってるし…」
「あ、秋月さん!それは帰る方向が一緒だからだよ」
「それに、呼び方も一人だけ『遠藤さん』だし…フフッ」
まりかがそこで笑う…こんな時の彼女は珍しく女の子っぽい。いや、こりゃ失敬。
「それは、別にたいした意味は…。君のことだって秋月さんって呼んでるだろ」
「ま、いいんじゃない?パワー娘と無気力男」
向島も笑ってそう言った。
「何言ってんですか、向島さん!」
そう声を荒げる同村に、長は「いや〜若いって素晴らしい」と腕を組んで頷く。うんうん、本当に同感です。うらやましいなあ!
「長さんまで…」
「まあ同村、冗談だよ、冗談!そんな怒るなって」
笑いながらそうなだめる井沢に同村は「まったく…」と赤い顔のままコーヒーを飲む。
その後話題はまたお互いの将来のことに流れていった。恋や夢がコーヒーの香りと混じり合う…そんな穏やかな昼下がりのひと時。
*
キーヤンカレーから戻り、再び白衣姿となって午後の実習のため学生ロビーに集合すると、そこには同じく白衣姿の美唄の姿があった。いつものソファに腰を下ろし、窓に落ちる雨に黙って視線を投げかけている。彼女はみんなに気付くと振り向いて笑顔を見せた。
「おっはよーみんな!…っていうかもうこんにちはかな。今朝はごめんね、ついつい寝坊しちゃって」
「な〜んだ、そうか」
と、長。続いてまりかも「もう、心配しちゃったよ美唄ちゃん」と笑顔で迎える。「今日キーヤンカレー行ったんだぜ?」と井沢もどこか安心した顔。
「あ、そうなの?私も食べたかったな、も〜」
美唄は子供のように悔しそうな顔。そこで向島が言う。
「まあまたそのうち行くでしょ。なんやかんやでしょっちゅう行ってるし」
「あ、MJさん、今日は朝からいらっしゃったんですね」
「君までそれを言うか、最近ずっといるだろ!」
そこでまた笑いが起こる。美唄も「あ、そういえばそうですね、アハハ」と明るく返した。
「でもまあ、遠藤さんが事故とかに遭ったんじゃなくてよかったよ」
ひとしきり笑いがやんだところで同村がそう言う。そんな様子に残りの班員たちはまた少しニヤリとする。
「ありがと、同村くん。でももし事故だったら救急車でそのまま駆けつけるから」
「そんな無茶な」
と、長がツッコミを入れる。そこで井沢も続いた。
「眼科の実習なんだから、救命救急センターに運ばれてもしょうがないじゃん。あ、そう言えば俺らの班、クリスマスの週が救命の実習なんだよね。まったく、ツイてないぜ」
「あ、そうなの?」
と、美唄。そこでまりかが腕時計を見て歩き出しながら言った。
「そうなのよ。救命救急が今年最後の実習で、イブが年内最後のポリクリ」
各々イブのポリクリについての見解を述べながら、他のみんなも歩き出す。そんな中、ふいに向島が虚空を見上げて言った。
「イブに予定がある人はポリクリ免除、とかあったら面白いな」
「え〜、それじゃあ頑張らないと!ね、まりかちゃん」
美唄がそう投げかけ、まりかは「そう言われても…」と複雑な表情。そこで井沢も同村に肩を組み、「お前も頑張らないとな」と一言。
「しつこい!」
また赤くなる主人公。しかしまあひとまず彼は安心したようだ。今目の前を歩いている彼女はいつも通りに明るく、いつも通りに笑っている。昨日のどこか不自然な印象も、山田の言っていた噂も、今朝の欠席も…きっと何かの思い過ごしだ。彼はそう自分に言い聞かせた。
*
午後からの実習は視力障害者の誘導の練習であった。場所は院内のリハビリルーム、20畳ほどのフローリングの部屋だ。指導担当は青年看護師の阿川。柔らかい物腰の彼は、専門に点字や歩行解除の視覚も持っていると自己紹介した。
「それでは始めます。みなさんもバリアフリーやノーマライゼーションという言葉はご存知ですね?近年、かつてに比べれば視覚の不自由な方でも暮らしやすい世の中になってきています。点字板や音声ガイドなどを見かける機会も多いでしょう」
阿川は動きやすいスポーツウエアに身を包み、6人の前に立って説明する。
「…とはいえまだまだ歩くのが難しい不便な場所もたくさんあります。院内じゃなくても、みなさんが街で視覚の不自由な方に手を貸す場面もあると思います」
そこで彼は立てかけてあった白杖を手に取る。
「これはそういった人たちが使う杖です。前方の障害物や段差などを確認するために役立つのはもちろんですが、自分は目が不自由だと周囲に伝えられるという意味でもとても大切なアイテムです。視覚の障害は一見しただけでは周囲からわかりにくいですからね」
そこでまりかが「その杖を使ってよい条件などはあるんですか?」と質問した。
「いいえ、目の不自由な方なら誰でも本人の意思で使って構いません。もちろん全盲の方だけでなく、弱視の方や視力はあるけど視野が狭い方など、周囲にわかっていてもらいたい方なら病状の度合いは問いません」
そこで阿川は白杖を彼女に渡し、その感触を確かめさせる。順に回しながら他の5人もそれを手にしてみた。最後に受け取った美唄も、実際に床に杖を立てて何やら考えている。
「それでは、誰かに実演してもらいましょうか」
阿川はそう言うとポケットからアイマスクを取り出す。最初にそれを着けることになったのは長だ。彼はその状態で室内に造られた擬似の街を杖を頼りに歩くよう指示される。
「気を付けてね、ゆっくりでいいから」
「は、はい…」
長は時々段差に足を取られたり、壁に足を擦ったりしながら進む。やる前に一応コースを見て確認はしたのだが…いざ歩いてみると難しいらしい。
「ではみなさん、声をかけて彼を誘導してあげてください」
阿川に言われ、5人は口々に言葉を投げる。
「長さん、もっと左です!」
「もうすぐ段差です、気を付けて」
長はそんな指示を参考に少しだけ歩くスピードを速めた。
「どうですか、長先生?」
「ええと、やっぱり難しいです」
アイマスクのまま長が阿川に答える。
「では、次は誰かがそばで体に触れて、残りのコースを誘導してあげてください」
それには井沢が選ばれた。長の横に立ち、杖を握っていない左腕に手を添えてゆっくりと進んでいく。
「いいですか長さん、もう少し左です。はいOKです。そのまま…」
彼は器用に誘導する。長も先ほどよりは安心して一歩を踏み出せるようだ。
「はい長さん、次は階段です。右足から一歩ずつ行きますよ」
「え?ああ、わかった」
こうしてコースを一周し、2人はみんなのもとに戻る。
「どうでした、長先生?」
アイマスクを取った長に阿川が尋ねる。
「ええ、見えないと結構怖かったです。段差とか斜面とかにビクビクしちゃいました」
「そうですね、いかに私たちが普段視覚に頼って生きているかということです。逆に言うとそれが不自由だということは、それだけ頼るものが少ないということです」
6人は頷く。
「ではみなさん、井沢先生の誘導はとても上手でしたが、何か気になったことや問題点はありましたか?何でも気付いたことを言ってみてください」
その問いにそれぞれ考え込むが…なかなか思いつかないようだ。まりかも先ほどのコースを見ながら思考を巡らせている。そこで井沢本人が口を開いた。
「もっと、頭の上のことも注意するべきでしたか?」
「はい、それもあります。街には足元だけでなく頭の上にも色々な障害物がありますからね。たとえ何もなくても、何もないということを伝えてあげると相手は安心します」
「なるほど…」
井沢に続き、まりかも深く頷く。阿川は「他に気付いたことはありませんか?」とみんなの顔を見回した。再び沈黙…しかしそこで美唄が無言で手を上げた。
「どうぞ」
「あの…階段とかにさしかかる時は、それが上りなのか下りなのかを教えてあげるべきだと思います。会談とか段差という言葉だけじゃ、目の悪い人にはそれが上りか下りかわかりません」
彼女の言葉はためらいがちであったが、阿川は「その通り!」と少し驚いた様子で返した。
「そう、上りと下りでは足の運びが全く違います。ここは室内ですから、いきなり下り階段ということはありませんが、街ではたくさんあります。介助される側はどうしても遠慮してしまって、なかなか自分から質問できないことも多いですから、そういうことにも気付いてあげることが大切ですね」
それを聞いて長も先ほど自分が戸惑った箇所を思い出す。
「いや〜よくわかりましたね。この質問は毎回するんですが、答えられた班はほとんどいません。今年は…初めてじゃないかな。こりゃ優秀な班だ」
看護師はそう言って微笑む。
「美唄ちゃん、スゴイ!」
まりかが小声で言った。誉められていつもの笑顔100パーセントかガッツポーズが発動するかに思われたが、美唄は小さく「別にそんな…」と返すのみ。そんな彼女に同村はまた少し怪訝な顔をする。
「みなさん、身体の不自由な方の介助をするというのはとても難しいことです。今の簡単な実演でもわかったように、相手の立場で考えることはなかなか大変です」
そこで阿川は真剣な表情になった。
「そして逆も言えます。介助されるということもまた難しい。今みなさんは介助をする側の勉強をしていますが、いつ自分がされる側になるかもわかりません。そのことを忘れずにいてください」
6人は「はい」と声を合わせる。そこでまた看護師は微笑む。
「では次はまたペアを変えてやってみましょう…」
2
翌日水曜日の実習は外来見学から始まった。待合室は平日午前だというのに相変わらず患者でごった返している。6人は診察に立ち会いながらそこで多くの患者の姿を見た。
一言に目が悪いといっても様々な形がある。遠視・近視といったピントの障害、見える範囲が制限される視野の障害、他にも暗さや明るさが苦手だったり色が判別できなかったり…その苦しさは患者の数だけある。本が読みづらくなって困ったものですと笑う老婦人、好きな仕事を失って塞ぎ込む青年、生まれながらに光を知らない幼い子供…。眼科外来の患者は午後1時を過ぎるまで引っ切り無しに訪れ、けして途切れることは無かった。
その後6人は短時間で昼食をかき込み、2時から病棟のカンファレンスルームでクルズスを受ける。担当は手塚、自らも丸メガネをかけた中年の男性医師だ。正面に立って話す彼の後ろにはスーツ姿の青年が控えていた。自己紹介をしない彼の正体を少し気にしながらも、6人は手塚の言葉に集中する。
「まあ眼科の解剖学とか病気の治療については他の先生のクルズスでやってるだろうから、僕からは少し違う視点での話をするね」
彼は洋画吹き替えの声優のようなシャープな声で喋る。
「外来見学でわかったと思うけど、眼科の治療っていうのは視力を回復させてあげることばかりじゃない。もちろんそれができれば一番だけど、そうはいかない疾患も多いよね。これ以上悪くならないよう予防してあげること、そしてその人に合わせた視力のサポートを教えてあげることが眼科医の仕事なんだ」
そこで手塚は後ろの青年に自己紹介を促す。彼は恐縮しながら一歩前に出た。
「どうも、ヨザクラメガネの三宅と申します。手塚先生にはいつもお世話になっております」
どうやら青年の正体は、手塚がよく連携するメガネショップの店員のようだ。彼はこれまでも色々な患者のニーズに合わせ、メガネやコンタクトレンズを用意してきたことを手際よく説明した。
「まあメガネで視力をサポートするのは当然だけど、今日三宅さんに来てもらったのは他の便利グッズを紹介してもらうためなんだ」
手塚にそう促され、青年は部屋の隅の大きなカバンからいくつかの物品を取り出した。学生たちはそこに視線を送る…それは今まで見たことのない物ばかりだった。三宅は机上にそれらを並べると1つずつ示していく。
「これらは全て視力補助具と呼ばれるものです。例えばこれ…」
それは一見フタつきの虫メガネ、しかし妙に持ち手の部分が太い。彼がフタをスライドさせスイッチを入れると、レンズの脇から明るい光が放たれた。「あっ」と6人が声を漏らす。
「これを使えば暗い場所でも小さな文字を読めます。レンズの倍率も一般の文房具店で売っている物よりずっと上です」
そして次に示されたのは板チョコサイズの電子機器。中央には大きな画面が埋め込まれており一見ポケットゲーム機のようにも見える。三宅はそれを電子拡大鏡だと紹介した。手塚の「ほらみんな、近くで見てごらん」の声を合図に、6人は立ち上がり未知の機器に群がった。そこで少し得意げになった彼が言う。
「みなさんよろしいですか?この新聞の上にこれを置くと…」
先ほどより大きな声が上がる。その画面には下の新聞の文字が拡大され映し出されていた。三宅がボタンを操作すると文字のサイズは自在に変化する。最大にすればたった一文字を画面いっぱいに広げることも可能だった。そしてその機器を横にずらせば、電光掲示板のニュースのごとく文字が流れていく。
「これなら相当目の悪い人でも読めるな」
と、長。向島も「すごいな」と呟く。まりかもメガネの奥の目を丸くして「これって画面の明るさの調整もできるんですか?」と尋ねた。
「もちろん、明るさもですが色調もその人が一番見やすいものを選べます」
青年がダイヤルを回すと白地に黒だった文字が黒地に白に反転する。また歓声が上がり、美唄も思わず「すごく読みやすい!」と漏らした。他にも青にオレンジ、紫に白など様々な色調が示される。学生たちの感動はまだおさまらないが三宅は次に進んだ。
「この電子拡大鏡はもっと画面の大きな物から名刺サイズの物まで色々あります。小さい物を持ち歩けば、例えば飛行機のチケットの文字が見えない時とかこれで読めます」
「そうか、搭乗口の番号とかチケットに書かれてますもんね。これがあれば人に訊かなくてもわかる」
井沢が興奮した様子で言った。
「そう…自分でできる、ということが大切なんだ」
と、手塚が付け加える。三宅も頷いて続けた。
「そうですね、確かに誰かに代わりに読んでもらうよりも患者さんの喜びは大きいと思います。あと最近はこんなのもあります」
三宅は胸ポケットから名刺サイズの薄い板を取り出した。「あ、アイズパッド」と長が反応する。
「そうです、最近流行のタブレット端末ですが、目の悪い方のために様々なアプリが開発されています。例えば…ちょっとよろしいですか」
三宅は壁際に立つよう美唄に頼む。そして従った彼女にその板をかざした。画面に美唄の腰から上が映し出されるのが同村たちにも見える。
…ピロリーン。
電子音が鳴り、次の瞬間その板は「白衣を着た長い髪の女性です」と喋った。またまた歓声が上がる。
「どういうことですか?」
同村が息を弾ませる。美唄自身もみんなのもとに駆け寄り「すっごーい、どうなってんの?」と笑顔を見せた。
「これは画面に映った景色を説明してくれるアプリです。他にも例えば…」
そう言って三宅が板を横に向けると、「白い机と黒い椅子です」と再びそこにあるものが音声で説明される。
「すごい…ここまで科学は進歩してたんだ」
と、感心する向島。長も「これなら目の見えない人でもそこに何があるかわかりますね」と納得する。
「他にもアイズパッドには色々なアプリがあるんですよ。お札が何円札か判別してくれるアプリ、今自分がどこにいて目的地までどう行けばいいか教えてくれるアプリ、困った時にボランティアの人に繋がってアドバイスをもらえるアプリ…。これらは全て目の不自由な方がこんなアプリがあったら嬉しいっていうアイデアに応えて開発されたんです」
「なるほど…」
同村はそこで小さな感動を覚える。ここにある便利グッズは、全て不自由に苦しむ誰かのそれを克服したいという願いから生み出されているのだ。
そこで思い出したようにまりかが三宅に言った。
「そういえばテレビで、音声パソコンってのを見たことがあります。それを使って全盲の弁護士さんが仕事してました」
「そうですね。他にも音声でメールを読み書きできる携帯電話、音声ガイド付きのエアコンや炊飯器なんてのもあります。大きいので今日は持ってこれませんでしたけど、本をスキャンして音声で読み上げてくれる機器まであります。みなさん、せっかくですから手に取って実感してみてください」
その後6人は興味津々で視覚補助具を体験した。その瞳はおもちゃ屋ではしゃぐ子供のように輝いている。向島が長に魔法の板をかざすと…「白衣を着た男性です」。
「すごいな、でもやっぱりオッサンですとは言わないんだ」
大真面目な先輩に長が「そりゃそうでしょう!何言ってるんですか」と返す。美唄は電子拡大鏡で新聞を読みながら「すごい迫力だよ、まりかちゃん!」とはしゃいだ。井沢もライト付き虫メガネを手に取りながら「今度ばあちゃんに買ってやろうかな」と微笑んでいる。そして同村はそんな5人を見ながら久しぶりに決めゼリフを放った。
「ドラえもんは…実現するな」
文芸部の無気力男よ、今回ばかりはその愚かな独り言を許してやろう。
その後全員が一通り未来の秘密道具を味わったところでクルズスは終了となった。三宅が頭を下げて先に退室し、手塚も明日の実習の予定を説明したところで立ち去ろうとしたが…。
「あ、そうだ」
ドアの手前で振り返って彼は言った。そこには悪戯っぽい笑みが浮かんでいる。
「みんな今日の夜は空いてる?…っていうか空いてなくても空けてね。実は教授から伝言があって…」
その瞬間全員が胸の中で思った…やっぱりきたか、と。
*
教授からの伝言はまあ端的に言うとこういうことだ…「飲みに行くからつき合え」。もちろんそんな威圧的な言葉ではなかったが、そこに教授という権威の衣を着せればそういう意味合いになるのは明白だ。当然学生の彼らに拒否権はない。
教授の名は三玉、学生好きで有名な初老の男性医師…眼科の実習に来た学生を必ず一度は飲みに誘う。事前に回った班からその情報は届いていたため、ここは仕方ないと6人もある程度腹をくくっていた。
約束は午後7時に病院近くの中華料理店。彼らは20分前に集合した。今日は雨は降っていなかったが朝からずっと曇り空、冷気を帯びた夜風が店先に佇む6人に吹き付ける。しかしここで先に店内に入れるはずはない。
やがて三玉は時間通りにノリノリでやって来た。
「お疲れ様です!」
学生は揃って頭を下げる。
「おう待たせたな、行くか!」
背は低いが骨太な体系、教授はがに股で歩み寄ってくる。その顔は日本人離れした鼻の高い西洋風…寂しい頭髪もむしろかっこよく見える。若い頃はきっと相当なハンサムだったに違いない。
「今夜は結構冷えるな。早く入って飲もう、ガハハハ」
そうしゃがれた声で笑う男を見ながら同村は密かに思う…この顔に手塚の声だったら本当に洋画みたいだったのにと。
そこで三玉はふと美唄に気付く。
「あれ、お前昨日の俺の実習の時いなかったな」
「すいません、寝坊しちゃって…」
美唄は謙虚に謝り頭を下げる。さすがにここは笑顔100パーセントでは通らないことを彼女も知っている。
「よ〜し、説教だ!俺の横に座れ!ガハハ…」
教授はそう言って14班のアイドルを店内に引っ張っていく。知らない人が見たら不健全な光景でもあるが…まあそれは学生好きゆえの優しさ、ということにしておこう。
「同村、怒るなよ」
とそっと井沢が耳打ちする。「何言ってんだよ」と返す主人公は確かに少し不機嫌そうだ。だがここでジェラシー任せに教授をブッ飛ばすほどさすがの彼も子供ではない。そもそもそんな度胸なんて見せたことのない人生である。
*
「どうなんだ、お前らみんな酒は飲めるのか?」
席に着くやいなや、三玉が大声で言った。
「飲める奴はジャンジャン飲めよ!それで二日酔いなら明日のポリクリは免除だ、ガハハ」
噂通りの教授に圧倒されながらも、6人は飲み物を注文する…といってもバイクを運転する長と飲めないまりか以外はほぼ強制的にビンビールだ。
「先生のご専門は、眼科のどの分野なんですか?」
飲み物が揃うまで、少し時間が空くと井沢がすかさず会話を作る。このあたりのテクニックは相変わらずお見事。
「専門?そんなの全部に決まってるだろ、ガハハ」
「そうですか、さすがですね」
今度は長がそう続けた。さすが年の功!…ってこりゃまた失敬。
そうこうしているうちに飲み物が運ばれてきて、三玉のもと乾杯が行なわれる。
「よおし好きな物を注文しろ、遠慮はすんなよ!お前は何か好きな物あるか?」」
教授は隣の美唄にメニューを見るよう促す。彼女はいつもの笑顔を少しだけ解放してそれに応じた。
「う〜ん、やっぱりここはエビチリですかねえ」
「おういいぞ、どんどん頼め!ガハハ」
美唄との距離がやや近い三玉の姿に同村のグラスを握る手が強まる。…まあまあ、ここは抑えて。これも社会勉強です。
*
「どうでい、眼科は楽しいかえ?」
開始から1時間。酒も入り顔を赤くした三玉の呂律も怪しくなってきた。
「ええ、まだ3日目ですけどとても興味深いです」
と、まりかが真面目に答える。
「そうかい、じゃあぜひ将来入局してくれよ…ってお前らはオールラウンド研修とかがあるから決めるのはまだずっと先か。いやいや勝手に新しい制度が始まっちまって難儀だなあ」
「ええ、まあ…」
と、井沢。そこで教授は現場の意見も聞かずに決めてしまうお偉方への苦言をいくつか並べた。学生は背筋を正して拝聴するしかない。
「それにしてもまあ…」
ひとしきり言い終えると、三玉は言葉を止め6人を見回す。
「う〜ん…いいなぁ、この班はよぉ!こんな可愛い女の子が2人もいて。俺の時なんか野郎ばっかの班だったからよぉ」
…何十年前の話だよ、とみんな思うがもちろん誰も口にはしない。三玉はそこで「これはもう飲むしかない!」と自らグラスを空ける。客も増えて店内もかなり賑やかだが、それでも彼の声が一番大きい。
「だからお前らは幸せだよぉ。おいそこのお前、さっきから黙って飲んでんじゃねぇよ」
それは当然同村のことだ。
「す、すいません」
「元気が足りん!お前、女はいるのか」
「い、いえ、おりません!」
「何?それはけしからん、飲め!」
文芸部の同村は当然こういった体育会系のノリに慣れていない。それでも持てる限りの知識を総動員し彼は「飲みます!」とグラスに両手を添えてそれを空けた。
「おう、いい感じじゃねえか、ガハハ」
実は山田からの受け売りであったがうまくいったらしい。
そんな同村に三玉の注意が向いている間に、井沢が隣の美唄に耳打ちした。
「美唄ちゃん、先生のグラス!」
「あ、ごめん」
美唄が慌ててビールのビンを取ろうとするが、それより先に向島が手近なビンを差し出した。
「先生、どうぞ」
「おうすまんな!」
三玉は勇んでそれに応じ、ビールを注がれながら今度は向島に「お前、女はいるのか」と問う。そして音楽が恋人である彼も同村と同じ運命を辿った。空けたグラスを頭の上にかざす向島に一同大笑い。教授は「じゃあ…」と今度は向島の隣のまりかに標的を移そうとした。それを察した井沢がすかさず立ち上がって言う。
「先生、僕には女がいます!」
「何?それはもっとけしからん、飲め!」
さすがのサッカー部は「はい!」と勢いよくそれに応じる。そしてその意志を組むように今度は長が立ち上がった。
「先生、僕はもう32歳のオッサンです!」
「何?威張るな、俺は62のじいさんだ!」
「はいすいません」
と、長もグラスを空ける…まあウーロン茶ですが。そんな体育会系コンビの活躍もあって教授も上機嫌で酒が進む。まるでわんこそばのごとく、グラスが空いたのを見極めると向島や同村がそこにビールを注ぐ。
本来なら隣に座っている…もとい座らされている美唄がお酌係りなのだが、どうも彼女は一歩出遅れてしまうようだ。先ほど井沢に耳打ちされた時のように、そのタイミングを見逃すことも何度かあった。体育会系ではないとはいえ彼女だって音楽部に足かけ5年、礼儀作法はそれなりに仕込まれてきたはずなのだが…。
「ガハハ、仕事の疲れは酒で吹き飛ばして明日もまた頑張る、これが大切だ!なあ、そうだろ」
「はい、そうですよね。私もそうします!」
とまあその分美唄は教授の言葉に全て答え、得意の笑顔も惜しみなく披露する。アイドルの隣で会の主催者本人が一番楽しんでいるのは明らかだった。
そして2時間が経過、宴はつつがなく終了するのであった。
14班諸君、これはこれで…お疲れ様。
*
午後9時過ぎ、足元のふらつく三玉を南新宿の大通りまで送り届ける。当然、タクシーを拾うのも学生のお仕事。
「先生、今夜はごちそうさまでした!」
教授がタクシーに乗り込むと、6人は合わせて頭を下げる。
「おうおう!また明日なぁ!」
気持ち良さそうな返事に続いてドアが閉まり、車は走り出す。
「ありがとうございました!」
また全員でそう言うと、タクシーが見えなくなるまで6人は頭を下げていた。…はい、よくできました。
「いやあ、教授はすごいパワーだったな」
頭を上げて井沢が言った。彼も随分飲んでいたのでやや足元が危うい。
「井沢、大丈夫か?」
心配する長に、彼は「大丈夫っすよ。むしろちょっといい感じです」と笑顔で返す。そんな彼にまりかが言った。
「今日はありがとね、井沢くん。何度も守ってくれて」
酔った爽やか青年はそこで「え?何のことかな」とおどける。美唄は「またまたあ」と彼を突っついた。
「まりかちゃんの代わりに何度も飲んでたじゃない」
「え、そうだっけ?」
まだとぼける井沢を見ながら同村は思う。成績や実家の病院の話になると少し得意げな顔もする彼だけど、こんな時は全くそれがない…やっぱりいい奴なんだな、と。アルコールの力もあってか優しい気持ちが込み上げてくる。いつぞやの大喧嘩が嘘のようだ。
「いや井沢、今日のMVPは君だよ」
そう言って同村は井沢の背中をポンと叩く。
「みんなもありがとう。ごめんね、私、飲み会とかに慣れてないから…全然面白い話とかできなくて」
そう申し訳なさそうに言うまりかに長が言った。
「何言ってんの、いつも班長に俺たち助けてもらってる。だからこれくらい俺たちがやりますぜ」
「そうだよ、秋月さん。何も気にすることないって」
と、同村も微笑む。
…パシャッ!
夜の街にフラッシュが光った。発光源はお久しぶりの美唄のデジカメ。
「お、出たな卒業アルバム委員!」
長に肩を貸されながら井沢が言う。そこには笑顔100パーセントのカメラマン。
「だってみんな、今すっごくいい顔してたんだもん」
「もお、驚いたよ美唄ちゃん」とまりかも笑う。
「遠藤さんもいい顔してるよ。カメラ代わろうか?」
「ありがとう同村くん。でもいいの、お酒入ると変な目つきになるから私…フフフ」
そう悪戯っぽく笑って彼女はデジカメをしまう。
「でも待ち望んだ14班の飲み会じゃない」
「え〜これは違うよ、あくまでこれは教授の会。14班のはちゃんと私たちで企画しなくちゃ」
そんな子供染みたこだわりをまた可愛いと同村は思ってしまう。そこで一瞬2人の目が合う。
「ちょいとお2人さん、2人の世界に入ってませんか?」
と、向島が笑う。
「もう何言ってるんですかMJさん。とりあえず今日は無事終わってよかったですね」
「確かに結構早めに終わったな」
そう返す向島に続き、まりかも「そうですね…二次会とかあったらどうしようかと思っちゃいました」と安どの顔。そこで井沢が大きくくしゃみをした。
「大丈夫か井沢」
同村が尋ねる。
「大丈夫、大丈夫。でも結構寒くなってるからみんな風邪ひかないようにしないと」
「そうだな、じゃあみんな気を付けて帰ろう。明日も早い」
そう長がまとめに入る。そこでまりかがいつもの手帳を取り出して本領発揮。
「明日は白内障の手術見学、8時に学ロビ集合です」
「了解です、班長!」
みんな一斉に答え、その場は散会に向かう。
まず足元の心配な井沢はタクシーで帰るという結論になり、長が彼を支えながら道路脇でタクシーを待つ。JR組は向島とまりか、個人主義の彼らはいつもはバラバラに帰るのだが…今夜は一緒に新宿駅へと歩き出した。電車の時刻が迫っているので少し早足だ。
「向島さーん、班長をしっかりお守りしてくださーい!」
呂律の怪しくなってきた井沢が遠ざかる2人にそう呼びかける。アウトロー留年生と4年連続特待生がまさか一緒に帰ることになろうとは…巡り合わせって不思議だね。2人は振り返って軽くこちらに手を振ると、夜の闇へと消えていった。
続いて歩き出すのは地下鉄組の同村と美唄。2人は井沢のタクシーが見つかるまでそこにいようとしたが、長が「寒いから早く帰りな」と促してくれた。
「すいません長さん、お先に失礼します」
そう言う同村に長は笑って返す。
「ホイホイ了解。あ、同村、送り狼になるなよ」
そんな一昔前のトレンディドラマのようなセリフに続き、井沢も「いや、むしろなるんだ同村!」と謎のエールを贈る。
それに対して「何言ってんだよ!」とまた過剰に反応してしまう主人公。武士の情けで顔が赤いのはお酒のせいってことにしておきましょう。その横で美唄はクスクスと笑っている。…女心ってわからない。まさに今週の空模様の如し。
「じゃあ長さん、井沢をよろしくお願いします」
そう言って歩き出す同村と美唄。
…まあ、たまにはこんな夜もいいでしょう。この調子だと美唄の望む班飲み会の実現も近いんじゃないかな?
3
それではその後をもう少し見てみよう。作者としては向島・まりかカップルも追跡してみたい気もするが…やはりここは同村・美唄ペアの方を。
午後9時半、三玉教授を見送った大通りからいつもの地下鉄駅までは少々距離があったため2人はまだ夜の街を歩いていた。
「でも今日の井沢くんの飲みっぷりは本当にかっこ良かったね。何度もまりかちゃんを助けてさあ…フフフ、ひょっとして好きなのかなとか思っちゃった」
美唄は疲れ知らずの明るさで話す。その隣で同村も笑って返した。
「また井沢に助けられた、あいつはすごいよ」
「同村くんだって結構飲まされてたでしょ、大丈夫?」
「あ、うん、大丈夫。でもこんなに飲んだのは久しぶりかな、いつも山田と飲む時はあいつが速攻で潰れちゃうから」
と、そこまで言って同村は昨日山田が話していたことを思い出す。美唄に関する悪い噂…でも今隣にいる彼女はそれとは程遠い笑顔を見せている。
「山田くんかあ、体育会系のスキー部だもんね。それが同村くんと仲良しってなんか不思議」
「…そうだな」
同村はそう微笑む。どんな疑惑よりも今目の前にある彼女の笑顔を信じよう、そう決めたのだ。
2人が歩いているのはビジネスビル街、この時刻にはほとんど人通りがない。ふいに冷たいビル風が吹き抜け、2人の会話を遮った。そして数秒の沈黙をおいて美唄が言った。
「ごめんね、先生のお酌…うまくできなくて」
意外な話題、それ以上に突然しおらしくなった彼女の声に同村は少し戸惑う。
「いや、そんなことないよ。俺だってうまく話せなかったし…。本当に井沢に感謝だよ」
彼女の返事はない。その沈黙を払うように彼は続けた。
「遠藤さんはあんまり好きじゃないの?お酌するのとか」
「別にそうじゃなくて…ハックション」
口を開いた美唄はそこで可愛くクシャミヲする。
「大丈夫?」
「うん、大丈夫。もう秋だね〜こんなに寒くなるなんて思わな…」
言葉を最後まで聞く前に、同村は彼女に自分のハーフコートをかけた。この男、やはり妙な所で大胆だ。
「同村くん、いいの?」
さすがの歌姫も少し驚いて立ち止まった。
「うん、せっかくだし」
「ありがとう。フフフ…」
「な。何かおかしいかな?」
慌てる同村に彼女は嬉しそうに首を振る。
「ごめんね。なんか、せっかくだからってのが面白くて。でも、フフフ…同村くんらしい」
「べ・別に変な意味は…」
動揺する同村の隣で彼女は笑い、やがてそれを弱めるとゆっくり彼に背を向けた。そして静かに空を見上げた。その視線の先には…排気ガスにネオンが映る灰色の夜空。
彼女の行動の意図が読めず、同村は黙って見守る。やがてそのままの姿勢で美唄は口を開いた。
「同村くんは…どうして医学部に?」
また話題が変わった。困惑する同村をよそに彼女はそのまま答えを待っている。彼は少し考えてから答えた。
「医学に…興味があったからかな。この学問を知らずにいるのはもったいないなって。だから、医者になるぞ!、みたいな覚悟…俺にはないんだよね」
美唄の背中に頼りない声が投げかけられる。
「人間のことを知りたかったっていうか、なんか、色々なことを納得したかったんだ。生きることとか、死ぬこととか…病気のこととか」
「ふ〜ん、すごいね…」
彼女は振り返らずにそう言った。
「いや全然すごくない…っていうかむしろダメなんだよ。もう5年生なのに未だに医者になる決断ができてないなんて。情けないよね、ハハハ…」
同村は無理におどけてみせる。
「私はね…」
美唄の声は今まで聞いたことのない儚さを帯びていた。そして彼女はまた話題を変えて言う。
「私、北海道生まれなの。私のお母さんが高校の修学旅行で行った時に、札幌駅でみんなとはぐれて迷子になっっちゃってね、その時に道を教えてくれたのがたまたま駅にいたお父さんだったの。お父さんは地元の高校生でね、運命の出会いってやつかな」
明るく振舞おうとはしているがいつもの彼女とは違う…同村はそれを感じながら黙って聞いていた。
「それで2人は意気投合しちゃってね。お母さんは次の日の自由行動を抜け出してお父さんと人生初のデートをしたの。お父さんもただの高校生だからそんなお金なんかないし、笑っちゃうんだけど、自分の住んでる町にお母さんを連れて行ったんだって」
そこで彼女の声は優しくなる。
「そして2人は正式に付き合うことになるんだけど…その初デートの町の名前が美唄っていうの。美しい唄って書いて美唄。お母さんもお父さんもこの地名が好きで、それで私に付けたんだって。名前としてはちょっと変なんだけどね」
美唄は空から視線を下ろし、少しだけ笑った。
「お母さんは高校卒業したら北海道の看護学校に進学して、お父さんは自衛隊に入って…。そのうち2人は結婚、美唄の町で生活を始めたの。そして私が生まれた…。
でも、私が生まれてすぐお父さんは怪我をして自衛隊をやめることになっちゃって…。自衛隊が生きがいだったお父さんは、他の仕事は長続きしなくて、だんだんお酒をたくさん飲むようになって…」
再び彼女の声が沈んでいく。
「私が小学生の頃も、しょっちゅう朝から飲んで酔っ払ってた。だんだんエスカレートしてね、お母さんにも暴力振るうようになって…。私が中学生の時についに離婚、お母さんと私は東京の実家に戻ったの」
同村は思わすそこで「お父さんは?」と尋ねた。
「今は精神病院にいるんだって…ずっと会ってないけどね」
美唄はそこでまた空を見た。
「それでかな、医学部に来ようと思ったのは…病気のことをちゃんと勉強すれば、お父さんをまた好きになれるかなって。まあ、お母さんが看護師さんってのもあるんだけどね」
同村は彼女の後ろ姿を見つめ続けている。
「私ね…私、美唄って名前大好き。子供の頃からお父さんとお母さんがケンカすると、いつも一人で歌って遊んでたの。だから、私、歌が大好き。美しい唄なんて、本当に嬉しい名前…。だから、お父さんにもお母さんにも感謝してるの」
彼女は何を言おうとしているのだろう…同村はそれを考え続けていた。
「同村くん、私ね…」
その声は震えている。そこでまた彼女が少し黙った。
「遠藤さん…」
「お酒も入ってるし、告白しちゃおうかな」
当然その言葉に同村は淡い期待を抱く。愚かな男は自分の脈が速くなるのを感じていた。強くなる鼓動が全身を打ち付けている。
「同村君、私ね…」
そこで彼女は振り返る。そして両手の拳を握り締め、意を決したようにはっきりと言った。
「眼が、悪いの」
*
美唄に見つめられたままそう告げられ、同村の思考は一瞬止まる。「…え?」と間抜けな聞き返しをするのが精一杯だった。
「あの、あのね」
彼女はさらに声を震わせて続ける。
「さっきの飲み会のお酌もね、わざとやらなかったんじゃないの。見えなかったの…私、視野が狭くて…先生のグラスに注意はしてたんだけど、やっぱり何回も見逃しちゃって」
「視野が…?」
美唄は黙って頷く。そこには泣き出しそうなのを必死にこらえるかのような、張り詰めた顔があった。そして震える唇で彼女はその病名を告げた。
同村は言葉を失う。消え入りそうな声の中にかろうじて聞き取ったその病名…知っている名前だった。だが、詳しい症状などは正直あまりよく思い出せない。それを察したのか彼女が続けた。
「夜盲症状から始まって、ちょっとずつ視野が狭くなって、ちょっとずつ見えなくなる病気…。まあ教科書にはちょろっとしか載ってないけどね」
美唄は笑う…が、その強がりは明らかだった。同村は眼科実習の前に予習した記憶のページを必死にめくる…そうだ、確かにあった。確かそれは…末期には失明に至ることもある難病指定疾患。治療法は…ない。
「最近ちょっと進行が速くて…自分でもわかるくらい、1年前より視野が明らかに狭いの。日常生活とか、本読んだりとか…ちょっと不便になってきててね」
それを聞いた瞬間、同村の頭の中にこの半年間の彼女の姿がフラッシュバックする。
彼女は駅の人ごみで歩き難そうに自分の後ろをついてきていた。夜の駐車場など暗い場所ではみんなの最後尾を歩いていた。手術見学の時、術野を覗き込もうとして先生にぶつかりそうになっていた…!
なんてバカだったんだ、俺は。どうして気付かなかったんだ、ずっと…彼女を見ていたのに。あんなに一緒にいたのに…!山田が言っていた街で同級生を無視する噂…あれもそうだ、視野が狭いから彼女にはわからなかったんだ!
同村の心を自己嫌悪の拳が容赦なく殴りつける。打ちのめされながら返せた言葉は「そうだったんだ…」だけだった。淡い期待であれだけ高鳴っていた彼の鼓動は、いつしか完全に影を潜めていた。
「だからこれからも迷惑かけちゃうかもしれないと思って、一応言っておこうかなって…」
美唄はまた無理に微笑む。同村は混乱する頭を整理するように言葉を搾り出した。
「医学部に来る前から知ってたの?…病気のこと」
彼女は頷く。
「この目ね…お母さん譲りなの。子供の頃からお母さんに似て自分は目が悪いんだなって思ってた。でも医学部に行きたいって言った時にお母さんが教えてくれたの。この病気って、人によって進行のスピードが違うし、お母さんも今のところ普通に暮らしてるから…まあ大丈夫でしょって割とのん気に思ってたんだけど…」
美唄はそこで少し俯く。
「私の場合は…ちょっと進行が速いみたい」
「遠藤さん…」
「あ、でもまだ別に今はたいしたことないから、そんなシリアスにならないで!なんか、キャラ違うよね、ハハハ…」
美唄は笑う…が、それが余計に痛々しい。
「別に隠してるわけじゃないし、音楽部の人はほとんど知ってるの。ほら、ライブハウスとか結構暗いから、言っておかないと迷惑かけちゃうから」
「そうなんだ…」
彼は思い当たる…そういえば向島は時折暗い所で彼女を気にかけていた。知っていたのだ、このことを。
「14班のみんなにはなんか言い出せずにいて…。みんなと違っちゃうのが怖かったのかな。同村くんは、よく人と違うことがかっこいいって言うけど…」
「いや、それは」
同村は慌てて言葉を探す。
「いいの、私もそうなの。人より目立ちたいとか思うから…だからボーカルとかできるんだし。でも、やっぱり病気が進行してくると…みんなと同じがいいなってちょっと思っちゃったり」
彼女はそこでまた同村に背を向けた。
「別に見えなくなっても死ぬわけじゃないし、今日実習で見たような便利な道具だってたくさんあるし…、大丈夫だってわかってるの。それにポリクリでもっともっと大変な運命の患者さんをたくさん見てきたんだから。…この程度でくじけちゃいけないよね。わかってるんだけどさ」
強がらなくても…と言い掛けて同村はそれを飲み込んだ。そんな幼稚な理屈はとうに通り過ぎた先を彼女は生きている。
「それに、私が苦しんだらお母さんがきっと悲しむから…。お母さんのせいじゃないのに、きっと自分を責めちゃうから。お父さんのことだけでも大変なのに…。大丈夫、私は大丈夫なの」
美唄はまるで自分に言い聞かせるように大丈夫とくり返す。同村が見つめる彼女の後ろ姿…この小さな体でたくさんのことを背負って生きてきたのだ。そこで彼の頭にふと浮かぶ言葉。
…『運命』。
確か、美唄はこの言葉を患者に対して使っていたことがあった。人生は変えられても運命は変えられない、と…。
「でもね…でもね…やっぱり時々は負けそうになるの。試験でマークシートをずらして塗っちゃったり、誰かの大切な物を踏んで壊しちゃったりすると、とっても情けなくなって…。大丈夫、大丈夫なのよ」
彼女が大丈夫、という度に同村の胸が絞めつけられる。
「でももし大学に知られて、大騒ぎになっちゃったらどうしようって…。みんなと一緒に卒業したり、国家試験を受けさせてもらえるかなぁって」
彼女が昨日午前の実習を休んだ理由がようやく同村にわかった。眼科の手技の実習では、学生がお互いを診察することになる。もし眼底を覗かれたら…その特徴的所見から彼女の病気は露呈してしまうのだ。
「そ、そんな、遠藤さん!」
同村はずっと言葉を探していた。
「え、遠藤さんの明るさとか、元気に、いつも俺たちはパワーをもらってるよ!それってすごいことだよ!きっと少しくらい目が悪くても、君のやれることはいっぱいあるよ。きっと…きっと…」
「ありがとう、同村くん」
美唄は必死の同村に振り返らずに言った。
「前にも言ってくれたよね。私は人の心をよく見てるって…。あの時、本当に、本当に嬉しかったんだよ。私ね、病気を知ってから色々敏感になったの。いかに健康な人の些細な一言が、病気の人を傷つけてるかって…。だから、私は目がよく見えない分、人の心をよく見ようって…そんなお医者さんになれるかなって」
「そうだよ!」
「でも、でもね…急にオールラウンド研修が義務化されちゃったでしょ?卒業したら全部の科を回って何でもできる医者を作るって…。私、この目じゃ外科の手術とか絶対無理だもん」
同村たちにとってはただ面倒くさいとぼやく程度の新制度。しかし彼女にとってそれは人生を覆すものだった。
「何でもできる医者…国がそれを求めてるなら、私みたいな人間…必要とされてないのよ」
同村は言葉が出てこない。ただ己の無力さを感じながら、彼女の背中を見つめていた。
「あ〜あ、目が悪くなって、一番未来が見えなくなっちゃったよ」
明るい調子を装っていたが、それは涙声だった。
「どう、同村くん?今の言葉、文芸部的には結構イケてない?」
振り返らずに言う美唄…彼女は、泣いていた。やがてグスッグスッと漏れる声が同村に聞こえてくる。
「美唄!」
そう叫び、同村は彼女を後ろから強く抱きしめた。
*
「お、俺、何もできないかもしれないけど…絶対、君を守るから。君が笑顔でいられるように、何でも、何でもするから…」
同村は思いつくままの言葉を必死に並べた。それはまとまりなく流れも悪い…文芸部の彼あるまじき乱文だった。
「お、俺、君が…」
同村の腕の中で、美唄は微動だにしない。
「好きだ!」
夜のオフィスビル街に声が響いた。そしてまた冷たい風が吹き抜けていく。通り過ぎる冷気の中、2人はそのままの状態で動かなかった。
「ありがと、同村くん」
彼女が静かに言った。その声に、同村は腕の力を抜く。
「優しいね、同村くんは…」
美唄はゆっくり振り返りながら、そっと同村の腕を振りほどく。
「びっくりして涙止まったよ」
彼女は笑う…いくつもの涙の筋が彼女の乱れた髪を頬にへばりつけていた。
「ありがとう…同村くん。でも…ごめんね」
穏やかな声がそう告げる。同村はまだ固まっている。
「同村くんは優しいから…でもそれは…恋愛じゃないよ、きっと。私もね、今日はちょっと気持ち緩んじゃっただけ」
「いや、俺は…」
「病気の子と言えて、スッキリしたよ。そのうちみんなにも話すから。あ、これも…ありがとね」
美唄は同村にコートを返した。
「やっぱり寒いから、私、タクシーで帰るよ」
コートを力なく受け取りながら同村は「あ、あの…」と伺う。
「じゃあね同村くん、また明日!」
「遠藤さん…」
歩き出そうとする彼女の手首を掴み、そう呼びかける。美唄はそこで振り返る…感情を押し殺した顔で。
「私、一人で大丈夫だから」
はっきりそう言うと彼女は微笑み、「だってまだ10時前だし」と付け加えた。同村も握っていた手を離す。
「じゃあ、おやすみ!」
最後にそう言うと、美唄は振り向かずに明るい通りに走って行った。
男は何も言えないまま、コートを持って立ち尽くすしかなかった。
*
午後10時過ぎ、いつもの地下鉄に揺られる同村。車内はそれほど込んではいないが座る気にはなれなかった。車窓に流れる闇を見ながら彼はずっと考えている。
…失恋。いやむしろそんなことはどうでもよかった。窓に映るのは…何もわかっていない、何もしてあげられないちっぽけな男の姿だった。
きっと…同じ立場にならない限り彼女を理解するなどできないのだろう。
この医学部と言う濁流の中、遠藤美唄は一歩ずつ施す側から施される側に近付きながら歩いているのだ…どこに辿り付くのかもわからない未来へ。
自分が見ることができないかもしれない卒業アルバム、その写真を笑顔で撮影する彼女の気持ちになど…到底届くはずもない。
やがて液に到着しドアが開く。その瞬間車内に怒号が響いた。見ると不機嫌そうな男が気弱な初老の女を責めている。
「おいお前、そこに立ってたら俺が降りられないだろ!どうしてどけって言ってるのにどかねえんだよ!」
すごんでくる男に相手は平謝りだ。女は頭を下げながら呂律の悪い口調で訴える。
「ごめんなさいごめんなさい、私、耳が悪いもので…気付かなくて本当にごめんなさい」
男は舌打ちするとそのまま電車を降りていった。悲しさと情けなさで沈む女の顔…それを見て同村は思う。
…わかってあげられない、わかってもらえない、これはどうしようもないことだ。
誰もが自分の運命を生きなくてはいけない。他人賀どれだけ考えようと、どんな言葉をかけようと、一人でそれに向き合わなければならない。
美唄の運命と闘えるのはただ一人、彼女だけなのだから。
*
翌日木曜日の朝8時、学生ロビーには美唄のいつもの元気な声が響いた。空の雨雲も消え、秋の陽光が窓辺に眩しく差し込んでいる。
「おっはよー!」
その笑顔もいつも通りの100パーセント。みんなが「おはよう美唄ちゃん」「美唄ちゃん、今日も元気だね」と口々に返す。
「おはよう…遠藤さん」
と、少し小声で同村。
「おはよう同村くん。どうした、元気ないぞ!二日酔い?ハハハ…」
美唄は大はしゃぎだ。
「じゃあみんな揃ったので行きましょう。眼科実習はまだ終わってません、今日は白内障の手術見学からです」
まりかがそう言い、今日も14班は歩き出す…今、目の前にある現実へと。
11月、療養病棟編に続く!